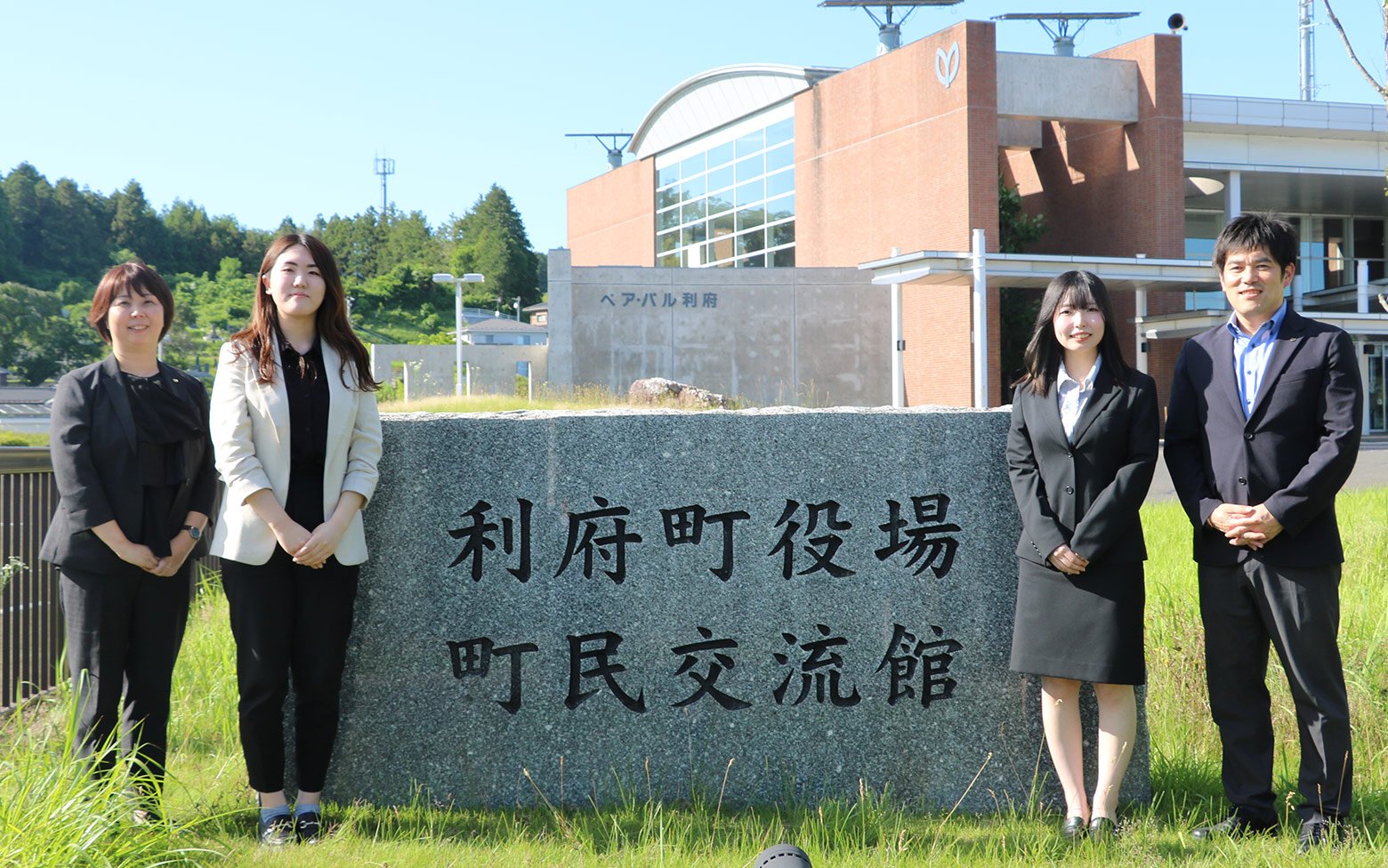宮城県宮城郡利府町は、住民サービスの向上や行政事務の効率化、地域全体のデジタル化を見据えたDX戦略を推進しています。そうした中で課題となっていたのが、取引事業者から送られてくる請求書の処理です。そこで『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入することで、請求書の収受から支払伝票の起票、承認・審査に至るフロー全体を一貫して電子化・ペーパーレス化する基盤を整えました。
サービス導入の背景と効果
-
課題
- 町役場の人手不足が深刻化する中で庁内業務の効率化が必要
- 紙書類のスキャンやファイリングといった煩雑な作業負担を軽減したい
- 地域社会全体のデジタル化を後押し、町の活性化につなげたい
-
決め手
- 取引事業者が無償で利用できる電子請求の仕組みを提供
- 民間企業のみならず自治体においても豊富な実績
- 財務会計システムとのAPI連携が可能
-
効果
- すでに導入済みの電子決裁に電子請求を加えた職員の作業負担軽減
- 運用開始時点での約260社が電子請求、年間1,200時間超の削減を試算
- 請求書の収受から支払伝票の起票、承認・審査に至るフローを高速化
地域社会全体のデジタル化を見据えたDX戦略
まずは利府町について、概要をご紹介ください。
総務部 デジタル推進室 室長(以下、デジタル推進室長):
利府町は、宮城県のほぼ中央部に位置しています。総面積は44.89平方キロメートルで、東方部を松島町、西方部を富谷市、南方部を仙台市及び多賀城市、塩竈市、北方部を大和町と大郷町に接するとともに、3つのJR駅と4つのインターチェンジを有し、交通アクセスに優れているのが特徴です。
仙台市の中心部まで約30分の通勤、通学圏でもあることから、ベッドタウンとして子育て世帯にも人気があり、さらに2002(平成14)年のFIFAワールドカップサッカーや東京2020オリンピック唯一の有観客会場となった宮城スタジアム(宮城県総合運動公園)、日本三景松島の一角をなす表松島の海、特産の利府梨といった豊富な地域資源を有しています。
町としてもこれらの特長を最大限に生かしつつ、全国的な人口減少・少子高齢化の波を乗り越えていくため、協働でまちづくりに取り組む「利府町総合計画」を打ち出しており、将来的に単独での市制移行を目指しています。

自治体DXへの取り組み状況についても、ぜひ教えてください。
デジタル推進室長:
地域社会のデジタル化を構築していく観点から、国のデジタル化に対する方針や自治体のDXへの推進要請などを踏まえ、本町のDX推進に向けた方針、関連する個別施策、ICTの戦略的な活用などを取りまとめた「利府町DX推進計画」を定め、利用者目線に立った住民サービスの向上や行政事務の効率化に取り組んでいます。
私たちデジタル推進室はその旗振り役として、RPAや生成AIの活用、ペーパーレス化の推進のほか、地域社会全体のデジタル化を後押ししています。
会計業務における電子決裁や電子請求への取り組みも、DX戦略の一環なのでしょうか。
デジタル推進室長:
おっしゃるとおりです。庁内業務の効率化もさることながら、本町と取引のある事業者様の負担軽減を図り、地域の経済を活性化させていくためにも、電子決裁や電子請求の導入は不可欠です。
業務負担軽減を目指し電子決裁システムを導入、次いで請求書処理をデジタル化
これまでの電子化の実施状況と成果、課題についてお聞かせください。
上下水道部 上下水道課 経営係 主事(以下、主事):
本町では令和6(2024)年1月に先行して公会計システムの電子決裁機能を導入し、事業者様から送られてくる請求書および添付書類などの電子化・ペーパーレス化を進めてきました。電子決裁機能を導入してからは、会計課での請求書原本保存が必要なくなったため、例年ファイル50~70冊になる書棚のスペースを削減できたことも、得られたメリットの1つです。

ただ、これによって庁内業務が効率化されたとはいえ、紙請求書のスキャンが必要であり、完全とはいえませんでした。当時、私はデジタル推進室に所属しており、紙で届く請求書を電子化する作業を担っていたのですが、請求書1枚ごとのスキャンや煩雑な原本整理などの処理に1回あたり2~3分ほど時間がかかっていました。
会計課 会計係 係長(以下、会計係長):
請求書や添付書類の中にはA4サイズからはみだすものもあり、スキャンしたところ、肝心の金額や日付などが途中で切れてしまうこともあります。

収受する請求書の処理は、毎年何件くらいになりますか。
会計課 会計係 主事(以下、会計係主事):
支出伝票の処理件数は年間約2万2,000件です。ただし複数の請求書が綴じられている場合があるため、実際に支払伝票を起こす請求書の件数は、それより若干上回ります。

紙で請求書を受け取った後の基本的なフローを教えてください。
主事:
郵便で役場に届いた請求書を総務課が代表して受け取り、19課、1室、1センターの部署ごとに仕分けを行い、それぞれの配下の各係の担当者が収受します。さらに担当者は請求書を複合機でスキャンしてPCに保存するとともに、原本を各係でファイリングして保存します。一方で財務会計システムから支出命令を起票し、電子化した請求書や契約書などを添付した上で電子決裁システムに登録し、上長の承認および会計課による審査を受けるというのが大まかなフローです。
支出命令書が承認されるまでには、かなり時間がかかりそうです。
主事:
実際に私自身も上下水道課の経営係に異動した現在、この役割を担っているのですが、10日に一度の締日ごとに事業者様から寄せられてくる20件程度の請求書を処理するのに、3時間近くを費やしています。単純な試算をすれば、年間2万2,000件の処理では約3,300時間が費やされていたともいえます。
デジタル推進室長:
繰り返しになりますが、請求書を1件ずつスキャンする手間や、その後の煩雑な原本管理は依然として大きな課題として残っており、これらの業務負担を抜本的に解決するため、請求書の電子化が必須という考えに至りました。システム連携によるさらなる効率化を見込んでいます。
電子請求書の導入は、いつ頃から検討を始められたのですか。
主事:
令和5(2023)年6月に参加した自治体職員向けオンラインセミナーにて、デジタル田園都市国家構想推進交付金を利用して電子請求書を導入した自治体の事例を拝見したのが最初のきっかけです。同時に『BtoBプラットフォーム 請求書』についても強い興味を持ち、本町でも導入に向けた検討を開始しました。
既存の電子決裁と共に、『BtoBプラットフォーム 請求書』によって電子請求書の受け取りを可能とすることで、庁内業務のペーパーレス化や業務効率化がさらに促進され、ひいては各係の担当者の負担軽減を実現できると期待しました。
他社の電子請求ソリューションと比べ、『BtoBプラットフォーム 請求書』のどんな特徴に注目されたのでしょうか。
主事:
先ほどのセミナーで事例紹介が行われた自治体をはじめ、『BtoBプラットフォーム 請求書』は官民を問わず非常に多くのユーザーに活用されていることに、まず注目しました。加えて本町からの招待によって、事業者様が無償で電子請求を始められることに魅力を感じました。これにより、本町のDX戦略において当初からの目的としている地域社会全体のデジタル化にも貢献できると考えました。
また、本町で別途利用している財務会計システムと電子請求の自動連携も視野に入れているのですが、この要件について『BtoBプラットフォーム 請求書』はすでに実績を有していたことも、選定の決め手の1つとなりました。
電子請求の利用拡大を進め、地域全体のデジタル化へ
『BtoBプラットフォーム 請求書』導入後の各部署の職員の皆様の反応はいかがでしたか?
会計係主事:
職員の反発や抵抗はほぼありませんでした。すでに様々な業務の電子化が進んでいることもあり、『BtoBプラットフォーム 請求書』を受け入れる土壌はしっかり整っていたと言えます。
請求書の電子化・ペーパーレス化による作業時間の削減効果は上がっていますか。
会計係長:
最初から電子化された状態で送られてくる請求書に関しては、スキャンや原本整理などの煩雑な作業がなくなるため、各係の担当者の負担は確実に軽減しています。
また、『BtoBプラットフォーム 請求書』を通じて送られてくる電子請求はフォーマットも統一されているため、会計課での審査も容易になりました。従来の紙の請求書で、口座情報などの記載位置がばらばらの書面から項目を探してペンでチェックしていた状況よりも確実で、書類の不備も迅速な発見が可能です。差し戻しの時間を短縮しました。この効果は、支払の遅延防止にもつながっています。
事業者様の『BtoBプラットフォーム 請求書』の利用はどの程度でしょうか?
デジタル推進室長:
率直なところ、そこは当初不安を感じていた部分です。本町が取引している事業者様には、デジタル活用に不慣れな地場の企業も多く、利用いただける数が少ないのではと思ったのです。
実際に本町の各部署が取引している事業者様約700社に、ハガキや説明会を通じてご案内したところ、運用開始の段階で、1/3以上の約260社に参加いただけました。数字としては決して高い比率ではありません。それでも推定8,000件超の請求書が『BtoBプラットフォーム 請求書』を通じた処理に変わり、年間約1,200時間の作業時間を削減できる試算です。
主事:
電子請求の普及率はまだ十分とは言えませんが、そうした中でも驚いたのは、すでに『BtoBプラットフォーム 請求書』を利用している事業者様もおり、ご自身で所有しているアカウントで利用させてほしいという要望が寄せられたことです。
また、「これまでDXという世の中の動きについていけなかった。取り組んでいくべきだという意識はあるものの、知識がなくてなかなか手につかなかったため、今回の電子請求への案内は良い機会となった」という前向きなお声も頂戴しており、こうした事業者様の反応からも、今後の普及に向けた明るい可能性を感じています。
電子請求の利用促進と定着化に向けて、どんな取り組みを行っていますか。
主事:
事業者様にご案内や説明会を行った際に、かなりのお問い合わせをいただきました。最も多く寄せられたのは運用に関する質問だったことから、個別に丁寧な回答を町の方針とともにお伝えしています。また、インフォマート社の協力を受けて、町のホームページ上に電子請求についてのFAQ(よくある質問と回答集)コーナーを作成するなど、認知拡大と普及に向けた対応を行っています。
庁内業務のさらなる効率化やDX推進という観点からも、今後に向けた取り組みをお聞かせください。
会計係長:
喫緊の大きな課題として残っているのが、財務会計システムと『BtoBプラットフォーム 請求書』間のAPIを利用した自動連携の実現です。財務会計システム側のアップデートを持って、令和7(2025)年度中には完了させる予定です。これにより請求から支払に至る業務フロー全体の一層の最適化を図りたいと考えています。
デジタル推進室長:
このように本町はDX推進において、まだ多くの課題を抱えているだけに、引き続きインフォマート社のサポートにも大いに期待しています。
※掲載内容は取材当時のものです。