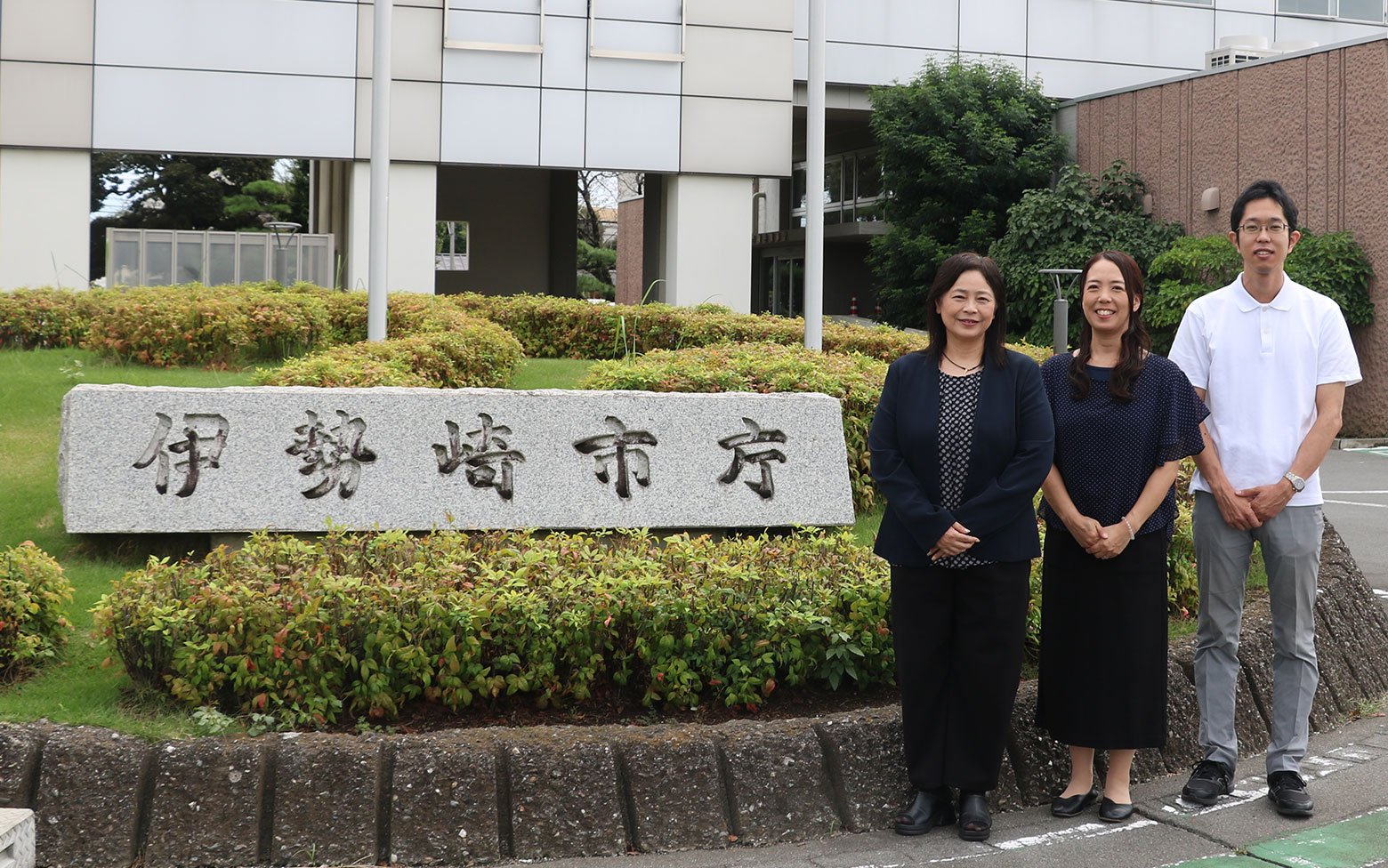群馬県伊勢崎市は、財務会計システムの電子決裁機能と連携する電子請求書システムとして『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入。年間約7万件受領する請求書処理の効率化を図っています。前年度に取引のあった地域の事業者のうち約1,000社に案内したところ、その約30%が早々に登録するなど、庁内と事業者の双方の業務効率化に寄与するDX推進に向けて好調なスタートを切ることができました。
サービス導入の背景と効果
-
課題
- 年間約7万件受領する請求書の処理を効率化したい
- 紙で受領する請求書について起票に1件あたり10~20分の処理時間が発生
- 出先施設で受け取る請求書に不備があった場合3~4日のタイムロスが発生
-
決め手
- 「次期財務会計システム導入事業電子決裁ワーキング」にて検討
- 国内企業(事業者)の1/3が利用している実績を評価
- 導入済みの電子決裁機能とのスムーズなデータ連携が可能
-
効果
- 案内を行った事業者の内、約3割が電子請求書システムに登録
- 電子請求書については1件あたりの起票処理時間を5分程度に短縮
- 削減できたリソースを、よりクリエイティブな業務にシフトできるように
ベテラン職員でも起票に1件20分程度かかるなど紙中心の請求書処理が大きな業務負担に
伊勢崎市について概要をご紹介ください。
会計課 課長補佐(以下、課長補佐):
伊勢崎市は「銘仙」に代表される織物のまちとして発展してきました。平成17(2005)年に旧伊勢崎市、佐波郡赤堀町、東村及び境町が合併し、新たな伊勢崎市としてスタートしてから20周年を迎えた令和6(2024)年度は、富岡製糸場と絹産業遺産群「田島弥平旧宅」の世界遺産登録10周年が重なるアニバーサリーイヤーとなりました。
市の大部分が平地で、強い地盤の上に立地していることも特徴です。自然災害が比較的少ない地の利に加え、便利な道路交通網にも恵まれており、近年では多くの製造業や大規模商業施設が進出するほか、近郊農業も盛んに行われています。また、伊勢崎市は「暮らしやすい都市」と言われており、令和7(2025)年4月1日現在の人口は21万1,651人で、人口推移も増加傾向にあります。
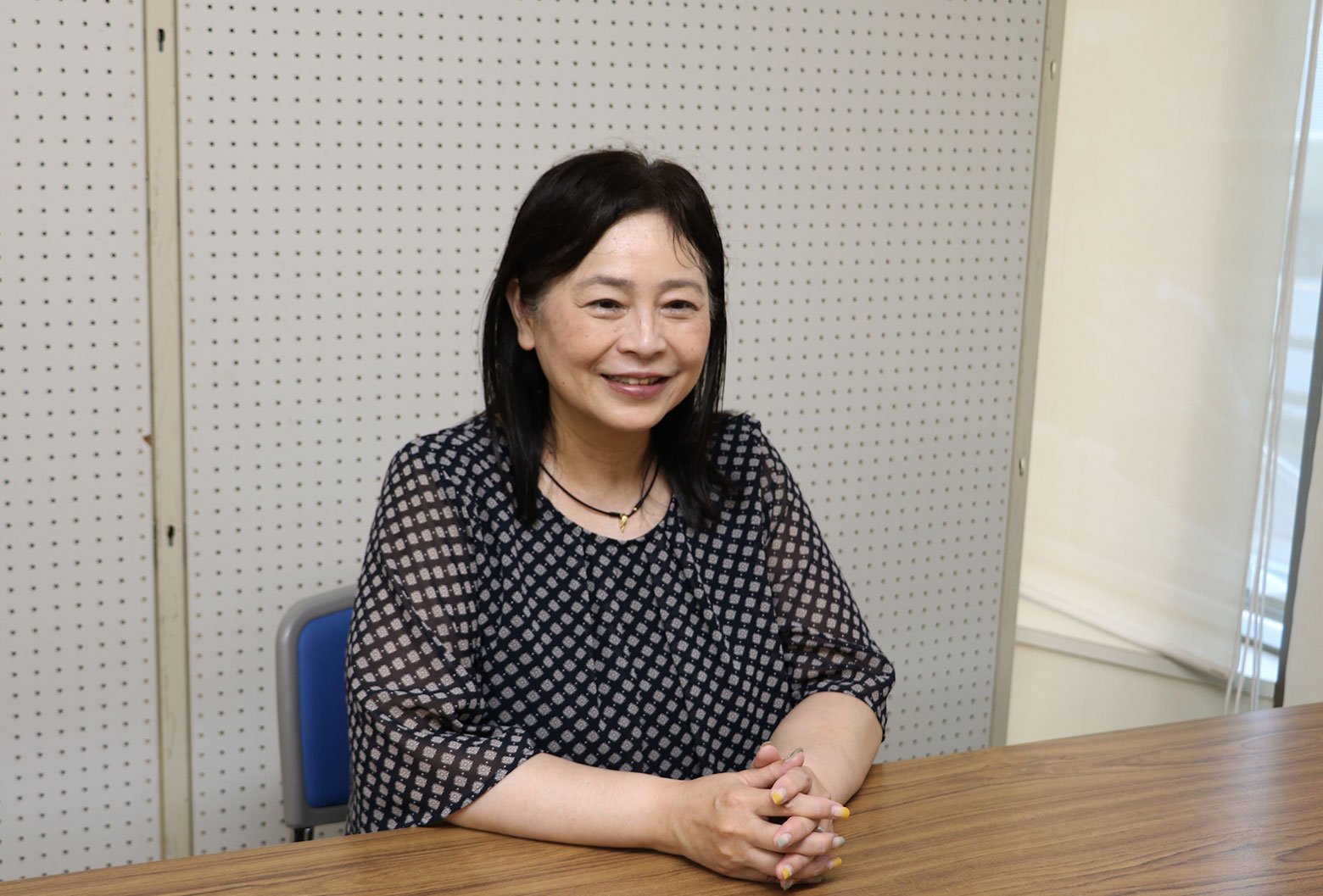
行政DXに向けては、どんな取り組みを行っていますか。
会計課 係長(以下、係長):
今年度から新たな総合計画基本構想に基づく「共生・共創・行財政政策」がスタートし、「効率的かつ安定的な行財政経営の推進」の実現に向けた重点事業として「行政DX推進事業」および「情報システム開発事業」を展開しています。その一環として取り組んでいるのが、財務会計における電子決裁と相乗効果を発揮する電子請求書の導入です。内部事務の効率化にとどまらず、地域の事業者の業務改善にも資する内向きと外向きの両面でのDXを目指しています。

積極的に行政DXに取り組まれているようですが、請求書のやり取りについては、どのような取引先からどのような形で請求書を受け取っているのでしょうか。
課長補佐:
取引先は市内の事業者が中心で、納品と同時に請求書を提出していただいています。約9割が紙の請求書で、残り1割がPDFファイルです。紙の請求書の中には手書きのものも3割程度あり、文字が読みづらい場合には、再提出を依頼せざるを得ないケースもかなりあります。
請求書の受取件数は、年間でどれくらいありますか。
係長:
当市全体で受領する請求書のうち、会計課で取り扱うのは一般会計と特別会計の一部の科目のみです。1,000社を超える事業者から年間約7万件の請求書を受領しており、ほぼ同数の支出命令書を発行しています。
請求書を受領した後のフローを教えてください。
会計課 主査(以下、主査):
請求書を受領した各所属部署の担当者は、納品などの履行確認および書類の不備の有無を確認した後、財務会計システムにて支出命令処理を行います。なお、紙の請求書についてはスキャナでPDF化を行います。
以降、導入済みの電子決裁機能を通じて課内の承認フローを経た後、会計課審査係への伝票回送・添付書類提出、会計課による審査・承認および紙書類の仕訳・計算・支払・消込処理、担当課における差引簿の確認というプロセスに進みます。

請求書業務には、どれくらいの作業時間を費やしていましたか。
係長:
請求書の照合と内容確認、書類不備に関するやりとり、口座情報確認、証拠書となる請求書の整理および原本のファイリング処理など、煩雑な手間がかかります。紙の書類をスキャンしてPDF化し、適切なファイル名を付けて所定のフォルダに保管するといった作業まで含めれば、かなり手慣れた職員であっても、請求書1件あたり10分~20分の処理時間がかかってしまいます。
主査:
最もタイムロスが大きいのは紙の請求書の不備による差し戻しが発生した際の対応で、特に私が以前所属していた出先施設でそれが顕著です。審査係から指摘を受けた請求書を本庁まで出向いて回収し、業者に戻して修正を依頼し、再発行された請求書をあらためて提出する必要があり、すべての作業が完了するまでに3~4日の余分な時間を費やす場合もあります。
財務会計システムとの親和性を評価し『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入
そうした課題を解決するために、電子請求書の導入を目指したのですね。
係長:
はい。前述したとおり財務会計システムを基盤とする電子決裁の仕組みがすでに導入されていましたので、そこに電子請求書システムを実装することで庁内事務にDXの恩恵を効果的に波及させ、職員の定型事務にかける時間を削減したいと考えました。加えて事業者側の作業時間やコスト負担を最小化するなど、地域全体としての業務の生産性向上にも寄与したいと考えています。
課長補佐:
職員の業務効率化によって生み出された時間を、人材育成や住民との対話、新たな企画の検討など、よりクリエイティブな仕事に振り向けていきます。
電子請求書の導入は、いつから検討を始めたのですか。
課長補佐:
令和5(2023)年度に「次期財務会計システム導入事業電子決裁ワーキング」が立ち上がり、電子決裁機能をもった財務会計システムの導入およびその後の運用を検討する中で、電子請求書サービス連携に着目したのがきっかけです。また、前年度から押印省略と財務会計の電子決裁導入を見据えて財務規則改正を実施するなど、庁内調整ならびに事業者への周知を実施してきました。
『BtoBプラットフォーム 請求書』を選んだのは、どのような理由でしょうか。
係長:
令和5(2023)年の夏頃にワーキングの協議の中で、『BtoBプラットフォーム 請求書』であれば電子決裁機能とのスムーズなデータ連携を行える、という点が高く評価されたのが、決め手となったポイントです。また、国内企業(事業者)の約1/3である110万社(検討時)が利用している実績も採用を後押ししました。
『BtoBプラットフォーム 請求書』はいつから運用を始めましたか。
課長補佐:
令和7(2025)年1月です。ただ、いきなり全事業者を対象にするのではなく、まずは6社からスモールスタートしました。取引件数が特に多い事業者4社に、すでに『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入していた2社を加えた6社です。
係長:
このファーストステップを経て、電子請求書の業務フローを確認するとともに、会計課内で詳細なマニュアルを再作成しました。また、インフォマート社の協力をいただきながら職員への説明会や、事業者向けのWeb説明会を実施し、2カ月後の同年3月より大々的な運用を開始しています。
請求書処理が1件あたり5分まで短縮され、高頻度取引先の明細処理も一元化
結果として、どれくらいの事業者が電子請求書に移行しましたか。
係長:
過去に取引実績のある約1,000社の事業者に案内を行ったところ、そのうちの約30%に相当する339社にログインをいただき、令和7(2025)年10月時点で月間約200件の請求書を電子で受領しています。
これは非常に喜ばしい反響です。電子請求書の利用率について、「導入当初30%、将来的に50%以上に高めて職員の仕事を楽にする」という“強気”の目標を掲げていたのですが、期待どおりの上々のスタートを切ることができました。
課長補佐:
市内の小さな個人商店も招待に応じていただくなど、反響の大きさに私たち自身も驚いています。
どんな成果があらわれていますか。
主査:
職員からは対象の電子請求書データを選択するだけで財務会計システムに規定項目が自動転記されるため、「楽になった」と評価の声が寄せられています。前述したとおり、これまでの紙の請求書では郵送物を開封して内容を確認し、スキャンし、データを財務会計システムに入力する一連の作業に10~20分程度かかっていましたが、電子請求書に関しては5分程度に短縮されています。出先施設が担当する請求書に差し戻しが発生した場合でも、本庁まで出向いて回収する手間はなくなりました。
また、事業者からも「郵送費などのコスト負担が増している中で、とても助かる取り組みであり、ぜひ他団体にも広めてほしい」という声が届いています。
係長:
電子請求書に移行した一例が、市内複数カ所にある給食センターへ食材を納入する事業者です。日々大量に納品する大根20本、ニンジン30本、豚肉40kgといった明細を添付した請求書は、各給食センター別に手書きやWordで作成し、毎月大変な量になります。「郵送代が減った」との声をいただいていますし、差戻しの際はセンターまで持参していたところ、画面上で修正するだけになった点も利便性を感じていただいているようで、お礼の電話をいただきました。電子請求書が導入された以降は、明細の転記から請求書の作成、送付、当市側での受領、確認・審査、支出伝票の作成、支払まで、システム上で一元的かつ迅速に処理できるようになり、事業者と当市職員の双方の業務効率化とコスト削減に寄与できたと感じています。
今後に向けた展望をお聞かせください。
課長補佐:
これまで進めてきた大規模なシステム更新もひと通り完了し、次はフロントからバックオフィスまでの一貫した業務最適化を進めていく計画です。そうした中で、『BtoBプラットフォーム 請求書』がさらに重要な役割を担っていくのは言うまでもありません。今回の取り組みは会計課が主体的に取り組みましたが、根幹に現場の高い課題認識があったからこそ的確な解決策の立案、実行につながったと自負しています。今後に向けても各部署と会計課、DX担当部門が相互に連携しながら、デジタル化による新たな価値創造を目指したいと考えています。
係長:
そのためにも電子請求書の利用率向上が不可欠です。例えば各事業者がすでに導入しているシステムからの利用を検討していただくなど、インフォマート社のサポートも受けながら、より柔軟かつ多様な連携の方法を提案・案内することで、『BtoBプラットフォーム』を利用する事業者のさらなる拡大に努めていきます。
※掲載内容は取材当時のものです。