戦後間もない大阪で、街のパン屋さんとして創業した株式会社ダイヤ様。70年を超え、今なお愛される「クックハウス」を20店舗超展開するほか、百貨店へ出店したサンドイッチ専門店「ダイヤ製パン」も好評を博しています。労働環境が過酷と思われがちなベーカリー業界も、業務を簡素化し負担を軽減する要素はあるという多田俊介社長。老舗パン屋が取り組んだ、IT化による業務改革について伺いました。
ココがPOINT!
-
1
仕入れ分析で食材を整理し、年間120万円のコストを削減
-
2
FAX発注用紙が不要になり、送信ミスも解消
-
3
曜日ごとに決まった仕入れ品を発注予約して、手間を削減
老舗ベーカリー「クックハウス」は駅ナカパン屋の先駆け
商業施設や駅ナカ、百貨店に積極的に出店されていますね。

代表取締役社長 多田俊介氏(以下、多田社長):
サンドイッチベーカリー「ダイヤ製パン」は創業時の社名ですが、百貨店への出店は、当社の歴史の中では最近の話です。駅ナカも百貨店も、我々が売り込んだというより先方からお声がけをいただいて出店しています。

当社の創業は1946年と戦後間もない頃で、進駐軍から支給された小麦を使ってパンを作り始め、創業初期は、学校給食用のパンを作っていました。大阪の繁華街・梅田の「クックハウス ホワイティうめだ店」は、1963年の地下街オープン当初からある貴重な店舗として取材を受けることもあります。
駅ナカへの進出は2004年、近鉄上本町駅構内に出店のお誘いをいただいたのがきっかけです。当時は駅ナカとベーカリー業態の組み合わせがいいと認知されてなかったのですが、当社が出店したところ売上も好調に伸び、その後も駅ナカ出店のお声がけが続くようになりました。
そして2014年に、高島屋大阪店からサンドイッチ専門店を出したいとのお話を受け、パン屋ならではの作り立てをお出しする店舗として出店したのが「ダイヤ製パン」です。評判をいただき、他の百貨店にも展開しています。
多くの引き合いをいただく御社の商品の特徴は何でしょうか?
多田社長:
クリームパンのクリームやサンドイッチにはさむ卵、ローストビーフといった具材も、自社で作っています。業務用の材料を使うと味の差別化が難しくなりますので。サンドイッチも30種類以上ありますが、創業以来積み重ねてきた歴史とレシピで、ひとつひとつ手作りにこだわり、美味しさを追求しています。
原材料の発注管理はどのように行っていますか?
多田社長:
『BtoBプラットフォーム 受発注』を導入しシステム化しています。小麦やバターなど製パンの材料だけでなく、店舗で使うコーヒー豆や包装資材なども含めて90社ほど仕入れ先があり、その9割とシステムを使って取引しています。
受発注システムを導入された経緯を教えてください。
多田社長:
私が中途入社で着任した2013年ごろまでは、昔ながらの電話やFAXでの発注でした。すると、どの季節になんの材料をどこから仕入れ、どれだけ使っていくらの価格で売っているのか、知りたいと思っても把握できなかったのです。伝票の単価が間違っていても、すぐにはわからないし、自社の現場の状況を知るすべがなくて困ってしまったのがきっかけです。現場の発注作業も手間をかけてやっているようだし、何か解決策があるのではと考えました。仕入情報の履歴を積み重ねていくには、システムを使ったほうが絶対楽になるし、間違いもありません。
そこで自社システムを構築しようと見積もってみたところ、500万円ほどかかると試算されたため、パッケージ化されたサービスがないかと探して『BtoBプラットフォーム 受発注』を見つけたんです。仕入れ先にも使っていただけるように利用企業数の多いサービスが良いと思っていたのですが、当時すでに8割くらいの仕入れ先が導入済だったとわかりました。初期投資もさほどかからないこともあり導入しようと決めました。
現場は、使い慣れた電話やFAXからの移行に混乱はありませんでしたか?

製造部 製造課 工場長:
ずっとアナログでしたので、最初のうちは混乱した記憶はあります。でも、慣れるとムダな紙もいらないし、送信ミスや言った・言わないといったトラブルもないので、システム化して良かったと思います。

店舗でも工場でもアイテム数が多く、仕入れ先や仕入れ品ごとに発注担当者を分けています。発注用紙で管理するとぐちゃぐちゃになってしまうので、システムで担当者ごとに発注リストを作りました。そこに数字を入れて発注していくだけなので、異動で担当者が変わっても簡単に引き継げますし、もし急に休む人が出ても誰かが補えます。
また、曜日ごとに発注が決まっている仕入れ品は、「週間発注」機能でまとめて発注予約できます。スマホからいつでも発注できるので、ちょっと手が空いた時などに簡単に済ませてしまえるのも助かります。

総務部 総務課 課長:
店舗が工場へのパンの発注にFAXを使わなくなったことで、紙の伝票管理や集計の手間がなくなりました。以前は1店で1日に4枚くらいFAXで発注用紙を送信していました。18店舗あるので毎日72枚ほどの紙を使っていたことになります。
仕入れデータを見える化し、年間120万円コスト削減
現場の仕入状況の把握は、できるようになりましたか?

多田社長:
結果として、すごく効果がありました。システム導入の一番のメリットはデータ化によって仕入状況がクリアになり、分析できるようになったことです。商品と原材料との対照表を作成して、使っていない食材を把握して倉庫のスペースを空けることができました。また、牛乳やバターなど同じ種類の材料を単価の安い仕入れ先に統一したり、仕入量を算出して価格交渉もしたりして、年間120万円ほどコスト削減ができました。システム利用料や導入費をまかなってあまりあるほどの効果といえます。
今後の展望をお聞かせください。
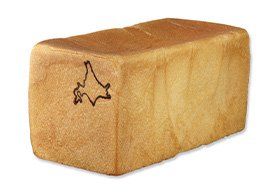
多田社長:
近年、北海道の小麦農家さんと一緒に“とかち小麦ヌーヴォー”という取り組みをしています。通常、収穫して製粉し小麦粉にするまでは数ヶ月かかります。それを収穫の時期にあわせ、とれたての新鮮な小麦を製粉して販売することで、育てる人、作る人、食べる人をつなげる試みです。旬を意識することで消費者の方にも産地や小麦の生育を身近に感じていただきたいんです。こうした取り組みは我々くらいの中小のベーカリーだからこそ率先してできると思っています。
食の安心・安全や美味しいパンを届ける、あるいは企業として利益を出すというのは当然のことであって、それが前提にあった上で、やはりパンに関わる人たちが幸せになることが一番だと思っています。生産者の方に、パンのために小麦を育てて良かったと思っていただきたいですし、もちろん食べる人には美味しいと思っていただきたい。作る人にも食べる人にも、パンを通じて喜びを感じていただければベーカリーとしてこんなに嬉しいことはありません。
※掲載内容は取材当時のものです。
