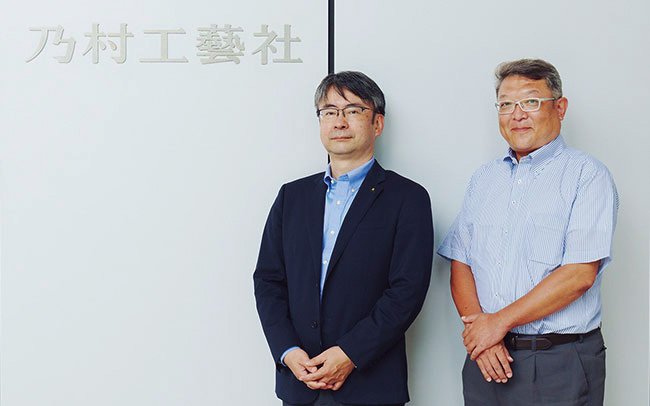博物館・美術館から百貨店、小売店、さまざまな空間の企画・デザインをはじめ、設計・制作・施工まで行う、ディスプレイ業界最大手の乃村工藝社様。社内で扱う膨大な契約件数に関わる煩雑な関連業務を、いかにして効率化できたのでしょうか。業務管理部の担当者に話を伺いました。
ココがPOINT !
-
1
イニシャルもランニングも、納得のコスト感
-
2
自社基幹システムと業務フローとの高い親和性
-
3
月間2千件以上の契約書を電子化
発注担当者がもちこむ膨大な契約
創業130年の老舗。その業務内容は多岐にわたっていますね。

業務管理部 田中良志部長(以下、田中部長):
弊社では、「人間尊重に立脚し、新しい価値の創造によって豊かな人間環境づくりに貢献する」ことを経営理念とし、「繁栄のお手伝いをするパートナー」であることをブランドステートメントとしています。
その立場から、空間創造・空間活性化を中心事業として据え、人が集まる場所や空間を活用するために、コンサルティングから入り、企画を提案し、設計や施工、その後の運営、メンテナンスまで含めた多種多様なサービスで対応しています。
実績としては、グループ全体での案件数は年間12,000件ほど。コロナで落ち込んではいますが1,000億円規模の売上高を維持しています。
業務管理部ではどんな業務を担当されていますか。
田中部長:
グループ会社を除く乃村本体では、年に8,000件から9,000件の案件を取り扱います。上場企業ですので、会計処理が適切に行われること、コンプライアンスに違反しないことなどが重要です。業務管理部では、こうしたことを中心に社内の業務ルールを決めたり、そのルールに則って仕事が進んでいるかを適切に管理したり、場合によっては、業務改善のための様々な施策に取り組んでいます。
契約書業務もその一環ということですね。
田中部長:
業務管理部が契約業務そのものを直接的に行うことはありません。当部署の主な役割は、協力会社への発注業務に関して、コンプライアンスに則ったルールや仕組みを作ることで、効率的にかつ法律に触れないよう統制が効いた契約行為が行われる状態を維持するところにあります。
そもそも当社では、デザイン系から施工管理のできる人材など専門性の高い社員を多く抱えていて、制作担当の部署はもちろん、デザイナーも外注デザイナーに発注する際などに注文書(契約書)を発行します。つまり、業務に携わるほぼ全ての社員が発注権を持っており、非常に多くの契約業務が日常的に行われていることになるわけです。
受け渡し、郵送、確認、入力…付随する業務は月240時間
具体的な契約書業務のフローを教えてもらえますか。
田中部長:
注文書・請書(契約書)は、数千社におよぶ協力会社との間で、業務が発生する都度個別に締結します。メインの案件はもちろん、副次的・波及的に発生する個別案件についても契約書を交わしますので、その数は膨大な量になります。

業務管理部管理課 佐藤道雄課長(以下、佐藤(道)課長):
紙面での運用をしていたころは、担当者が注文書(契約書)を作成するところから始まり、上長の承認を得、押印責任者が捺印し、担当者はそれを封入・封緘して相手先に郵送したり、ときには直接取りに来てもらうこともありました。
先方で注文書(契約書)の内容を確認したあと、見積書などとともに請書を返送してもらいますが、返送がなければ督促しなくてはなりません。文書に不備があれば、このやりとりを繰り返します。最終的に締結済契約書としての請書を受領し、その原本をファイルするところまでが一連の流れでした。
請書は、おおむねA4の紙が3~4枚。それが月間数千件にのぼります。今回あらためて数字を洗い直してみたら、月に11冊の幅広ファイルが増えていました。保管するだけで多くの時間と場所が必要だったのです。
田中部長:
この請書の整理業務に何時間を費やしたかという工数を付けていますが、その工数ベースからいけば月に210時間、付随する電話応対業務を含めればじつに240時間もの作業時間がかかっていたのです。
2018年以降は電子化に踏み切ったとのことですが。
田中部長:
協力会社との契約業務について、一部だけでも作業の軽減を図るべく某社のファイル送信サービスを利用して、注文書、請書、納品請求書の三つの書類を一つのPDFにして電子的に送ることにしました。先方で請書を印刷して、印紙を貼り、割り印をして返送していただく、という形での運用をはじめたのです。
法務部 佐藤正己部長(以下、佐藤(正)部長):
当時すでに電子契約サービスはいくつかあったものの、いずれも機能が限定的で、弊社業務にはマッチしませんでした。そもそも建設業は契約については非常に厳しく制限があって、双方が合意したことが電子的に担保され、改ざんされないことなど、細部にいたるまで要件が規定されています。それらをクリアし、かつ当社の業務フローに馴染むサービスがなかったのです。
その時点で最善の策がPDFで注文書を送るということだったんですね。
田中部長:
2020年になり、やはりコロナが大きく影響しました。注文書はPDFで送れても、請書は郵便で届きますので、それを開封して管理する必要があります。その先の基幹システムへの請書受領履歴の入力作業も解消すべき課題となってきました。また、協力会社側から見ると、請書を出していただくために出社しないといけないと言うことになります。
このように、協力会社側も含め、出社しなければできない業務がかなりあることが露呈しました。例えばこの先、関東エリアで大きな地震や災害があった場合のことを考えると、BCP(事業継続計画)の観点からも、もう少し突っ込んで出社対応が必要な業務の軽減を考えなければならない、という需要が出てきました。
電子契約書サービスの導入に期待したこと
改善点のあった契約書業務ですが、電子化によって何を期待しましたか。
田中部長:
やはり、建設業法における契約の要件を満たすこと。あとは、どこまで自動化が可能か、当社の業務フローにどこまでマッチするかといった点ですね。
佐藤(正)部長:
電子帳簿保存法(電帳法)の改正も大きなポイントでした。電子化した場合、締結された契約はどのように管理されるのか、どう運用すべきなのか。まずは改正電帳法の解釈から検討しました。
契約書システムの導入までの経緯を教えてください。
佐藤(正)部長:
導入した契約書のシステムを、社内の基幹システムに繋げて社内統制を取れるようにしたいと考えていました。
田中部長:
例えば担当者レベルの一存でクリックひとつ押せば契約完了、となってしまうと統制が効かなくなります。特に顧客との契約においてはそのリスクが高い。そのため当面は、協力会社との注文書・請書のやりとりに限定して使っていくというスタンスで、導入の1年ほど前から電子契約サービスを探しはじめました。
自社の業務フローにも合致し、基幹システムとの連携や技術的親和性もクリアし、電帳法への対応も可能というサービスは他にもありましたが、最終的にはランニングコストが魅力だったこともありインフォマートの『BtoBプラットフォーム 契約書』の導入を決めました。
導入に当たって協力会社様への案内はどのように。
佐藤(道)課長:
協力会社のうち、過去3年ぐらいの取引実績をもとに5,000社ほどピックアップして、まずは一斉にご案内を送付しました。
田中部長:
協力会社側での『BtoB プラットフォーム 契約書』導入に対する抵抗感を少しでも低減するため、メリットとして「印紙がいらなくなりますよ」とか「ボタンひとつで契約が完了します」とか、あるいは「契約の履歴がすべてクラウド上に残ります」、「紙でのやりとりから解放されます」などという点を訴求していきました。
佐藤(正)部長:
案内文を作る上で一番大切にしたのは、協力会社に寄り添うことでした。その点をブラさないよう、協力会社の目線からのメリットは何なのかがきちんと伝わるように工夫しました。前提として「乃村工藝社の施策として電子化します」ということではなくて、取引先の皆さんの業務低減にも貢献できます」というトーンで案内しました。
佐藤(道)課長:
業務フローの変更をお願いするわけですから、ハードルが高いかなと思っていました。ところが1回目の案内でサービスに乗ってくれる協力会社が多いことに驚かされました。電子化が重要だという認識が社会的にも定着しているのだと、強く感じましたね。
稼働開始から6ヶ月ほどで、すでに月間2,600件もの利用があります。
田中部長:
現在、経常的に取引の厚い協力会社が約500社なので、妥当な数字だと思っています。スポットで入るお客様の紹介会社などは継続的な電子契約利用はなかなか難しいですが、当社ではその仕事に見合った材料・技術を提供している会社など、常に新しい会社様とのお取引が発生し続ける傾向がありますので、その辺りを勘案すると今後さらに伸びていくと考えています。
作業時間の半減と、さらなる効果波及に期待
結果として電子化率はどのくらい上がりましたか。
佐藤(道)課長:
やはり、建設業法における契約の要件を満たすこと。あとは、どこまで自動化が可能か、当社の業務フローにどこまでマッチするかといった点ですね。
田中部長:
お声がけした5,000社では、約半数が導入してくれていて、実際の発注件数と照らし合わせれば、発注件数の6~7割ほどが『BtoB プラットフォーム 契約書』で対応してくれています。最初は500社がいいところだと思っていましたから、滑り出しは上々です。
どのようなメリットを感じていますか。
田中部長:
発注担当者にとって業務自体は変わっていません。単に注文請書をやりとりする方法が変わりましたという程度。むしろバックオフィス側のメリットが大きかったです。請書の受領業務については半自動化され、文書管理システムとの自動連携も可能になり、バックオフィス側の工数ベースでいえば1案件にかける時間は50%以上も削減されました。
佐藤(道)課長:
契約書データが自動的に文書管理システムと連携することが可能になりました。その点でも、バックオフィスにおけるメリットは大きいんです。
田中部長:
課題としては、問い合わせが導入前の1.5倍になりました。でもその多くが使い方に関するものなので、時間の経過とともに減っていくと考えています。
導入から半年あまりたちますが、いまようやく導入効果が見え出した感じです。取引先だけでなく、弊社のBCP対策のきっかけにもなり、今後は数字に表れにくい副次的な波及効果が楽しみです。
※掲載内容は取材当時のものです。