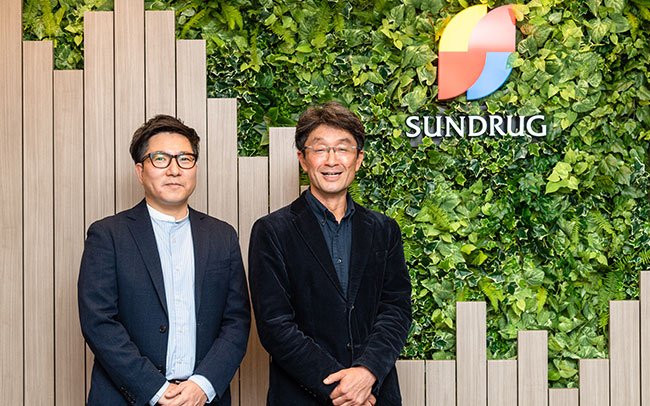全国に約1,300店舗(2022年3月期連結)のドラッグストアを展開するサンドラッグ様では、日々、さまざまな契約が交わされます。すべての契約を紙ベースで行なっていた際には、スピード感や業務負荷に課題がありました。本社に法務部が設立され、電子契約書も導入。以降、基本的にすべての契約を電子に切り替えているそうです。電子契約書の導入は、従業員に契約の大切さを意識付けたそうですが、具体的な導入メリットについて、担当者のお二人に伺いました。
※2023年1月現在
ココがPOINT!
-
1
導入コストとランニングコストの費用感
-
2
契約の効力を担保する「当事者型」への安心感
-
3
従業員に浸透した「契約」の重要性に対する意識
煩雑な契約処理業務とスピード感、管理の難しさに課題
それぞれご所属の部署での担当業務を教えていただけますか?

五味 肇 様
執行役員 社長室長 五味 肇 様(以下、五味様):
社長室では業務範囲ごとにいくつかのセクションに分かれています。1つがデジタルマーケティング関連です。オウンドメディアや SNS などの広告等の施策を行います。次に自動発注関連業務があります。販促内容から POSの売上予測を立てて、自動で発注する仕組みの構築です。さらに、棚卸減耗損などのロス対策も担当します。数え間違いや打ち間違い、万引きなどで発生するロスは、小売業で約1%発生すると言われています。売上高が 6,000億円を超える中での1%ですから、対策は必須です。
そのほか、不良在庫をいかに無くすかといったことや、最適な人的配置で生産性を高めるワークスケジュールの組み立て、またフランチャイズの管理運営業務も担当するなど、幅広い業務を行なっています。

秋山 忠幸 様
法務部 部門長 秋山 忠幸 様(以下、秋山様):
私は大きく分けて4つの業務を担当しています。1つは契約書の雛形作成、契約書のチェック、電子契約の管理といった契約書関連業務、2つ目はコンプライアンスの社内周知等の教育関連業務、3つ目は法改正への対応、4つ目として社内で起こりうるリスクの洗い出しと対策、また対策のための仕組みの検討といったことを行なっています。
契約書のなかで、処理件数の多いものには、どのような契約がありますか?
秋山様:
一番多いのは NDA(秘密保持契約)です。次に業務委託契約があり、同じ程度に取引基本契約でしょうか。そのほか、店舗開発に関わる物件賃貸借契約もあります。従来は、すべて紙の契約書で取り交わしていました。
紙による契約書業務では、どのような課題があったでしょうか。
秋山様:
紙ベースで契約書の処理を行なっていた頃は、現在のように法務部で契約関連を一元管理しておらず、各部署で契約書をファイリングして管理していました。
五味様:
各部署での管理では、担当者が変更になった際の引き継ぎがされなかったり、契約書がどこに保管されているかわからず、探すのに時間がかかるといったことがどうしても起きてしまいます。法務部は2021年に立ち上げられましたが、それ以前にも、契約関連の一元管理を社内で検討したことはありました。ただ、管理方法について良い提案もなく、課題は棚上げにされていました。
導入の決め手は、コストバランスと安心感
契約を締結するまでの業務上の課題はありましたか?
秋山様:
日常的な契約書業務でも、課題はありました。全国に事業所がありますが、例えば九州で契約締結の話があれば、まず現地の事業所で契約書の原本を作成し、データで東京の本社へ送ってもらいます。本社で内容を確認し、押印した後、製本して九州の事業所へ送り返し、先方と取り交わすといった流れで行なっていました。
印刷から製本、発送の手間もかかりますし、郵便代や収入印紙代などの諸経費もかかります。本社でハンコを押す際にも、管理本部長が不在のためハンコが押されるまでに時間がかかるといったこともありました。
契約書を電子化するに至る経緯について、教えてください。
五味様:
DX 推進の一環と、やはり紙と事務経費の削減が大きな理由です。先ほども言いましたが、契約書を一元管理する方法を探していたのですが、そうしたなか東京のビッグサイトで開催されていた「財務エキスポ」でインフォマートの『BtoB プラットフォーム 契約書』を知りました。こんな便利なサービスがあるのであれば、契約書の電子化に向けて導入を検討しようということになりました。
ほかにも契約書の電子化サービスはありますが、『BtoB プラットフォーム 契約書』を選んでいただいたのは、なぜでしょうか?
五味様:
やはり営業の方の熱意が一番でしょうね(笑)。もちろん、それも大きな理由ですが、私が導入を決めた理由は 2つあります。もう1つはコスト面です。これは重要です。サービスを導入しても、費用対効果でメリットがなければ意味がありません。もう1つは信頼性の面です。電子契約には、立会人型と当事者型、2つの方法があります。弁護士も交えて法律を紐解いていくと、契約当事者の双方で署名・認証する当事者型がよりいいのではないかと思いました。『BtoB プラットフォーム 契約書』は、当事者型ですので、そこも理由の一つです。
また、『BtoB プラットフォーム』シリーズでは、請求書サービスの業界シェアが高く、電子契約を進めるにあたり、インフォマートさんであればノウハウも豊富で、電子化にスムーズに移行できるのではないかと思いました。
従業員が契約の重要性を意識するようになる
電子契約を導入されて、業務にはどのような変化があったでしょうか。
秋山様:
法律上、紙の契約書が必要なものと、先方の都合で紙の場合以外は、すべての契約で電子化することを社内で推奨しています。結果的に、すべての契約書を法務部で一元管理できるようになりました。
業務フローの迅速化も顕著です。急ぎ契約を結びたいという場合、最短でその日のうちに締結まで完了します。以前は、ハンコを押印するまでに2、3日かかることもあり、それから発送ですから、電子化で締結までかなり早くなりました。
各部署の担当者の方は、業務に変化はあったのでしょうか。
秋山様:
社内での契約業務の流れ自体に大きな変化はありません。紙ベースのときから、社内のワークフローシステムを通して、承認して、押印という流れでした。電子化では、そのフローの延長線に法務部が入って、『BtoB プラットフォーム 契約書』に取り込む流れにしています。ですので、契約を申請する各部署の担当者はこれまでと大きく変わりません。
五味様:
事務レベルの時間短縮はもちろんですが、ハンコを押す管理本部長の業務負担も課題でしたから、それが削減できたことは大きな効果です。
そのほか電子化によるメリットを感じることはありますか。
五味様:
紙の削減と業務の迅速化が電子化の主眼で、実際に達成されていますが、想定外で効果を実感していることがあります。それは各部署の担当者レベルで、契約に対する意識が高まったことです。
契約といっても概念が曖昧で、それぞれの契約にどんな意味があるのか、強く意識することもありませんでした。それが電子化と合わせて法務部が契約についての社内教育を行ったことによる相乗効果で、契約についての意識づけが習慣化されたように思います。
契約を意識することで、何かトラブルがあった際、契約書を確認したり、内容をアップデートするようになりますし、どんなときに契約を結ぶのかがクリアになってきました。
例えば NDA についても、あらゆることが知財という意識も醸成されています。どこにリスクがあるのか、法改正によっても状況は変わってきますので、基本的には NDA は結ぶというように社内文化も変わってきました。これは企業としては、いい変化だと思います。
今後の展望をお聞かせください。
秋山様:
「リマインドメール機能」を使いこなしたいと思います。例えば、社内教育で利用している e ラーニングツールの契約があって、新しいものに切り替えようとしたら、すでに自動更新されていたということがあります。リマインドメール機能で、契約期間の期日を前もって知らせてくれるのは、とても便利ですから、上手に使っていきたいと思います。
五味様:
かつては、商談ベースの口約束で契約が済んでいた時代もありましたが、今はメーカーさんをはじめとして、しっかりと記録する時代になり、契約書や覚書もどんどん増えています。世の中的にも、契約に対する認識が広がってくると思います。今回、電子契約の導入によって、社内での契約書の重要性が認識されてきました。これからもそうした認識を深めていきたいと思います。

※掲載内容は取材当時のものです。