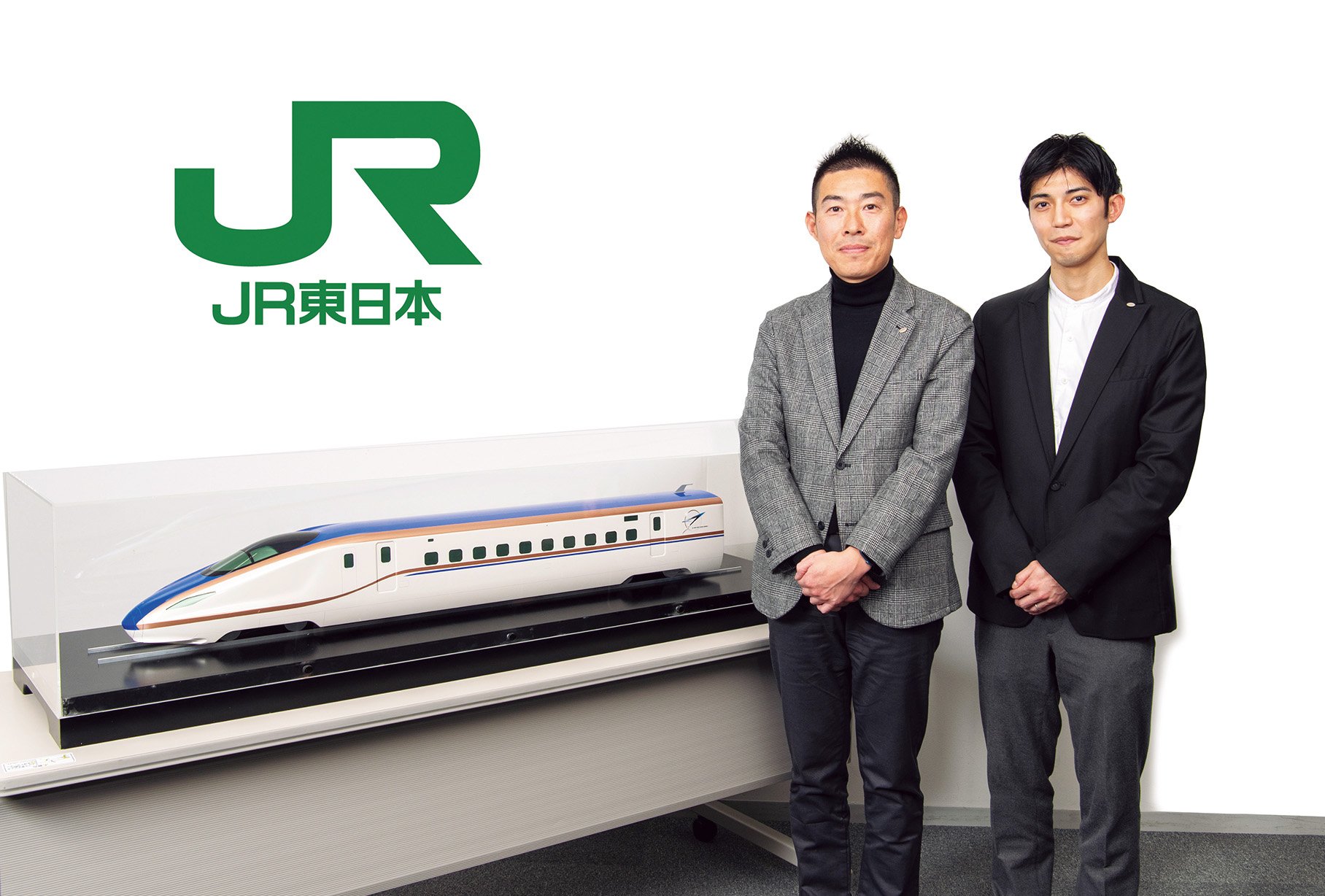日本最大の鉄道事業を営み、東日本エリアに地域や人をつなぐネットワークを広げている東日本旅客鉄道株式会社様。働き方の変化や法制度に対応すべく、グループ外の取引で依然として残っていた紙による請求書業務を発行・受取どちらも電子化。導入に際し実施した社内説明会は、業務デジタル化を意識づける役割もありました。変容する社会に対応した、新しい働き方と価値創造の実現を目指す取り組みとは。
ココがPOINT!
-
1
請求書発行業務にかかる月50時間がほぼゼロに
-
2
請求書の受け取り漏れや入力ミスのリスクが低減
-
3
業務の幅を広げる柔軟な働き方が可能に
10年先を見越した事業変革が、コロナ禍によって目の前の課題に
お二人が所属している株式会社JR東日本マネジメントサービスの事業概要を教えてください。

JR東日本マネジメントサービスJR事業部次期立案会計ワークフロー/インボイス対応プロジェクト マネージャー 中島 智樹氏(以下、中島氏):
JR東日本マネジメントサービス(以下、JEMS)は、東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)100%出資の子会社です。JR東日本を始め、JR東日本グループ各社の会計業務を受託し、正確な財務情報の開示に貢献するアカウンティング事業がメインです。
また、グループ各社で使用する共通の経理システムの開発、保守及び更新にも携わり、業務の省力化、効率化、高度化を目指しています。

JR東日本マネジメントサービスJR事業部次期立案会計ワークフロー/インボイス対応プロジェクト グループ長 瀧川 英彦氏(以下、瀧川氏):
JR東日本グループの企業価値向上への貢献と日本経済社会の発展への寄与がJEMSのミッションです。財務業務のエキスパート集団として、DX推進や、良質な財務サービスの提供と知的価値の創出を目指しています。
JR東日本は、1987年の会社発足以来、鉄道のインフラなどを起点としたサービス提供に取り組んできました。2018年に策定したグループ経営ビジョン「変革2027」において、次の10年で起点とするのは、すべての人の生活における「豊かさ」と位置づけ、新たな価値を創造し社会へ提供するべく、さまざまな取り組みを行っています。
たとえばどのような変革に取り組んでいますか?
瀧川氏:
JR東日本では、昨今のテレワークやEコマースに代表されるような、人の移動が伴わない生活スタイルへの転換をコロナ禍前に策定した「変革2027」ですでに想定していました。少子化や高齢化による人口減少や、働き方、豊かさに対する価値観の変化や多様化、さらにはデジタル化、グローバル化といった社会変容によって将来的に顕在化する課題と捉えていたのです。ただ、私たちが10年先に描いていた社会は、コロナ禍によって一気に目の前に来てしまいました。
今、JR東日本の社内では働き方や組織の見直しを図っています。できるだけお客さま、現地・現物に近いところでスピーディな判断により課題を解決し、仕事を通じて1人ひとりの能力を上げるという取り組みです。
私たちのミッションであった、2023年8月のJR東日本の立案会計ワークフローシステムの更新もそのひとつでした。これは稟議と会計を兼ね揃えたシステムで、約15年前からほぼ7年周期で更新を重ねています。今回システムの会計領域の開発を、私たちが所属するJEMSが受託しました。また、今回の更新にあわせて、インボイス制度や改正電子帳簿保存法、またテレワーク・ワーケーションなどの新しい働き方にも対応すべく、経理業務のデジタル化も積極的に進めました。電子請求書システム『BtoBプラットフォーム 請求書』の導入は、まさにその一環です。
発行にかかる作業時間や受取における入力ミスのリスクが激減
『BtoB プラットフォーム 請求書』導入前は、どのような課題がありましたか。
瀧川氏:
JR東日本グループ各社間の取引は、早い段階から独自システムで電子請求書のやりとりを実現しています。一方、グループ外のお取引先さまとは基本的に紙の郵送やPDFを添付したメールでやりとりしていました。
請求書発行に関しては、JR東日本では、鉄道高架下貸付の賃料や、駅構内テナントの水道光熱費、またJR他社をはじめ鉄道各社との運賃や料金の精算など、JR東日本グループ以外のお取引先さまに月約5,000通の請求書を発行しています。
紙の請求書は同じビル内にあるシステム室にて一括印刷され、それを毎日弊社スタッフが取りに行って、封入・封かん機にかけ、後納郵便で発送するのがルーチンでした。単純計算で毎日200通ほどの請求書を、2人の担当者が2時間、多いときには3時間近くかけて発送していました。
一方、請求書受取に関しても、土地の賃料、各種設備の建設費用、日々の会社運営で欠かせない費用など様々な取引において、JR東日本グループ以外のお取引先さまより月に約4,000通を受け取っています。紙で受領した請求書は、記載事項を立案会計ワークフローシステムなどへ入力した後、スキャニングしてPDF化したものを会計データと紐づけ、原本を保管していました。膨大な紙の請求書の保管場所の確保も大変でしたし、入力ミスや紙の請求書紛失による決算漏れのリスクも存在しました。
請求書の発行・受取、両方のデジタル化を検討されたのですね。
瀧川氏:
はい。同時にデジタル化するなら同一システムを利用するほうが合理的です。『BtoB プラットフォーム 請求書』は発行も受取も対応しており、何より国内シェアナンバーワン※の実績が決め手でした。
実は、JR東日本に先行してJR東日本グループの約40社では既に『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入していました。数年前に実施したグループ会社が共通利用している経理基幹システムのリプレイスの際に、請求書機能として組み込んでおり、その導入実績を参考にしてJR東日本でも採用しました。
受取に関しては、AI-OCRも検討しましたが、紙を読み込んでデータ化するのは読み込む手間があるほか、読取精度が100%でない限り、補完チェックが必須となります。お取引先さまが入力したデータがそのまま届くプラットフォーム型であればミスもなく安心です。
また、サービスを提供しているインフォマートはデジタルインボイス推進協議会(EIPA)の幹事法人ですし、将来的にデジタルインボイスの普及を見据えた選択でもありました。
※2023年6月現在 東京商工リサーチ調べ
導入にあたって、工夫したことはありますか?
中島氏:
私はJR東日本の社員教育を担当しました。システムは全社員が使える仕組みですが、会計業務に直接関わる経理部門のユーザーと、お取引先さまと直接やり取りする各部署のユーザーでは利用する機能の範囲が異なります。そこでレベルを3段階に分け、システムに最も濃密に関わるJR東日本の各エリアの経理担当を代表して13人を選抜し、エバンジェリスト(伝道者)として本社で2日間かけ研修を実施しました。実際の運用方法のデモンストレーションだけでなく、電子化の理念もしっかり伝え、デジタルシフトへの意識づけを行いました。次に、システムへの関わりが中堅どころのユーザーに対してはオンライン上でデモ操作を行い、システムの概要や新機能の紹介を行いました。この説明会は全7回実施し、延べ1,000人近くが参加しました。最後に、利用頻度の少ないユーザーに向けては、マニュアルの動画やPDFを作成して社内ポータルにアップし、必要に応じて、自習できる環境を整えています。
その甲斐もあってか、各ユーザーは電子請求書対応を新たな立案会計ワークフローシステムの新機能の一つと捉え、新システム対応の一環として電子請求書の発行や受取にシフトしてくれました。
導入の効果はいかがでしょうか。
中島氏:
発行に関しては、紙で送る必要がある請求書以外、ほぼ自動化となり、これまで毎日2人で2~3時間かけて行っていた封入などの手作業がほとんど不要になりました。万が一再発行が必要になっても、従来のようにデータを探して再出力する手間が不要で、画面上でスムーズに完了します。担当者からは時間に余裕が生まれ、これまで手が回らなかった、より生産性向上に寄与する業務にシフトできるようになったと聞いています。
一方、受取は現在デジタルデータの受領を推進している最中ですが、はじめて『BtoBプラットフォーム 請求書』に届いた電子請求書が、設計通りにFTP連携の自動ダウンロード機能で立案会計ワークフローシステムに届いたときは感動しました。「書式追加機能」を利用して、請求ごとに発番する識別番号を入力必須にして稟議に紐づけることで効率的な処理を実現しています。
『BtoBプラットフォーム 請求書』の導入により、JR東日本グループ外のお取引先さまと電子請求書をやりとりできる仕組みを構築することができ、JR東日本全体に電子請求書、デジタル化への意識付けができたと思っています。
働く場所や移動時間にとらわれない、新しい働き方の拡充にも
今後の展望をお聞かせください。
瀧川氏:
いわゆるバックオフィス部門だけでなく、駅社員や乗務員などが所属しお客さまに近いところで業務を行う現業機関にも『BtoB プラットフォーム 請求書』を拡げていきたいです。組織の再編や働き方の見直しで、例えば乗務員が列車本数の多い朝夕の時間帯だけ乗務して、他の時間はバックオフィスでデスクワークをするといった柔軟な働き方も始まっています。『BtoB プラットフォーム 請求書』は現業機関における業務の幅を拡げることの一助になり得るシステムだと考えています。
『BtoBプラットフォーム 請求書』の導入で、同業の方からも頻繁にお問い合わせいただいており、鉄道事業者の中でも請求書のデジタル化に注目が高まっていると実感します。請求書に限らず、電子化・デジタル化はお取引先さまのご協力なくしては進められません。築いてきたネットワークを生かし、デジタルの道を延伸していきたいです。
※掲載内容は取材当時のものです。