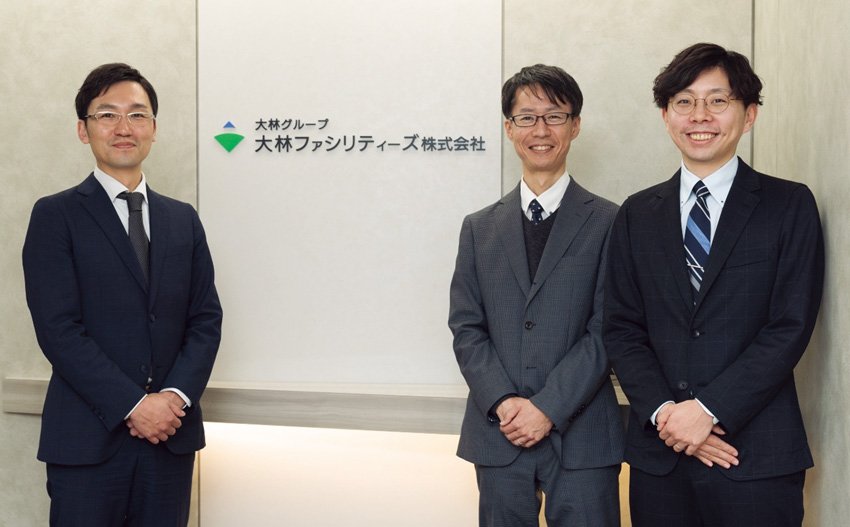ゼネコン大手の大林組のグループ企業として、ビル管理事業と建築事業を行う大林ファシリティーズ株式会社様。東京支店と大阪支店で、毎月合わせて6000枚にものぼる紙の請求書の処理には、人的・時間的・精神的なコストがかかっていました。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応を前に『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入。すでに大きな効果を実感されています。
ココがPOINT!
-
1
月6000枚もの請求書をデジタル化し、業務時間を半減
-
2
煩雑な承認フローも解消し、ハンコの押印はゼロに
-
3
業務の改善効果を実感し、さらなるデジタル化へ取り組み
毎月届く6000枚もの請求書の処理に追われていた
事業内容をお聞かせください。

事務課長:
創業は1963年で、建物の管理業務と建築業務、2つの事業を軸にビジネスサポート事業やオペレーションマネジメント事業などの事業を有しております。売り上げの6~7割は管理業が占めており、主にグループの親会社である大林組が施工した建物の管理をしています。また、近年はPFI(Private Finance Initiative=公共の施設を民間企業が管理・運営する手法)をはじめ、行政機関からの業務委託に向けた積極的な提案を行い、受注も増えているところです。建築業は建物のリニューアル工事をはじめ、省エネルギー化の提案や緑化工事などを担います。
ビル管理業、建築業における請求書をはじめとした帳票類のデジタル化の状況はいかがでしょうか。
事務課長:
歴史ある企業も多い業界ですから、紙の書類が多く、取引先でも紙が残っている企業は多くあります。特にビル管理は裾野が広く、例えば建物の清掃ひとつとっても、毎日の清掃から1~2カ月ごとのガラス清掃、共用部の床の定期清掃など、多種多様です。設備取引先企業も多くなります。建築でも同様に工事の種類分、取引先はかなり多くなります。管理ではさらに裾野が広く、それだけ取引先企業も多くなります。建築でも同様に工事の種類分、取引先はかなり多くなります。
紙の請求書業務は、どのように行なっていたのでしょうか。
ビル管理事務担当者(以下、ビル管理担当者):
当社は東京支店、大阪支店があり、支店に紐づく形で全国に13の営業所を設けています。請求書はそれぞれの支店や営業所で受け取っています。

請求書は取引先に当社のホームページからエクセルの指定の書式をダウンロードしていただき、印刷、押印、郵送してもらいます。受け取った請求書は物件の担当ごとに私たち事務課の担当者に振り分けられ、それぞれが処理を行った後、経理に提出します。営業所においては、処理後に請求書の原本を支店の経理まで郵送しています。

建築事務担当者(以下、建築担当者):
処理の流れは、ほぼ同じですが、建築では建築現場に事務所を設営する場合があり、現場担当者が現場事務所で受け取って処理するか、月に1度、大阪支店に来て処理をしなければならず、移動や郵送の作業が発生していました。現場担当者は忙しく、経理への提出期限ぎりぎりに処理することも多く、支店の事務方も業務が集中してしまうこともありました。
経理課長:
各事業部で処理した請求書が経理課に集められ、経理担当者が1枚ずつ目視でチェックします。金額に間違いがないか検算し、仕訳も間違っていないか確認します。
請求書の枚数は、ビル管理、建築合わせて毎月約3300枚にもなります。東京と合わせると合計で約6000枚。これだけの量が毎月届いているのです。大阪支店においては、経理担当が6名で1人あたり500~600枚を毎月処理していました。
請求書を経理へ送るまでの業務について教えてください。
ビル管理担当者:
まず案件を受注した段階で、販売管理システムにデータを入力します。請求書が届いたら、請求内容を確認して間違いがなければ営業担当と上長が押印します。事務は請求書の内容と受注時のデータが合っているかを確認して、販売管理システムで支払い確定の処理を行います。支払い確定処理は経理課でも確認できるので、経理課でも請求書が回ってきたら、入力されたデータと紙の請求書を突合するという流れです。
そうした一連の作業でご苦労された点は?
ビル管理担当者:
請求書には、担当者と上長のハンコの他に、物件ごとにその物件のゴム印と仕訳のゴム印を押します。さらに販売管理システムで処理をすると案件ごとに6ケタの整理番号が発行されるので、その番号を手書きで記入します。ハンコも整理番号も枚数が増えてくると、流れ作業になってしまい、間違ってしまうことがありました。ハンコを押さなければ経理に回せないので、急遽体調不良で休むときは翌日まとまった時間を作って作業をするか、当日中に処理が必要な場合は他の人に代わってもらうこともありました。
デジタル化で処理時間が半減し、精神的負担も軽減
請求書のデジタル化を進めるきっかけについて教えてください。
事務課長:
とにかく大変な請求書業務をデジタル化したいということで、プロジェクトチームを立ち上げました。業務の効率化はもちろんですが、インボイス制度、電子帳簿保存法といった法令対応を控え、このままの体制ではとても対応できないということもありました。
複数のサービスと比較検討した結果、『BtoBプラットフォーム 請求書』は、利用企業数の圧倒的な多さと将来性、それから取引先企業への金銭的な負担がない、という点に大きなメリットを感じました。ビル管理担当者と建築担当者の2人がプロジェクトチームを主導してくれたおかげで、大阪支店だけでなく東京支店へも波及し、結果的に全社で『BtoBプラットフォーム 請求書』を導入できました。
『BtoBプラットフォーム 請求書』導入による効果をどのように感じていますか?
ビル管理担当者:
経理に回すまでの作業がとても楽になりました。まず、紙ではなくなったので請求書の整理番号の記入や各物件、仕訳のゴム印を押す作業が一切なくなりました。仕訳は『BtoBプラットフォーム 請求書』上で予め設定しており、物件や経理課で確認が必要なもののみを空白に設定することで、すでに8割が埋まった状態にしています。請求書1枚あたりの処理時間は半減しました。
以前は束になった請求書を1枚1枚めくって処理していたのが、一括で申請・承認できますし、何より大量の紙がデスクに置かれるという精神的な負担が軽くなったと、ある部長は話していました。
建築担当者:
承認が必要な場合はメールで知らせてくれますので、現場へ出ている上長も出先にいながらクラウド上で確認・承認ができるようになりました。以前のように、上長などの承認者が帰ってくるまで、事務方の我々も待つという時間も解消されています。
経理課長:
請求データがすぐに届くので、締め作業がしやすくなりました。特に効果を感じているのは、進捗を経理課でも確認できることです。承認フローや督促が必要なものなど、紙の時代には見えなかったものが可視化され、経理からも事業部へ処理を促すことができます。
販売管理システムとの照合も、受取請求書のデータを一括ダウンロードして確認できます。支払いデータの作成も、以前は2種類ある販売管理システムから出力したデータを会計システムへ取り込んだり、販売管理システム外の支払いは経理課員が直接会計システムへ入力したりしていましたが、今は『BtoBプラットフォーム 請求書』から出力されるデータのみを会計システムへ取り込めばよくなったため、作業時間の短縮ができました。
それに大阪支店に3000枚以上届く請求書を、物件順に並べ替えてファイリングしていましたが、その作業が一切なくなりました。スペースも有効活用できますし、並び替え作業のために配置していた1名を別の業務に当てることができました。
データ連携により、すべてを一気通貫に処理する未来
御社でのデジタル化の進捗と今度の展望についてお聞かせください。

ビル管理担当者:
すべてを電子請求書で受け取れるのがベストではありますが、どうしても紙の請求書じゃないと対応できない取引先もおられます。そこでAI-OCRでデータ化してくれる『BP Storage for請求書』も合わせて導入することで、紙やPDFで届く請求書もデータ化し、『BtoBプラットフォーム 請求書』に取り込んでいます。これにより、すべての請求書をデジタルで一本化できました。
また、インボイス制度が始まる前にデジタル化できたので、制度にも無理なく対応できました。もし、紙のままだったらインボイスに対応していない請求書の差し戻しもすごい数だったでしょうし、取引先へ1件1件電話で再発行をお願いして、といった最悪の事態が避けられて本当によかったです。
事務課長:
今回のデジタル化をきっかけに東京支店とも協力して、請求書の業務フローを統一化することができたことで内部統制も強化されました。受取請求書と支払いデータが一元管理されたので、次は契約書のデジタル化を検討しています。最終的には契約書の金額が、そのまま請求書の金額になるとか、将来的には販売管理システムとのデータ連携も果たして、すべての取引が一気通貫で運営できるような未来に向けて取り組みたいと思っています。
※掲載内容は取材当時のものです。