兵庫県尼崎市にある総合病院、尼崎中央病院を中心に、14の医療介護事業施設を運営している社会医療法人中央会様。診療部門では電子カルテなどのデジタル化を進めてきた一方で、バックオフィス業務のデジタル化は遅れがちでした。膨大な明細項目の処理が必要な医療業界の請求書をクラウドサービスでデジタル化、データ活用による業務効率化を実現。DXと働き方改革を大きく推進しています。
ココがPOINT!
-
1
大きな負担だった保管業務を、ペーパーレス化で解消
-
2
請求明細のデータ化で、煩雑な集計業務を効率化
-
3
電子データによる確実な受け取りで、紛失リスクを低減
バックオフィスのデジタル化をはばむ、複雑で項目の多い請求書
地域に根差して多岐にわたる医療サービスを提供されていると伺っています。
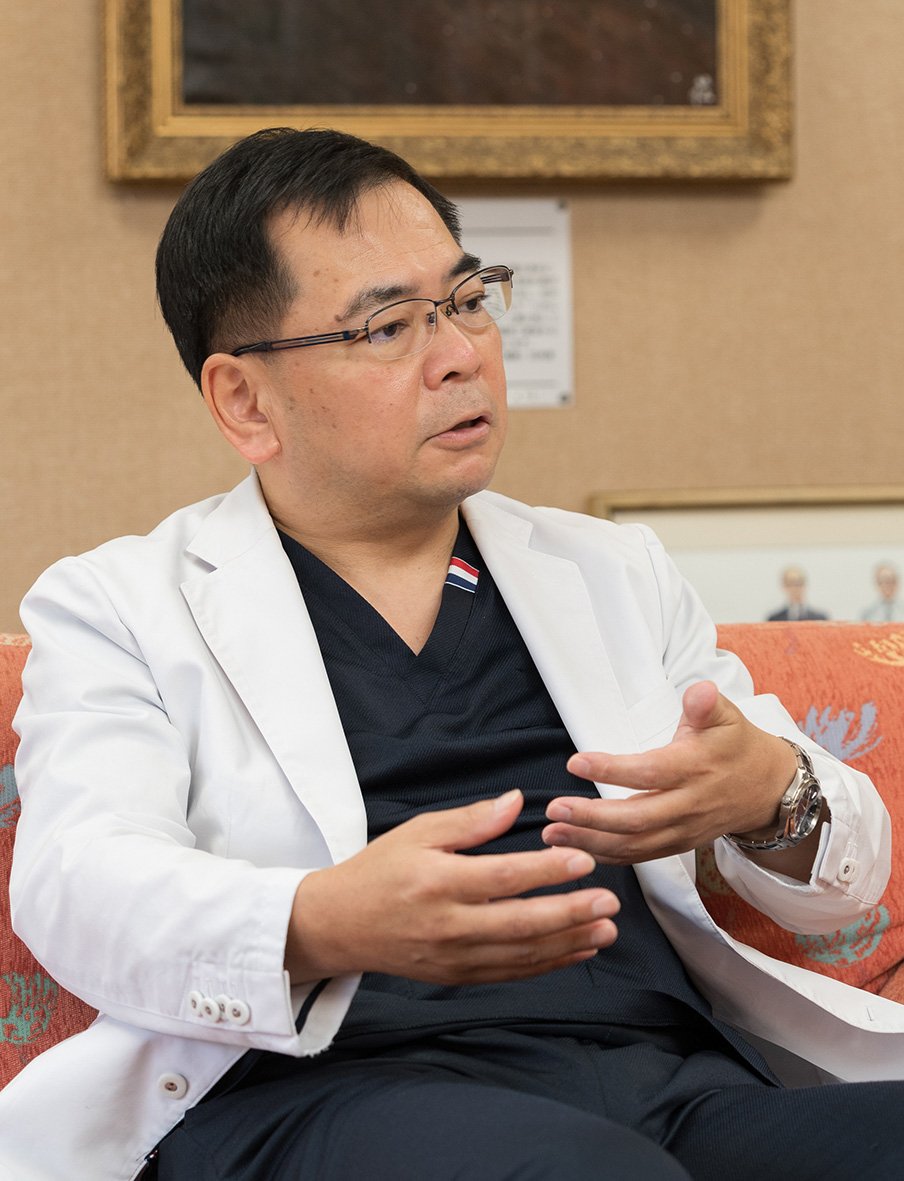
理事長医学博士 吉田純一氏(以下、吉田理事長):
社会医療法人中央会(以下、中央会)は、1951年設立の「潮江病院」が始まりです。当初は34床の小さな病院でしたが、現在は14の医療介護事業施設を運営しています。中心である尼崎中央病院は、急性期から介護まで、地域を支える市民のための病院として216床・29の診療科を有するケアミックス病院です。2024年11月には尼崎中央リハビリテーション病院(回復期リハビリテーション病棟93床)を開院、介護医療院トワイエ尼崎(144床)も開設し、地域医療の中核を担う存在として成長を続けているところです。
医療法人では、請求書の処理についてどのような課題を抱えていたのでしょうか?

藤本 貴行氏
人事労務統括課長 兼 経理課長 藤本貴行氏(以下、藤本経理課長):
中央会の経理課は3名のスタッフで、月に約100社から届く1,200枚ほどの請求書を処理しています。請求書は病院内の各部署や老健施設などの事業所で受け取り、社内便で経理課に届きます。請求書以外の紙の書類も多く、紛失のリスクがありました。
経理課では受け取った請求書をもとに会計システムへ入力しますが、請求書一枚に複数の事業所の明細が記載されている場合、まず、事業所ごとの選別が必要です。さらに、一つの取引業者でも購入品目が多岐にわたり、物品も非常に多いという医療業界特有の課題があります。様々な形式やサイズの膨大な明細をめくりながら、「これは医療消耗品、文具、消耗品…」と判断し、適切な勘定科目に仕訳するのです。一連の支払作業の完了後のファイリングも、ばらばらの請求書を紐で綴るので手間のかかる作業でした。加えて、改正電子帳簿保存法への対応も求められていました。
『BtoBプラットフォーム 請求書』導入の経緯について教えてください。
吉田理事長:
まず、当院のデジタル化の考え方についてですが、新しい製品の導入は、ある程度マニュアル化でき、業務改善、働き方改革につながることが重要ととらえています。
院内デジタル化の第一歩は20年ほど前、尼崎中央病院の電子カルテ導入がはじまりです。医療の高度化・複雑化に伴い、院内では様々な統計をとる業務が多く、データ収集や帳票作成で職員にかかる負担を軽減する必要があったのです。加えて、医療現場では説明書や同意書を含め、紙の書類が非常に多いため、データ処理をできるだけペーパーレスにしたいという思いがありました。
診療部門のデジタル化とペーパーレス化がある程度進んだので、次はバックオフィスのデジタル化に着手しました。2018年頃のことです。本当はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入したかったのですが、それどころではありませんでした。まだ手作業で紙をめくりながら、業務をしていたのです。これにはさすがに驚きました。
医療に限らず一般的に、中小企業では財務や勤怠業務が属人的になりがちで、1人か2人で担当していることも少なくありません。その人がいなくなったらどうするのでしょうか。担当者が変わっても多少学べば動かせるシステムが必要です。そこから人事、労務、給与、勤怠、財務、経理といったバックオフィス全体の電子化に取り組んできました。
電子請求書システムの存在を知ったのは、2021年に参加した医療法人向け経営セミナーです。ところがこれは便利そうだと思って導入を検討したところ、経理担当から「このシステムでは経理業務効率化につながらない」という反対の声が上がりました。
請求明細のデータ化で、事業所ごと・勘定科目ごとの集計が可能に
なぜ、その電子請求書システムでは効率化できないと思われたのでしょうか?
藤本経理課長:
我々が求めていたのは、請求明細も含めて電子データ(CSV)で受け取れるシステムです。当初紹介された電子請求書システムは、紙の請求書をスキャンしてOCRで電子データ化するものでした。このシステムでは請求書の鑑(かがみ)部分しかデータ化されず、請求明細はPDFとして保存されるだけです。
さきほど申し上げたような、複数の事業所の明細が記載され購入品目も多い複雑な請求書の処理は、請求明細までデータ化されていなければ会計仕訳ができません。結局、PDFを見ながら手入力するので手間は減りません。この課題は、どの医療機関も同様に抱えているはずです。
吉田理事長:
OCRでデータ化しても精度は完璧ではなく、人の手で確認し訂正しなければ使えません。また、高額な費用がかかるシステムばかりでした。ある企業からは「RPAとAIを使えば可能です。ただし、ランニングコストが年間1,000万円かかります」と提案されました。それなら入力担当の人員を2人雇用できるなぁと考え、保留していました。
『BtoB プラットフォーム 請求書』を選んだ決め手は何だったのでしょうか?
吉田理事長:
電子請求書システムを5社ほど比較検討しましたが、プラットフォームでデータをやりとりするDtoD(データ・トゥ・データ)のサービスは、『BtoBプラットフォーム 請求書』だけでした。
『BtoB プラットフォーム 請求書』を使えば、取引業者と請求明細データを共有できます。取引業者が作成した請求書がデータで届くので、転記ミスが発生せず、100%正確に処理できます。明細を含むすべての項目がデータとして受け取れるという点で、当院の希望を満たしてくれました。やりたいと思っていたことが、ほぼすべて実現できたと思っています。本当に良い製品にたどり着きました。
藤本経理課長:
導入の際の懸念点は、取引先がどこまでこのシステムを使ってくれるかでした。しかし開始してみると実際は、約7割という予想以上に多くの業者さんが対応可能だと言ってくれました。『BtoB プラットフォーム 請求書』をすでに利用しているという事業者も多く、スタンダードなシステムなのだと感じています。
医療法人のクラウドサービス利用は、セキュリティ面で難色を示す声もありませんか。
吉田理事長:
医療法人は電子カルテで患者の個人情報を扱っているため、セキュリティには敏感です。ただ、電子カルテはオンプレミス(自社でサーバーを保有・管理すること)での運用がほとんどです。請求書システム単体でセキュリティを確保できれば大丈夫だと判断しました。それに、近年はクラウド化の波は避けられないという認識が広がっています。ある程度知見があれば、クラウドでも適切にセキュリティを確保すれば問題ないと理解しているので、以前とは雰囲気が変わってきています。
『BtoB プラットフォーム 請求書』の運用状況と、効果を教えてください。
藤本経理課長:
現在、約66社と半数以上の取引業者が『BtoB プラットフォーム 請求書』を利用しています。毎月約100社からの請求書を受け取っているため、デジタル化率は66%ほどです。まだ紙での運用も一部残っているものの、かなりの請求書が電子化され、紙の請求書の取り扱いが大幅に減少しています。
これまで請求書はすべて、各部署・事業所あてに届いていました。現在は『BtoB プラットフォーム 請求書』で受け取る請求書は、経理課に集約してから、各施設へ承認をまわすフローです。ある程度の規模の事業所であれば専任の事務員がいますが、職員10人未満の小さな事業所では、所長が伝票処理まで行っている場合もあります。グループ全体で導入することで現場の業務負担を減らしながら、紛失リスクや入力業務の負担も軽減できました。
請求明細のデータを活用することで、施設ごと・勘定科目ごとの集計が可能になり、業務改善を実感しているところです。保管にかかる手間も減り、検索性も高まりました。
デジタル化をさらに推し進め、働き方改革にも積極的に取り組む
今後はどのように活用していきたいですか?
吉田理事長:
2024年10月から郵便料金が改定され、デジタル化を推進するタイミングだと感じています。現在は紙の請求書でも、電子請求書への移行が可能そうな取引業者に対しては、再度の利用促進を計画しています。また、法人内の施設間での物品請求システムのクラウド化も進行中です。
「DXと働き方改革」は、医療業界に限らず、現代社会のキーワードです。特にバックオフィス業務の改善においては如実です。もちろん医療業界でも取り組んではいるものの、診療部門に比べると大きく遅れています。今後も、バックオフィスのDXと働き方改革に、積極的に取り組んでいきたいと思います。
※掲載内容は取材当時のものです。
