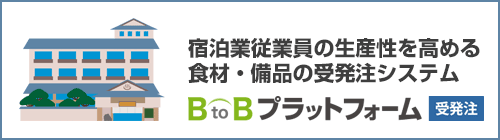ホテル業が抱える構造的な課題と原因
外国人観光客が日本へ訪れる数は、世界12位、アジア4位の多さとなっている(日本政府観光局「世界各国・地域への外国人訪問者数(2019年上位40位)」)。国内の人口縮小が進むなかで、特に地方は顕著だ。地方のホテルや飲食店にとって、いかに国内外から観光客を呼び込めるかが、アフターコロナの地域経済を回すカギになるといえる。しかしホテル・飲食業のコンサルティングをする濱野氏は、観光業の活性化を妨げかねない課題を3つあるという。
(1)ステイタス(評価、給与水準)が低い
(2)人材が集まりにくい
(3)業務の属人化により長時間労働が発生しやすい

代表取締役社長 濱野将豊氏
「若手の経営者からも多くの問題提起の声をいただいていますが、ホテルや飲食業界に従事されている方々の給与水準といったステイタスがまだまだ低いです。また、人材不足や生産性の低さから長時間労働が常態化している事業者さんも散見されます。さらには、特定の従業員さんの属人化したお仕事がイノベーションの阻害要因になっていたり、様々な事故、不正の温床になっていたりします。(濱野氏)」
これらは単独の問題ではなく、トライアングルのように作用し、多くの問題を派生させる要因となっている。原因としては主に2つあるという。
「第一に、紙による管理です。ゲストカード、食材のFAX発注書や納品伝票、請求書、レストランなどの注文伝票など、紙の管理と聞けば様々なものが思い当たるでしょう。これらを各部門から集めて整理、精算する作業は確実に毎日発生します。

営業部長 石垣舞子氏
しかし、膨大な作業量を限られた人員で管理するのは、ホテル管理システムや受発注システムなどのITツールを活用しない限り現実的に解決できません(濱野氏)」
「第二の原因は、経営者が業務改革をせず、現状維持に甘んじている点です。コンサルティングをする中で、ITツールやシステムなんて必要ないというお話しもよく出たりします。
変わることそのものへの苦手意識が根強い背景があり、最初から可能性を閉ざしてしまっているのです(石垣氏)」
ホテル・飲食業が取るべき道は、生産性を上げること
ホテル・飲食事業者がまず取り組むべきポイントは、生産性を上げ、従業員さんの給与、ステイタスを上げることだという濱野氏はいう。具体的に次の2点を挙げた。
(1)消費者との接点(接客場面)を増やして、おもてなしの価値を高める
(2)バックヤードの作業を減らす
「特に海外の観光客にとって、日本のおもてなしの文化に触れる体験は、日本旅行における価値そのものです。改めて日本のおもてなしの文化は世界に誇れるものという意識を持ち、接客やサービスの価値を高めることに注力すべきです」
そしてホテル事業者が接客場面を増やすためには、おのずとバックヤード作業を減らすことが必要になるという。
「人材不足やコロナ禍の現在、人員を増やすことは難しいでしょう。これは、バックヤードに人を置かない体制を作ることで、お客様への対応にスタッフを振り分けることが対策になります。これまで裏方の作業にかけていた時間と労力のムダをなくし、限りあるリソースを有効活用して、接客業の本質に立ち戻るべきなのです(濱野氏)」
対策はITツールの活用
ホテルや飲食業のバックヤード業務を削減するには、紙の伝票類や業務の電話連絡を削減する必要がある。そのためには、Wi-Fiなどの通信インフラやタブレット等のITツールを整備し、必要な情報を正確かつタイムリーに共有できる業務管理システムの活用が効果的だという。

「情報や業務の見える化が重要です。予約や売上情報はもちろん、仕入れ内容や清掃連絡など、煩雑かつ日々発生する業務に対し、どのように作業が行われているのかを可視化するのです。そうすることで、会計上の原価や部門、仕分けなどを統制し、さまざまな業務の標準化ができるようになります。従業員の時間や労力のムダを省き、生産性を高めるためにITツールの活用が重要となってくるのです(濱野氏)」
ホテル業や飲食業の中には従業員がITツールを使いこなせないという懸念もある。これに対して濱野氏は、心配するほどではないという。
「地方のホテル業や飲食業はご高齢の方が多いことは確かです。ガラパゴスケータイしか使ったことがない方もいるでしょう。実際の例として、ホテル業の気質にITは合わないというご不安があり、私が提案したITツールの導入に1年半かかった企業もあります。
しかし、コロナ禍の2021年は、この時期だからこそITツールを入れてみようというホテル業の方は多くいました。私が実際に操作画面をお見せしながら説明すると従業員の方もご理解いただき、慣れればいいんですねというお声を必ずいただきます(濱野氏)」
「たとえば、食材の仕入れを任されているスタッフが、日々必要な数量を感覚的に把握していることは調理場などで多いケースです。ここにITツールを導入すると、価格統制はもちろんのこと、アナログで行うには複雑なメニューごとの原価管理なども正確かつスピーディーに計算し、ボタンの操作さえ覚えてしまえば高齢の従業員でも容易に扱うことが可能なツールもあります。
人の入れ替わりの多いホテル業界においては、仕事内容の引き継ぎや伝達を滞りなく行うことが生産性の質を高めるポイントでもあります。発注作業を通して、どんな物をどのぐらい仕入れているかという料理長の視点を学べることは、部下にとって勉強になると同時に、仕事の流れや工程を料理長から継承することでもあるのです。(石垣氏)」
また、清掃スタッフが電話で「○号室の清掃に入っていいですか」とフロントへ連絡する光景は、今でもよく目にします。Wi-Fiはお客様のためだけと思われがちですが、たとえば清掃管理システムやオーダーシステムなど、社員の動線にWi-Fiがあることで、すべてのスタッフが必要な情報をタイムリーに共有、取得可能となり、生産性を高めることができます。通信さえ整ってしまえば、様々な管理ツールはあとからから付加することが可能です。
国や地方自治体には生産性を上げるためのIT関連の助成金制度もあります。いまだにアナログが多い旅館・ホテル業において、働き方を改革し、生産性を向上させるものに的確な投資を行うことは、もはや必須項目といえるでしょう(濱野氏)」
日本の観光産業のあるべき姿
消費者が「この場所にもう1度訪れたい」と思えるよう交流人口を増やし、長期に渡って支持を得るための仕組み作りは、アフターコロナにおけるインバウンド対策にも繋がっていく。いまのホテルや旅館・飲食事業者には、互いに切磋琢磨、競争することと観光資源の共有、いかに仕組みやシステムを共有デファクト化することが重要という。

「特に地方のホテル業の経営者は、視野を広く持ち、“競争”と“共有”を分けて考えるべきです。より良い体験やサービスを提供するために切磋琢磨して他のホテルと競争することは必要です。同時に、自分たちが根を張る地域や業態そのものの活性化を促すため仕組みや情報を共有することも必要なのです(濱野氏)」
観光の醍醐味として、その土地の人や文化と触れ合うことが挙げられる。消費者の観光・飲食体験で得た感動や喜びは、訪れた地域の印象そのものだ。
「地域のさまざまな業種業態がお互いに熱意を持って意見を出し合いながら、宿泊地、観光地が横断的に団結して取り組み、脈々と続いているその土地ならではの自然や文化を含めた観光産業全体を盛り上げていく体制が必要不可欠です。(濱野氏)」
人生を豊かにする観光産業
自らの家業がホテル経営だったという濱野氏。ホテル業・飲食業向けのコンサルティング事業で独立したときは、特に業界に思い入れがあったという。
「私が起業した当時、テクノロジーをうまく使いながら、ホテル・旅館業を中心にサービス産業全般の生産性を上げたいという思いがありました。観光とテクノロジーの融合という私の経営の原点は、まさにそこにあります。

ホテルの経営は売上も大切ですし、スタッフを育成する・お客様との交流の接点を増やすことも大切です。いわば両輪のバランスが重要なのです。気付いているけれどやり方がわからない、あるいはそもそもの原因に気付くための視点がないという事業者に対し、課題解決のご提案やサポートしていくことが私の使命と思いながら、北海道を中心に全国で活動を行っています。
旅行は人生をより楽しく生きるために大切な要素です。日本の宿泊・観光業は、世界でも充分に戦える素晴らしい産業のひとつだと私は胸を張りたいですし、ますます魅力的になってほしいと、心から願っています(濱野氏)」
株式会社サイトシーテック
所在地:北海道札幌市中央区北二条西2-32 第37桂和ビル6階602号
事業内容:ホテル、旅館、飲食店の経営コンサルティング
企業サイト:https://sightseetech.com/