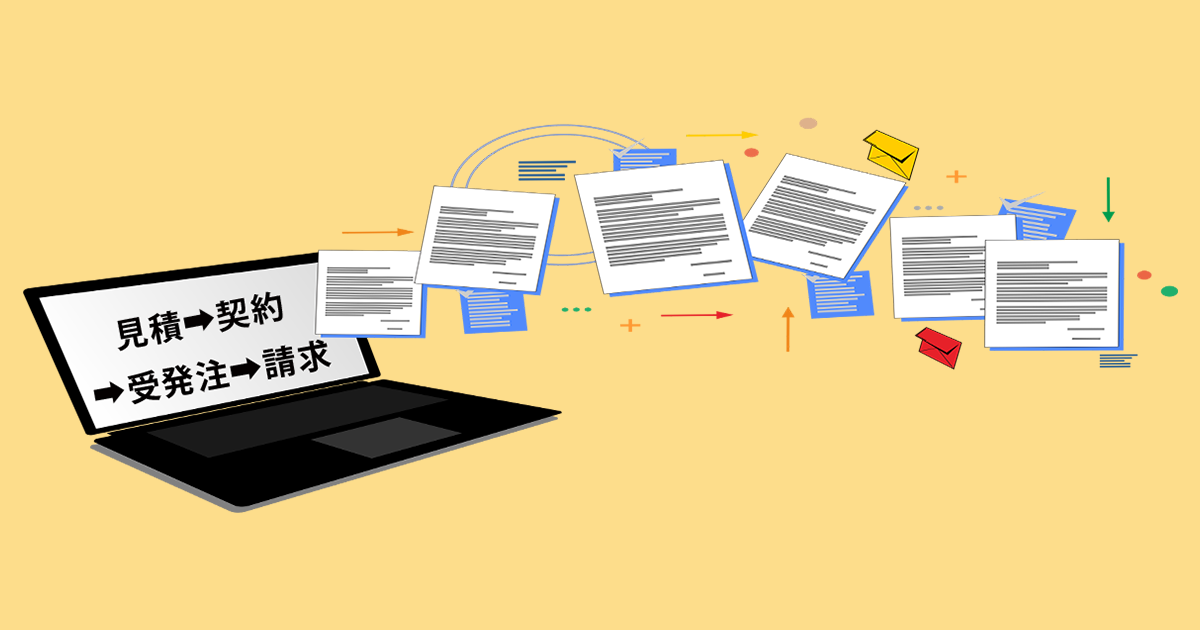各自治体でDX推進が加速度的に進められています。政府が2020年に示した「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」も自治体の動きの後押しになっているひとつでしょう。そこで「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」をビジョンとしたデジタル社会をめざすことが明らかにされました。そして2022年に「デジタル社会の実現に向けた重点計画」が閣議決定され、具体的に自治体が取り組むべき内容が示されました。今回は重点計画のひとつである「システムの標準化・共通化」について、いつまでに何をどう変えていくのかを見ていきましょう。
■ 目次
情報システムの標準化・共通化とは
政府がめざしている「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会」「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」は、「デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及」「国民目線のUI・UXの改善と国民向けサービスの実現」「国等の情報システムの整備および管理」「その他」といった具体的な取り組みによって進められています。
このデジタル社会の実現のためには、自治体のDXの推進は重要なカギとなります。自治体のDX推進の基盤である自治体情報システムの標準化・共通化は住民の利便性を高めるとともに、行政サービス提供業務を効率化するためにも有効な手段だと考えられています。
自治体の情報システムの標準化・共通化というのは、政府がめざしている「デジタル社会の実現」に向けた「デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及」という取り組みの中に含まれる施策のひとつです。全体像を理解するために「デジタル社会に必要な共通機能の整備・普及」に含まれる施策を見ておきましょう。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード
行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。行政機関の情報連携によって、さまざまな行政手続をする際に必要な紙の書類を省略することが可能になります。
公金受取口座登録制度
マイナンバー関連の制度です。
GビズID
行政手続等を行う際の当該法人を認証するための仕組みです。
電子署名
契約書等の電子文書における作成者なりすましや内容の改ざんを防ぐために、電子署名について法律上の定義や効力を規定し、電子署名の正当性を確認する際に必要な認定制度を設けたものです。
電子委任状
法人の代表権付与に関する電磁的記録である電子委任状の普及を促すものです。
ガバメントクラウド
政府共通のクラウドサービスの利用環境です。迅速、柔軟、セキュアでコスト効率の高いシステムを構築可能とし、利用者にとって利便性の高いサービスの提供、改善をめざすものです。地方公共団体でも同様に利点を享受できるよう検討しています。
ガバメントソリューションサービス(ガバメントネットワークの整備)
政府共通の標準的な業務実施環境(パーソナルコンピュータやネットワーク環境)の提供を行います。
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化
地方公共団体が、基幹業務システムについて、ガバメントクラウド上に構築された標準化基準を満たすアプリケーションの中から自らに適したものを効率的かつ効果的に選択することが可能となる環境を整備します。
自治体窓口DX「書かないワンストップ窓口」
地方自治体との共創によって地方自治体における「書かない、待たない、回らない、ワンストップ窓口」を実現します。
サイバーセキュリティ
情報システムの設計・開発段階を含めたセキュリティの強化を図ります。
データ戦略
最大のデータ保有者である行政機関自身が国全体の最大のプラットフォームとなるべく、データの分散管理を基本として、包括的データ戦略の実装(トラスト基盤の構築、基盤データの整備、データ連携を可能とするシステム構築など)に取り組みます。
DFFT
データに対する基本的考え方や理念を共有する国々と連携し、データ流通に関する国際的なルール作りや議論等を推進し、提唱国として責任を持ってDFFTの実現に向けて取り組んでいきます。
自治体の情報システムの標準化・共通化の方法と方針
自治体の情報システムの標準化・共通化に利用されるのは、政府が構築を進めているガバメントクラウドと呼ばれる政府共通のクラウドサービスです。クラウドサービスの利点を最大限に活用することで、迅速、柔軟、かつセキュアでコスト効率の高いシステムを構築可能とし、利用者にとって利便性の高いサービスをいち早く提供し改善していくことを目指します。
ガバメントクラウド上には標準化の要件を満たしたアプリケーションが構築されます。ガバメントクラウド上に構築されたアプリケーションの中から、必要なものを選択して活用することになります。
ただし、2022年に閣議決定された「地方公共団体情報システム標準化基本方針」では、ガバメントクラウドの利用が必須ではないことを明記し、「ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境の方が、性能面や経済合理性等を比較衡量して総合的に優れていると判断する場合には、当該ガバメントクラウド以外のクラウド環境その他の環境を利用することを妨げない。」としています。
自治体DXに関する内容は以下の記事を参考にしてください。
スケジュールと対象の基幹系業務システム

自治体の情報システム標準化・共通化の対象となる業務はどういったものなのか、また、ガバメントクラウドを活用した標準準拠システムへの移行はいつまでをめざすのか、具体的な内容を確認していきましょう。
2025年度までの移行をめざす
政府は、基幹業務システムを利用する地方公共団体が2025年度までにガバメントクラウドを活用した標準システムへ移行することを目標として掲げています。
具体的には、2023年4月から2026年3月までを「移行支援期間」としています。
全体の動きは以下のスケジュールで進められます。
ガバメントクラウドの整備:2020年度〜2025年度
ガバメントクラウドの提供(地方公共団体関係):2020年年度〜2025年度
地方公共団体の標準準拠システムへの移行:2023年度〜2025年度
自治体システムをガバメントクラウドへ移行する手順
ガバメントクラウドへの移行は、現行のシステムによって異なりますが、次の方法で移行を進めていくのが一般的な手順です。
1. 現行システムの構成と機能を洗い出す
洗い出す内容は以下の内容です。
- 業務システムの基礎情報
- 外部への委託状況
- 現行システム利用拠点
- 業務主管部署ごとのシステム利用状況
- データ量
- 周辺機器
- システム間でのデータ連携状況
2. 現行システムと標準仕様の差を分析する
3. 移行計画を作成する
計画書には「移行目的」「移行方針」「調達する範囲や単位」「調達方式」「スケジュール」「移行による課題と対策」「推進体制」等を盛り込みます。また、移行計画は関係担当者間で検討しながら作成をして、共有しておくことが大切です。
4. ベンダーを選定する
移行計画の作成が終わった段階で、ガバメントクラウド上の基幹システムを構築・運用するベンダーを選びます。ベンダーを選定するさいには、作業を依頼するにあたっての要件や費用など、確認しておきます。
また、すでに依頼するベンダーが決定している場合は、この手順項目は飛ばします。
5. 契約を締結する
依頼するベンダーとデジタル庁と契約を締結します。デジタル庁には「ガバメントクラウド利用権付与・運用管理委託契約」と「ガバメントクラウド運用管理補助委託契約」の締結をします。
6. システム移行時の設定を行う
標準準拠システムをもとにして運用シミュレーションをしたのち、運用方法を決めていきましょう。
現行のシステムと操作が変わる場合もあるため、新しいシステムの機能について、よく確認しておく必要があります。
7. データを移行する
既存のデータを整理して、バックアップを取ります。その作業が終了したら、移行すべきデータを移します。
8. 運用テストを行う
データが移せたら、運用テストを行います。移行したデータに問題はないか、連携のさいに問題が発生しないかなどを確認します。
また、職員がシステムを使えるように研修会を開いたり、直接操作をして操作性を実感したりできる機会を設けます。運用開始までには使えるように準備を進めます。
9. ネットワークに接続し、標準準拠システム活用の環境構築を完了させる
運用テストで問題のないことが確認できたら、環境構築し、ネットワーク接続をします。端末の動作、プリンタ等の周辺機器が問題なく稼働するかの確認も行います。すべてが順調に稼働することが確認できれば、移行作業は完了です。
対象となるのは20業務
自治体の情報システム標準化・共通化の対象となる業務は20の基幹業務です。2020年に示された「デジタル・ガバメント実行計画」では主な17業務を処理する基幹系システムの標準化・共通化をすることが示されていましたが、3業務が追加され20業務を対象として取り組みを推進することになっています。
児童・子育て支援関連業務
児童手当、児童扶養手当、子ども・子育て支援
住民基本台帳関連業務
住民基本台帳、国民年金、選挙人名簿管理
税関連業務
固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税
国民健康保険関連業務
国民健康保険
障害者福祉関連業務
障害者福祉
介護福祉関連業務
後期高齢者医療、介護保険
その他の業務
生活保護、健康管理、就学、印鑑登録
戸籍関連業務
戸籍、戸籍の附票
自治体の情報システムを標準化・共通化することのメリット
政府がデジタル社会の実現をめざし、さまざまな取り組みを推進する姿勢を明確にしたことで、地方自治体においても、DX推進への取り組みが本格的に動き始めています。自治体の情報システムを標準化・共通化することもそのひとつです。こうした取り組みを推進することにはどんなメリットがあるのでしょうか。ここでは情報システムを標準化・共通化をすることのメリットを考えてみましょう。
コスト削減・ベンダロックインの解消
標準準拠システムが利用されるようになれば、自治体が個別に情報システムを開発する必要はなくなります。そのことで、人的にも財政的にも負担軽減が期待できるでしょう。さらに、サーバーの監視や機器のメンテナンス等の作業も不要になるため、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストの削減にもつながります。
また、複数のクラウドサービスから事業者が選択可能な状況を整備することで、クラウドサービス提供事業者間の競争環境を確保し、ベンダロックイン(ベンダロックイン:特定ベンダの技術に依存した製品やサービスなどを採用した情報システム構成にすることで、他ベンダの同種製品への乗り換えが困難になること。)を防止することができます。さらに、アプリケーションレベルにおける複数の事業者による競争環境を確保することもできます。標準化・共通化を推進することはベンダロックインの解消につながるとともに、ベンダの競争環境の確保にも寄与するものです。
住民の利便性向上
標準化・共通化を通して職員の業務負担が軽減される結果、住民への直接的なサービス提供といった、本来、重視すべき業務に時間を使えるようになります。また、こうした職員の負担軽減は、労働力不足の中にあって、持続的に行政サービスが提供できる体制整備にもつながります。
行政運営の効率化
標準準拠システムの利用にあわせて、標準化対象事務に係る業務フローを見直すことになります。つまり行政運営の効率化を図ることにつながるといえるでしょう。また、自治体がサーバーやハードウェア、OS、アプリケーションなどのソフトウェアを自ら整備し、管理する負担も軽減されます。そのほかシステムに関わる情報セキュリティ対策は、ガバメントクラウドが一括して行います。そのため、これまで各自治体が個別に実施していた情報セキュリティ対策が不要となり、運用や監視にかかっていた時間やコストが削減できます。
まとめ: 情報システムを標準化・共通化によって自治体DX推進が加速され、利便性の高い行政サービス提供が実現される
自治体のDXは職員にとっても住民にとってもメリットのある取り組みです。その推進のカギともなるのが自治体情報システムの標準化・共通化です。
ガバメントクラウド上のシステム利用へ切り替える目標期限は2025年度。早急に準備をはじめなければ間に合いません。システム移行に向けた計画の策定や業務の変更、それにともなう体制の再構築など、段階ごとの取り組みを着実に進めていくことが大切になってくるでしょう。
またガバメントクラウド上のシステム利用へ切り替えると同時に、ベンダーとの協力体制も強化することが重要です。単にシステムを導入するだけでなく、効果を発揮するためには、ベンダーとの協力が必要不可欠です。ベンダーとは、クラウドサービスやソフトウェア、コンサルティングサービスなどを提供する企業のことを指します。
導入後には、システムの使用方法や活用方法に関してベンダーとすり合わせを行い、不明点のサポートを受けることで、システムを有効的に活用できるようにもなります。ベンダーとの協力体制を強化し、ベンダーと伴走しながら、システムの効率的な運用を行うことで、より良いシステム標準化を実現できるでしょう。
IT系に知見がある人材が不足している自治体は、アフターサポートや保守サービスが厚いベンダーを選ぶことをおすすめします。
※本記事は更新日時点の情報に基づいています。
監修者プロフィール

一般社団法人 未来創造ネットワーク 代表理事
松藤 保孝 氏
自治省(現総務省)入省後、三重県知事公室企画室長、神奈川県国民健康保険課長、環境計画課長、市町村課長、経済産業省中小企業庁企画官、総務省大臣官房企画官、堺市財政局長、関西学院大学大学院 法学研究科・経営戦略研究科教授、内閣府地方創生推進室内閣参事官等を歴任し、さまざまな政策の企画立案、スリムで強靭な組織の構築、行政の業務方法や制度のイノベーションを推進。一昨年退官後、地域の個性や強みを生かすイノベーションを推進する活動を行う。