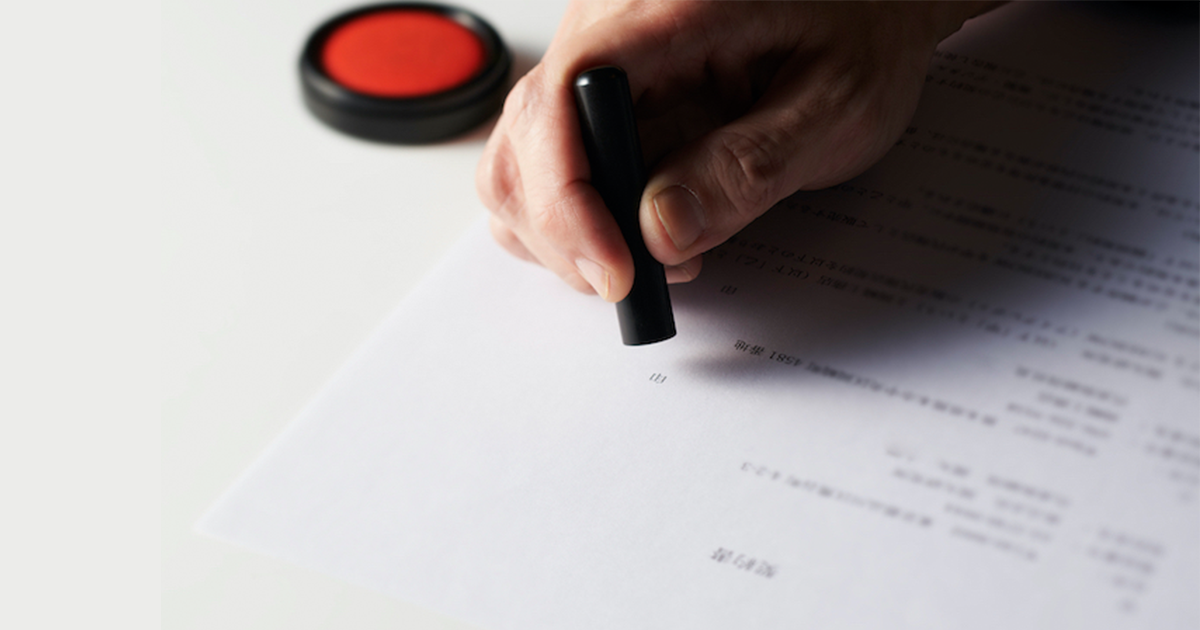日本社会に根付く「押印文化」。その慣習を見直し、行政手続きの効率化とデジタル化を推進するため、政府主導で押印廃止への動きが加速しています。
しかし、押印廃止の必要性は理解していても、実際に何から手を付けていいのかわからないという担当者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、押印廃止の進め方について総務省が推奨する手順を参考にご紹介します。また押印廃止を成功させるポイントや廃止後の展望についても解説します。ぜひ本記事を最後まで読み進めて、住民や企業、また、自治体の担当者の時間やさまざまな負担を解消する体制を整えていきましょう。
押印廃止とは
まずは押印廃止とは何か、あらためて確認していきましょう。
押印廃止の定義と背景
自治体における押印廃止とは、行政手続きにおいて、これまで慣習的に求められてきた書類への押印を不要とする取り組みです。その背景には、政府が推進するデジタルガバメント実現への働きかけがあります。
例えば、住民票の写しを請求する際、多くの自治体で申請書への押印が必要とされてきました。しかし、これでは窓口に出向かなければならず、オンライン申請への移行の障壁となります。押印のために出社を強いられる「ハンコ出社」も社会問題化しました。
こうした状況を改善し、行政手続きのデジタル化とペーパーレス化を進めるため、政府は積極的に自治体に押印廃止を要請しているのです。
自治体の押印文化に対する企業からの悲鳴
民間企業からも、自治体に対して押印文化の廃止を求める声があるのが実情です。
弊社が自治体と取引がある民間企業を対象に実施した「自治体の会計業務に関する実態調査」では、多くの企業が自治体独自のルールによるコスト増や業務効率に課題を感じています。
具体的には、以下のようなお悩みがあることが多いようです。
- 紙でのやりとりが多く、郵送費・保管費などのコストがかかる
- 押印のために出社しなければならない
- 再発行の際に手間がかかる
自治体ならではの慣習に悩まされる企業は多く、自治体は早急な対応が求められます。
自治体の会計業務に関する実態調査の詳細はこちらから
押印廃止のメリット
押印廃止には、以下のようなメリットが期待されます。各メリットを正しく理解することで、庁内にも効果を伝えやすくなります。
業務効率化と生産性向上
書類への押印や押印確認の作業が不要になることで、行政側の事務処理がスピードアップします。また、紙の書類を扱う手間も減り、業務全体の生産性向上も期待できます。企業側にとっても、再発行や郵送などの付加価値のない作業が削減され、本来の業務に集中できるようになります。
コスト削減とペーパーレス化の実現
押印に使う印鑑の作成・管理コストや、紙の書類に要する印刷・保管コストが削減できます。ペーパーレス化も進み、環境負荷の低減にもつながるでしょう。
テレワークの推進と多様な働き方の実現
押印のためだけに出社する必要がなくなれば、場所や時間に縛られない柔軟な働き方が可能です。育児や介護との両立など、多様な人材が活躍できる環境づくりにもつながるでしょう。
さらに、企業からは「行政から働き方改革を求められているのに、その行政の自治体が対応してくれない」といった不満を持っているようです。テレワークの重要性が広く認識されるようになってきた状況下で、自治体が率先して押印廃止に取り組むことは急務といえるでしょう。
押印廃止の概要やメリットについては、以下の記事が参考になります。
押印廃止の進め方5ステップ

押印廃止を実施するには、以下の5ステップで進めます。
- - ステップ1. 組織の合意形成
- - ステップ2. 推進体制の整備
- - ステップ3. 押印手続きの棚卸し
- - ステップ4. 見直し方針の策定
- - ステップ5. 押印廃止の実行
ステップごとに、概要やポイントについて説明します。
ステップ1. 組織の合意形成
押印廃止を進めるには、関係者の理解が必要となりますが、全庁的な意思統一が不可欠です。デジタル化のメリットを職員に丁寧に説明し、「押印=正式な手続き」という固定観念を払拭することが重要です。
また、「ハンコがあれば安心」「ハンコを押さないと不安」といった声にも真摯(しんし)に耳を傾け、電子決裁の仕組みや法的な効力について分かりやすく説明します。押印廃止が業務効率化につながり、住民サービスの向上にもつながる、という点を強調し、職員の理解と協力を得ましょう。
ステップ2. 押印廃止を加速する体制の整備
押印廃止を速やかに進める為に、全庁的な関係者が参加する会議を開催し、押印の目的、法的な意義、押印廃止のメリット等について意見交換し、課題やその対応策を整理し、共有し、また、進捗を管理し、全庁的に一気に進めることも有効です。
各部署から押印廃止の推進担当者を選任し、部署横断的なプロジェクトチームを結成したり、押印廃止に詳しいデジタル化を専門とする外部の専門家の意見を聞くことも効果的です。庁内では気付きにくい業務の非効率や押印廃止のポイントを指摘してもらい、全庁的な意識改革を促しましょう。
ステップ3. 押印手続きの棚卸し
押印廃止を進めるうえで、現状の押印手続きを徹底的に洗い出し、その必要性を見直すことが重要です。この業務は、押印廃止の成否を分ける鍵となるプロセスとも言えるでしょう。
まず、各部署が所管する条例、規則、要綱などを網羅的に調査し、押印を求めている手続きをリストアップします。そのうえで、それぞれの手続きについて、押印の法的根拠や必要性を精査していきます。
ここで注意すべきは、「昔からハンコを押してきたから」といった慣例や前例にとらわれないことです。確かに、長年の習慣で押印が当たり前のように扱われてきた手続きは少なくありません。しかし、押印廃止を進めるためには、そうした慣習にとらわれず、ゼロベースで押印の是非を問い直す必要があります。
例えば、押印の目的が本人確認の一つの手段であれば、本人確認の有効な手段は押印以外にもたくさんあります。安易に、法令に規定しているからではなく、その意義を理解することが必要です。押印が必要不可欠でない場合には、条例や規則の方を改正すべきでしょう。
具体的に明確な必要がなければ、地域の住民や企業の時間やお金のリソースを割き、生産性を低下させることになってしまいます。
また、押印見直しの基準を庁内で統一しておくことも重要です。単に印鑑を廃止すればいいというわけではありません。あくまで、住民の利便性向上と行政効率化を目的として、廃止可能な手続きを特定していく必要があります。
下記の記事では、押印省略の効果や各団体の取り組み状況について解説しています。
ステップ4. 見直し方針の策定
棚卸しの結果を踏まえ、押印手続きの見直し方針を策定します。申請書類の様式変更や、電子申請システムの導入など、具体的な代替手段を盛り込むことが重要です。
押印廃止を先送りせず、できることから迅速に対応していくことが重要です。各部局が所管する手続きの押印廃止や業務の改善が速やかに進むよう、全庁的な見直し方針を策定し、課題やその解決策の共有や進捗管理を行うことも有効です。
ステップ5. 押印廃止の実行
押印廃止の方針が固まれば、いよいよ実行段階です。住民や取引先に対し、ホームページやSNS、広報紙など、あらゆる媒体を活用して周知を図ります。
「なぜ押印が不要になるのか」「電子申請の具体的なメリットは何か」など、押印廃止の意義を分かりやすく伝えましょう。オンラインでの手続き方法を動画で紹介したり、よくある質問とその回答をQ&Aでまとめたりと、工夫次第で住民の不安や抵抗感は和らげられるはずです。
また、窓口での対応も重要です。高齢者や外国人住民など、デジタルに不慣れな住民へのサポート体制を整え、柔軟な対応を心がけましょう。
一方、行政内部でも、押印廃止をデジタル化推進の起爆剤と位置付け、業務全体の見直しを進めます。ペーパーレス化や業務のシステム化など、できることから着実に実行し、押印廃止の効果を実感できるようにすることが重要です。
最終的には、行政手続きの簡素化と迅速化を住民にアピールし、押印廃止が住民サービスの向上につながることを強調しましょう。窓口の混雑緩和や申請処理の早期化など、具体的な成果を示すことで、住民の共感を得られるはずです。
押印廃止を成功させるポイント

押印廃止をトラブルなく進行するためには、ポイントがあります。
法的効力・セキュリティを担保できるシステムを導入する
押印の大きな役割のひとつが、本人確認と文書の真正性の担保です。つまり、押印された文書は、本人の意思に基づいて作成され、内容が改ざんされていないということを保証するものです。
押印を廃止する際は、これらの機能を電子的に代替する方法を確立する必要があります。具体的には、電子署名や認証システムの導入が有効でしょう。電子署名法に基づく適切な電子署名を用いることで、押印と同等の法的効力を担保できます。
電子データの改ざんを防止し、万一のトラブルの際に確実な証拠能力を確保できるようなシステム設計になっているか、十分に確認しておきましょう。
また、押印廃止によって行政手続きが電子化されれば、大量の個人情報がデジタルデータとして管理されることになります。これは、サイバー攻撃のリスクが格段に高まることを意味します。
特に、住民の機微な情報を扱う自治体は、サイバー攻撃の標的になりやすいと言えるでしょう。マイナンバーをはじめとする行政情報の流出は、住民の信頼を大きく損ねかねません。
そのため、押印廃止に向けたシステム構築においては、セキュリティ対策を徹底することが極めて重要です。最新のセキュリティ技術を導入したり、定期的なぜい弱性診断をしたりと、多層的な防御策を講じる必要があります。
加えて、職員に対するセキュリティ教育も欠かせません。人的なぜい弱性を突いたサイバー攻撃も多いため、職員一人ひとりのセキュリティ意識を高め、適切な対応力を身につけることが求められます。
利用者(住民・事業者)への丁寧な説明と周知を行う
行政手続きから押印をなくすことへの住民や事業者からの「本当に安全なのか」「手続きが面倒になるのでは」といった不安の声にも真摯(しんし)に耳を傾け、丁寧に説明することが求められます。
また、周知方法も工夫が必要です。ホームページや広報誌での案内はもちろん、動画コンテンツやSNSを活用するのも効果的でしょう。
また、問い合わせの増加も見込まれます。FAQの整備や専用のコールセンター設置など、利用者の疑問や不安に細やかに対応できる体制を整備しておくことでクレームも回避しやすくなります。
例外的に押印が必要な手続きには個別で対応する
法律で押印が義務付けられている一部の例外的な手続きでは、押印の完全廃止が難しい場合もあります。こうしたケースをあらかじめ洗い出し、代替手段を検討しておく必要があります。
取引先の事情で押印が必要な場合は、過渡期の措置として、一部の手続きに限って押印を残すことも選択肢のひとつでしょう。
ただし、あくまで例外的な措置であることを明確にし、原則として押印廃止を進める方針は揺るがないことを内外に示す必要があります。一部の例外を理由に、全体の取り組みが滞ることのないよう注意してください。
廃止後の効果も検証する
押印廃止は、業務フローや様式の大幅な見直しを伴います。電子化のメリットを最大限に引き出すため、単に押印をなくすだけでなく、業務プロセス全体の効率化を図ることが重要です。
そのためには、押印廃止後の業務の流れを可視化し、適切にマネジメントすることが求められます。特に、電子決裁の導入やワークフローシステムの管理など、庁内の意思決定プロセスの変更には細心の注意が必要です。
また、押印廃止の効果を定期的に検証し、PDCAサイクルを回すことも欠かせません。単に押印がなくなった件数だけでなく、手続きの所要時間や住民の満足度など、多面的な指標を用いて評価しましょう。
検証で得られた課題を次の改善につなげ、押印廃止を起点により良い行政サービスを追求する姿勢が重要です。
押印廃止後の展望
本記事でも見てきたように、押印廃止は、押印の必要性や法的な意義を正しく理解したうえで、地域の住民や企業に不必要な負担をかけることなく行政サービスを進めるきっかけとなるテーマです。
押印廃止を成し遂げることで、どんな変化が見込めるのでしょうか。
廃止後の展望について見ていきましょう。
業務のデジタル化加速とDX推進
押印廃止は、単なる手続きの電子化にとどまりません。むしろ、自治体業務全体のデジタル化を加速する絶好の機会と捉えるべきです。紙の書類に依存した非効率な業務フローを抜本的に見直し、ペーパーレス化や業務自動化を一気に進めることで、行政サービスの質と効率を飛躍的に高められるはずです。
D to D(Data to Data)システムやAI-OCR、RPAなどの先進技術を活用したツールを導入することで、単に業務効率を高めるだけでなく、人的ミスの防止やサービスの質の向上にもつながるでしょう。
ペーパーレス化による環境負荷の低減
押印廃止でペーパーレス化すると、大量の紙資源の節約やSDGs(持続可能な開発目標)の達成にも貢献します。
申請書類の電子化で、年間数百万枚もの紙の削減効果が見込めるケースも珍しくありません。さらに、書類の保管スペースを削減できれば、庁舎の省エネ化も可能です。こうした資源・エネルギーの無駄を省くことは、自治体のGX(グリーントランスフォーメーション)を加速する大きな一歩となります。
押印廃止は、自治体のグリーン化推進の切り札として、新しい時代の行政サービスのあり方を示す象徴的な取り組みとなるのではないでしょうか。
まとめ:押印廃止で行政効率化と企業負担の軽減を実現
行政手続きから押印をなくすことで、行政の業務効率化やコスト削減など幅広い効果を期待できるため、積極的に取り組みを進める必要があります。同時に、現在、多くの企業が自治体の押印慣行によって深刻な負担を強いられており、各方面から不満の声があがっています。この現状を看過することなく、早急に対応することが求められます。
また、押印廃止を真に効果的なものにするためには、ペーパーレス化とセットで進めることが不可欠です。
近年、電子決裁システムを導入する自治体が増えていますが、これだけでは不十分です。決裁に付随する紙帳票(見積書、請求書、契約書など)もセットで電子化することで、本当の意味での業務効率化は実現できるでしょう。
インフォマートでは、ペーパーレス化を実現できるソリューションをご提供しております。
商品の特長や機能、導入事例については、以下をご参照ください。
※本記事は更新日時点の情報に基づいています。
監修者プロフィール

一般社団法人 未来創造ネットワーク 代表理事
松藤 保孝 氏
自治省(現総務省)入省後、三重県知事公室企画室長、神奈川県国民健康保険課長、環境計画課長、市町村課長、経済産業省中小企業庁企画官、総務省大臣官房企画官、堺市財政局長、関西学院大学大学院 法学研究科・経営戦略研究科教授、内閣府地方創生推進室内閣参事官等を歴任し、さまざまな政策の企画立案、スリムで強靭な組織の構築、行政の業務方法や制度のイノベーションを推進。一昨年退官後、地域の個性や強みを生かすイノベーションを推進する活動を行う。