文書管理システムというのは庁内で活用している文書を正しく整理整頓して保存し、必要なときに、必要な文書をスムーズに取り出せるように管理するためのシステムを指します。ファイルを一元管理するという機能だけを考えるとファイルサーバーの活用で同じことができると考えられますが、文書管理システムは文書を管理・活用することに特化した機能が搭載されているものが一般的です。例えば、文書を作成し、利用し、保管し、廃棄するまで一連の作業を安全に管理できる体制が構築できます。今回は自治体で文書管理システムを導入する利点やシステムの選び方、活用についてみていきましょう。
■ 目次
自治体で文書管理が必要な理由
「公文書等の管理に関する法律」が制定され、2011年より施行されました。公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)の施行により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。
公文書等というのは、公文書管理法第2条第8項によると、行政文書、法人文書、特定歴史公文書等をいいます。
もう少し詳しくみておくと次のとおりです。
- 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項) - 法人文書
独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項) - 特定歴史公文書等
歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)
政府をはじめ、地方自治体でも、公文書管理は民主主義の根本にかかわる重要なテーマです。
「公文書等の管理に関する法律」に対応していくことは、行政が適正かつ効率的に運営ができるようにすること」を実現するための対応ということでもありますが、既存のように紙文書で管理をしている体制から電子化を進め、電子決裁等を投入することで、公文書等を作成から廃棄までをシステム上で管理できるようになります。また、その過程にかかわる、文書作成、決済業務、保存、引き継ぎ、廃棄といった業務において、効率化を図ることが期待できます。その他、紙文書を保管するスペースの削減、保管文書の紛失防止に関する対策、不正な修正・廃棄を抑制するための対策といった点も削減でき、さまざまなメリットがあると考えられます。具体的には次の項で説明していますが、こうした多くのメリットの実現の結果、本来の住民への行政サービス提供をより充実させることも可能になると考えられます。
自治体における文書管理システム導入で期待できる効果
まず、文書管理システムとはどういったシステムで、どのような機能が搭載されているのかを正しく理解しておきましょう。それぞれの搭載機能によって、どのような効果がもたらされるのかについても、考えておきましょう。
文書管理システムの主な機能
文書管理システムというのは、庁内で扱う書類を電子化して、文書の作成から廃棄までのすべてを一元管理するシステムです。主に次の機能が搭載されています。それぞれの機能を活用することでどのようなことが可能になるのかも併せて確認しておきましょう。
保管機能
文書管理システムには文書データを種類ごとに分類して保管する機能が搭載されています。
期待できる効果
分類して保管できるため、必要な文書へのアクセスが容易となるほか、更新する必要のある文書を検索することも簡単に行えます。さまざまな端末や各部署で保管され分散していた文書を一元管理できるようになることで、同じ文書が複数保存されていたり、どちらが最新のデータなのかが不明になったりする混乱が避けられます。
検索機能
文書内に保管されているすべての文字情報からキーワードを検索することができます。
期待できる効果
文書管理システムに保管された文書を検索する場合は、多くの文書管理システムに搭載されている「全文検索機能」を使うと便利です。文書内のすべての文字情報からキーワードを検索することができますので、短時間で効果的に求める文書を探すことができます。そのほか、文書を電子化し保存するときに設定したタグや属性情報から検索することもできるなど、多くの検索機能が搭載されています。
アクセス管理・セキュリティ機能
文書管理システムには、保存されている文書にアクセスする権限を設定することができ、セキュリティを高めるために活用できます。アクセス権限を設定することで、限られた人しか文書を開示・編集ができないように制限することが可能です。
期待できる効果
文書の使用や閲覧を限られた人に絞ることで、不正なアクセスや持ち出しを厳しく監視することができるので、機密文書の保存にも安心して活用できます。
バージョン管理機能
文書管理システムで最新の文書データを一元管理できます。
期待できる効果
保存している文書はそれぞれのタイミングで活用され、更新される可能性があります。各部署や担当者の端末に保存されていた状態では、同じ文書が複数存在し、どれが最新のデータであるのかが不明になるケースが少なくありません。こうしたバージョン管理においても文書管理システムで一元管理することで常に最新の文書データを保存・活用することができます。
文書のライフサイクル管理機能
文書には、作成・活用・保管・更新・廃棄といったライフサイクルがあります。それぞれの文書のライフサイクルを適切に管理することができます。
期待できる効果
文書のライフサイクルを管理することで、例えば、契約書の期限管理を正確に行うことで更新時期の確認もれによる失効等のミスが防げます。このような文書のライフサイクル管理機能も文書管理システムに搭載された有効な機能です。
ワークフロー機能
登録した文書に対して電子承認のプロセスを設定することができる機能です。
期待できる効果
これを活用することで、外出先やテレワーク時でも文書の承認や回覧受領ができるようになります。
稟議書・決裁書などを関係者に回して、承認を得るフローにおいて、承認者が外出している場合、フローが中断され、スムーズに承認が得られないケースがあります。しかし、文書管理システムのワークフロー機能を活用すれば、申請から承認までの履歴が残せるのはもちろん、脱ハンコを実現することもでき、スムーズに作業を完了させることが可能です。
外部システムとの連携機能
文書管理システムにはAPI連携が可能なシステムがあります。APIというのは、外部のさまざまなシステムやアプリケーションとのデータの交換や機能の統合を可能にする仕組みです。文書管理システムでAPI連携をすると顧客管理(CRM)システムやプロジェクト管理ツールと連動して、データの共有や更新をより簡単に行えるようになります。
期待できる効果
外部システムとの連携がスムーズにできることで、例えば、住民等の情報と関連する文書を結び付けることができるようになります。こうした環境が整えば、行政サービスを行う上で、住民等の最新情報を踏まえたうえで、最適な対応ができるようになります。また、プロジェクトの進捗に関する文書をリアルタイムで更新したり、必要な文書をプロジェクト実施中にすぐに検索し、活用したりすることもできます。
これらの機能のほかに、電子決裁機能が搭載されたものもあります。
こうした多様な機能を必要に応じて活用することで、業務の効率化を図るだけでなく、データを有効に活用することが可能になるのです。
自治体DXの進め方や課題と対策については、次の記事が参考になります。
自治体が文書管理システム導入する際の手順
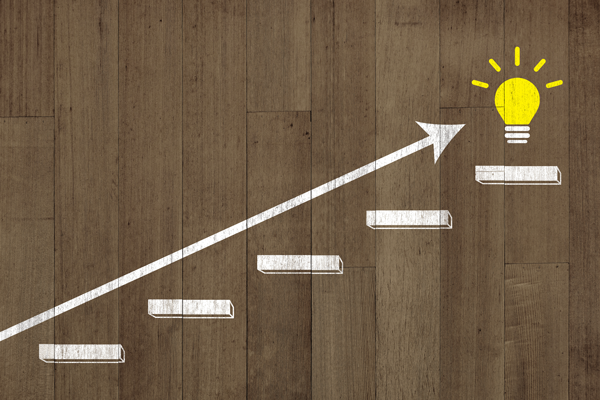
自治体が文書管理システムを導入する際には、まずは2つの視点で取り組むことが必要です。
1つめは、長期的な視点で取り組むこと。2つめは小さくはじめて拡大していくこと。
自治体がDXを推進する場合、混乱や失敗を避けたいお考えもあると思います。その場合、取り組みやすいところから、導入しやすいところからデジタルツールを導入し、定期的に効果を検証し、その効果を実証し、必要な修正をしながら、新しい業務のやり方を浸透させていきます。一方で、まず始めないと、何にも変わりません。ゴールを目指していく継続的な行動が重要なのです。
そのうえで、大まかに分けて4つの主要なポイントに焦点を当てて進めていきましょう。
目的を明確にし、達成するための機能をそなえた文書管理システムを選ぶ
文書管理システムの導入に際しては、どのような機能が搭載されたシステムを選ぶのかを決めなければなりません。そのためには、何をしたいのか、要件・目的を明確にすることが必要です。
目的を明らかにするには、まず、業務における課題を洗い出し、その重要度やその課題が解消することによって削減されるコスト、工数、ミスなどを考慮しながら優先順位を決めましょう。さらに、業務担当者からの意見も優先順位決定に考慮することが重要です。
優先順位が確定したら、それらを解決するために必要な機能を搭載したシステムを複数選びましょう。
文書管理システムの仕様を庁内業務に合わせてカスタマイズも検討する
導入候補となる文書管理システムを複数選んだ後は、さらに詳しくシステムを調べてみましょう。実際にデモをみる、ベンダーから提案を受けるなど、具体的な操作性、バージョンアップ、機能拡張などの観点から評価を行います。
必ず確認しておくべき点は、庁内業務に合わせてカスタマイズが可能であるか、そうした際にベンターからのサポートはどの程度受けられるのか、などです。運用し始めると何かしらの不具合、トラブル、不明点などが発生するものです。そうした際のサポートや技術提供が受けられるのかについて、ベンダーの対応も十分に確認しておく必要があります。
文書管理システムを運用し、修正を行う
システムを導入して、環境を構築したのちは、すぐに本格運用をするのではなく、利用者や業務を限定して試運転を行いましょう。その時点で問題があれば、修正を繰り返します。試運転が問題無く実行できれば、本格運用へと移ります。
本格運用をはじめたのちにも、定期的に効果を評価したり、操作性を確認したりしながら、修正・改善を繰り返す必要があります。
導入後の効果(費用対効果も含め)を測定する
一定期間、本格運用を続け、費用対効果を測定します。すぐには効果として現れないものですが、PDCAサイクルを回しながら継続することが重要です。
また、文書管理システムを導入する業務についても、最初は優先順位から限られた範囲でスタートをし、効果をみながら徐々に庁内全体へと拡大していくようにしましょう。
その場合、自治体内部の効果だけではなく、地域の住民や、地域の企業の方々にとっての効果、さらに自治体の新たな政策立案による住民の方々への効果を、総合的に判断することが重要です。
文書管理システムの選び方
自治体において文書管理システムを導入する場合、どのようなシステムを選べばよいのかについて考えてみましょう。
各システムを比較する際の基本的なポイントは以下のとおりです。
比較ポイント
クラウド型かオンプレミス型か
文書管理システムにはクラウド型とオンプレミス型があります。
クラウド型はシステムの提供企業のサーバー上で使用するためサーバーの準備などに係る導入コストが低く抑えられます。またバージョンアップの管理も提供企業側が行うのが基本なので手間がかかりません。一方、オンプレミスに比べるとセキュリティ面に不安が残るという考えもあります。セキュリティ体制が提供企業側の基準で実施されますが、最近では、クラウド型でも、かなりのレベルのセキュリテイー対策を講じることが多く、高いセキュリテイーレベルにすることが当然の前提となっています。
オンプレミス型のメリットは自社内で完結するためセキュリティリスクが低いことです。ただし、文書管理システムを導入するには、サーバー管理や定期メンテナンス、バージョンアップへの対応など自社が行う必要があり、それらのコストが高額になります。また、セキュリテイーを追求するあまり、一般的な自治体業務を行う必要性以上の過大な機能にコストを払うことにもなりかねません。
目的を達成できる機能があるか
文書管理システムにはタイプによって特化した機能があります。自治体においてどのような業務において、どのような作業を対象としているのかによって、必要となる機能は異なります。一般的な機能ではなく、目的に応じた機能に合わせてシステムを考える必要があります。
他のシステムとの連携はできるか
文書管理システムと他のシステムが連携できれば、文書を一元管理できるようになります。例えば、ワークフローシステムとの連携が可能となれば、承認後のデータを効率的に、確実に管理できるようになります。文書として保存が確実になれば、データの改ざんや不正利用の防止にもつながると期待できます。このように他のシステムと連携ができることで、機能を拡張することができます。
検索のしやすさ
文書管理システム導入の目的のひとつとして、必要な文書にスムーズにアクセスできることが挙げられます。いいかえれば、検索性の高さが必要なのです。
法令や各種制度への対応
文書の種類によっては法令や各種制度に沿った文書管理が求められます。適切な書式、保管方法、保管期間など、必要と想定されるそれぞれの規定に沿った文書管理ができるのかどうかを確認しておきましょう。
JIIMA認証の有無
JIIMA認証というのは、ソフトウエアやソフトウエアサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックして、法的要件を満たしていると判断したものに与えられる認証です。この認証があることで、電子帳簿保存法に基づいて管理が可能なシステムであると判断できます。
セキュリティ設定・アクセス制限
クラウド型の文書管理システムを検討している際には、セキュリティの水準を確認しておくことが重要です。例えば、閲覧・編集などへのアクセス権限を設定できるか、アクセスや操作履歴を確認できるか、ダウンロードや印刷を禁止する機能はあるか、アカウントロックや多要素認証など、不正アクセス防止の仕組みはあるか等を確認しましょう。
文書管理システムのタイプを理解し、やりたいことができるかどうかを判断する
上記で紹介した比較ポイントのなかで、目的を達成できる機能があるかどうかを検討するためには、まず、文書管理システムに搭載されている機能と、実現したい業務のあり方や効果が合っているかどうかの確認をしましょう。それぞれの文書管理システムにはさまざまな機能が搭載されています。どのようなシステムなら、どういった作業ができるのかを理解しておくと、最適なシステムを選ぶことができるでしょう。
最適な文書管理システムを選ぶには、それぞれのシステムのタイプを理解しておくと判断しやすくなります。
ここで大まかに文書管理システムのタイプをみておきましょう。
文書管理システムには大きく分けて次の5タイプがあります。それぞれの活用方法についても簡単にみておきましょう。
文書全般を保管・活用タイプ
文書の種類を問わない文書管理システムです。報告書や稟議書といった文書を共有したり、他部署で文書を活用したり、テレワーク時の文書取得などにも活用できます。
文書全般の作成・共有タイプ
文書を管理するというフローには文書作成・活用・保存・廃棄という流れがあります。このタイプのシステムは文書作成においても効率化を図りたい場合に便利です。例えば、業務マニュアルを庁内で共有しておきたい場合など、マニュアルを関係担当者複数名で作成するケースに活用できます。
契約書の保管・活用タイプ
契約書の台帳管理や更新作業を効率的に行いたい場合に適したタイプです。契約書をデータ化して、必要に応じて取り出せるようにデータベースを構築することができるので、更新作業も効率化できます。
契約書を作成・共有タイプ
契約書を作成・共有できるタイプは契約書のテンプレートがついているので、作成作業が簡単に行えるほか、データを共有することで速やかに承認を得ることもできるので契約業務を効率化できます。
外部保管タイプ(クラウド型ファイルサーバー型)
例えばテレワーク中の職員ともデータを共有しながらプロジェクトを進めるといったケースが考えられるなら、クラウド型のファイル共有ができるタイプを選ぶのが適切です。オンラインストレージを活用して保存することになるので、文書以外にも画像やアプリケーションなどのデータ共有できるようになります。
こうした文書管理システムのタイプや搭載されている機能を理解して、どういった業務で、どのような文書管理体制を構築したいのかを明確にしたうえで、システムを選びましょう。
まとめ:自治体における膨大な資料整理やペーパーレス化を進め、スマート自治体を目指す
自治体が取り扱う文書は行政文書として規定に沿って保存・管理されます。企業との間で取り合わした契約や、住民が申請するために提供した個人情報など、セキュリテイーを万全にしながら、かつ、各業務に必要な共有を行うことで、行政サービスや業務の利便性を向上させることができます。こうした仕組みを構築するためには、文書管理システムが有効です。
文書管理システムの導入効果は、膨大な量の紙の削減です。ペーパーレス化によって業務効率化に加え、保存スペースの削減や印刷コストも削減できます。
稟議に係る手順や時間も削減でき、テレワークの導入にもつなげることが期待できます。
職員の業務負担が軽減され、単純な作業に費やしていた時間が減らせることで、住民サービスの充実につながる業務に時間が割けるようになります。こうした積み重ねが地域住民の利便性向上にもつながり、魅力のある地域へと変革が進むことにもなります。
インフォマートが提案しているBtoBプラットフォーム 契約書は契約・承認・保管管理機能がオールインワンで搭載されています。発行側も受領側も、Webだけで契約が完了する高度な電子契約システムです。契約の進捗状況を必要な段階で確認でき、操作はとても簡単です。
また、汎用性が高い仕組みなので、1つのIDで自治体と民間企業、民間企業同士の電子取引やデータ保管・管理が双方で行えます。こうした汎用性の高さは、地域全体のデジタル化普及を後押しするものでもあります。
詳しくは次のサイトが参考になります。
契約・承認・保管管理機能がオールインワン「BtoBプラットフォーム 契約書」
今回注目した文書管理システムの導入は、自治体DX推進に係る取り組みにおいては、一例にすぎませんが、その効果は大きいといえます。
まず必要性の高いものから取り組みを進め、スマート自治体を目指しましょう。
※本記事は更新日時点の情報に基づいています。
監修者プロフィール

一般社団法人 未来創造ネットワーク 代表理事
松藤 保孝 氏
自治省(現総務省)入省後、三重県知事公室企画室長、神奈川県国民健康保険課長、環境計画課長、市町村課長、経済産業省中小企業庁企画官、総務省大臣官房企画官、堺市財政局長、関西学院大学大学院 法学研究科・経営戦略研究科教授、内閣府地方創生推進室内閣参事官等を歴任し、さまざまな政策の企画立案、スリムで強靭な組織の構築、行政の業務方法や制度のイノベーションを推進。一昨年退官後、地域の個性や強みを生かすイノベーションを推進する活動を行う。




