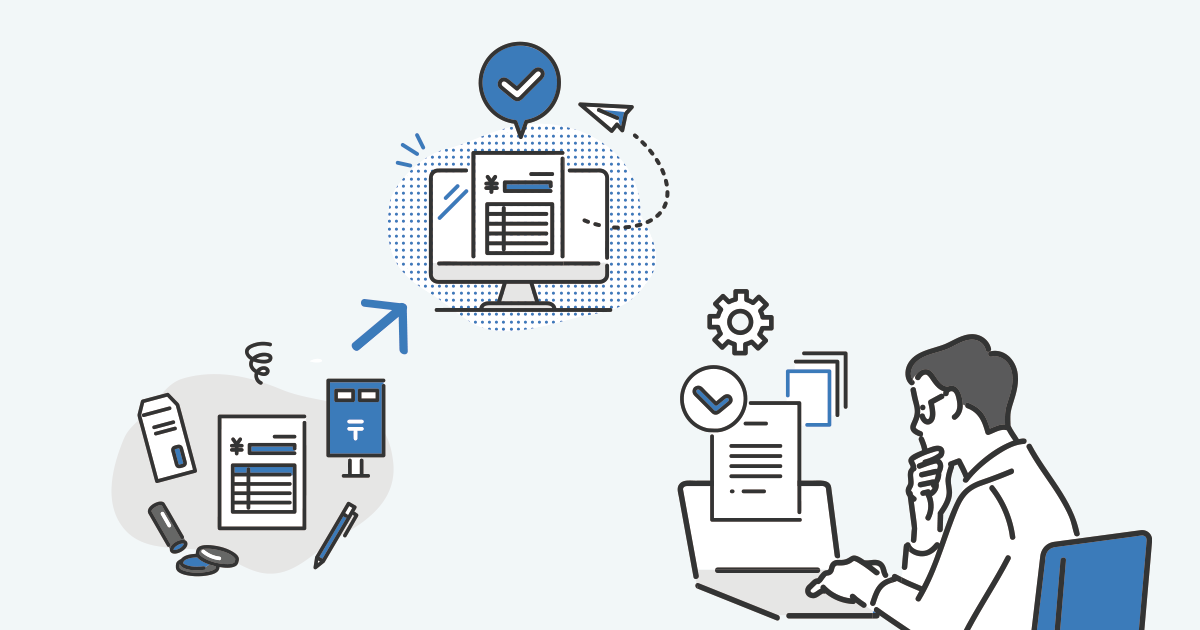鹿児島県鹿屋市は大隅半島のほぼ中央に位置する、人口10万人規模の自治体です。鹿屋市の会計事務DXの取り組みを、鹿屋市デジタル推進課 情報推進係 係長の富永泰浩様にご講演いただきました。
庁内の意思疎通に欠かせないスローガン
鹿屋市は、超少子高齢化社会の到来、社会生活の多様化が進む中で、市民サービスを維持・向上していくために、ICTの活用や新しい技術の導入による「スマートな市民サービス」の充実を目標として、その受け皿となる「スマートな職場」づくりとこれらを担う「スマートな職員」の育成を進め、市民にとって利便性の高い市役所の実現を目指す「鹿屋市役所スマート化計画」(現在は「鹿屋市DX推進計画」に移行)を策定しました。その一施策として、会計事務DXに着手しました。
会計事務DXの実施計画
-
STEP1
令和3年9月
- 電子請求書の実証実験
- 電子決済の開始
- [導入経緯]
- 令和4年1月~文書管理
- 令和5年4月~財務会計
(出納室審査を除く) - 令和5年6月~財務会計
(会計審査含め、全て電子決済)
-
STEP2
令和5年10月
- 電子請求書の取引開始
- 電子請求書をPDF出力し財務会計システムへ添付
- 支出伝票起票し、庁内の電子決済を開始
- 電子請求書の取引開始
-
STEP3
令和6年10月(準備中)
- 事業者から発行された電子請求書情報を財務会計システムへ自動連携
令和6年7月時点の運用は電子で受け取った請求書をPDFに出力し、財務会計システムに添付することで対応しています。電子請求システムを導入しただけでも、窓口受取時の対応、保管、支出命令書への貼付、出納室への提出(持参)の手間が削減でき、請求書不備による差し戻しと再発行の手間とタイムロスも削減することができました。
令和6年10月(予定)から、事業者からの電子請求書情報を財務会計システムへ自動連携できるよう準備を進めています。それにより財務会計システムへの請求書情報の転記の手間を無くすことができ、請求書のPDFも連携することができます。
電子請求システムを導入した背景と費用対効果
電子請求システム「BtoBプラットフォーム」を採用した理由
- ①財務会計システムへの連携が可能
- ②機能や操作がわかりやすい
- ③事業者側の法的要件を満たしている
- ④民間企業では約108万社の導入実績があり、説明会のサポートやマニュアル作成などの導入支援が充実している
請求書が全て「BtoBプラットフォーム 請求書」を利用して電子化された場合、導入前は12,500時間かかっていた作業時間が、導入後は4,583時間と約8,000時間の短縮。およそ63%の削減効果となります。
紙の請求書
<請求書受取~支出命令書作成までの工程>
- 請求書情報の確認
- 請求書不備による差戻作業(電話、郵送等)
- 請求書の入力と支出命令書作成
- 所属長の承認
- 会計課による審査
- 請求書原本ファイリング
電子請求書
<年間5万通 電子化した場合の削減効果>
63%削減
導入前12,500時間
導入後4,583時間
電子請求システム導入時の反応と課題解決のための対応
| 事業者 | 庁内職員 | |
|---|---|---|
|
電子請求システムの導入を強制していないことから、反対の意見等はありませんでしたが、個人経営のような規模の大きくない事業者等は現状への課題意識が十分ではないように感じました。また、同時期に始まったインボイス制度と電子請求書を混同している様子も見られました。 |
反応 |
社会のデジタル化の動きや庁内のスマート化計画の推進もあり、明確な反対の声はなかったものの、電子請求書導入に伴う業務フローの見直しや電子請求そのものへのイメージが湧かないことによる、デジタルへの抵抗感や懐疑的な雰囲気が感じられました。 |
|
対面式やオンライン式での説明会を複数回実施し、電子請求が強制ではないことを説明して、理解を求めるところから始めました。鹿屋市のHPに運用ルールや操作方法などを掲載し、問合せ対応などのサポートも行なって、事業者の理解を増やしていきました。 |
対応 |
紙と電子の二重管理による煩雑さへの抵抗感の解消と、また関係部署との運用ルールの決定においては、苦労がありました。将来的な効率化の見通しを示して関係部署と協議・調整を重ね、新たな運用ルールを決めて職員に説明し、理解を得ました。 |
鹿屋市様からのコメント
会計部門、デジタル関連部門と各々の立場はありますが、会計事務DXの推進にあたっては同じ方向を向き、協力して進めていただきたいです。100%電子化は遠い先でも、電子化の恩恵を受ける市民や事業者は確実にいます。紙と電子の処理は煩雑であったり、しばらく紙が主流であったりしても、行政サービスとして、市民・事業者の方々が利用しやすい方法を選択できる環境を整備する必要があるのではないかと思っています。