インボイス制度の不動産賃貸業への影響とは?
2023年10月から始まったインボイス制度は、不動産賃貸業界においても課税関係や実務対応に大きな影響を及ぼしています。 住宅賃貸は非課税取引として対象外となる一方、事業用物件では適格請求書の発行が必要 となり、物件の用途によって対応方法が大きく変わりました。本記事では、インボイス制度の基礎から具体的な実務対応まで、不動産賃貸業に関わる方々に必要な情報をわかりやすく解説していきます。
不動産業界向け『BtoBプラットフォーム』サービス概要資料
『BtoBプラットフォーム』は、企業間電子取引でトップシェアを誇るサービスです。
取引先は無料で利用でき、導入時には取引先へのサポートも含めた万全の体制でサポートします。
\ 3分でわかる! /
資料ダウンロード(無料)不動産賃貸業におけるインボイス制度の基礎
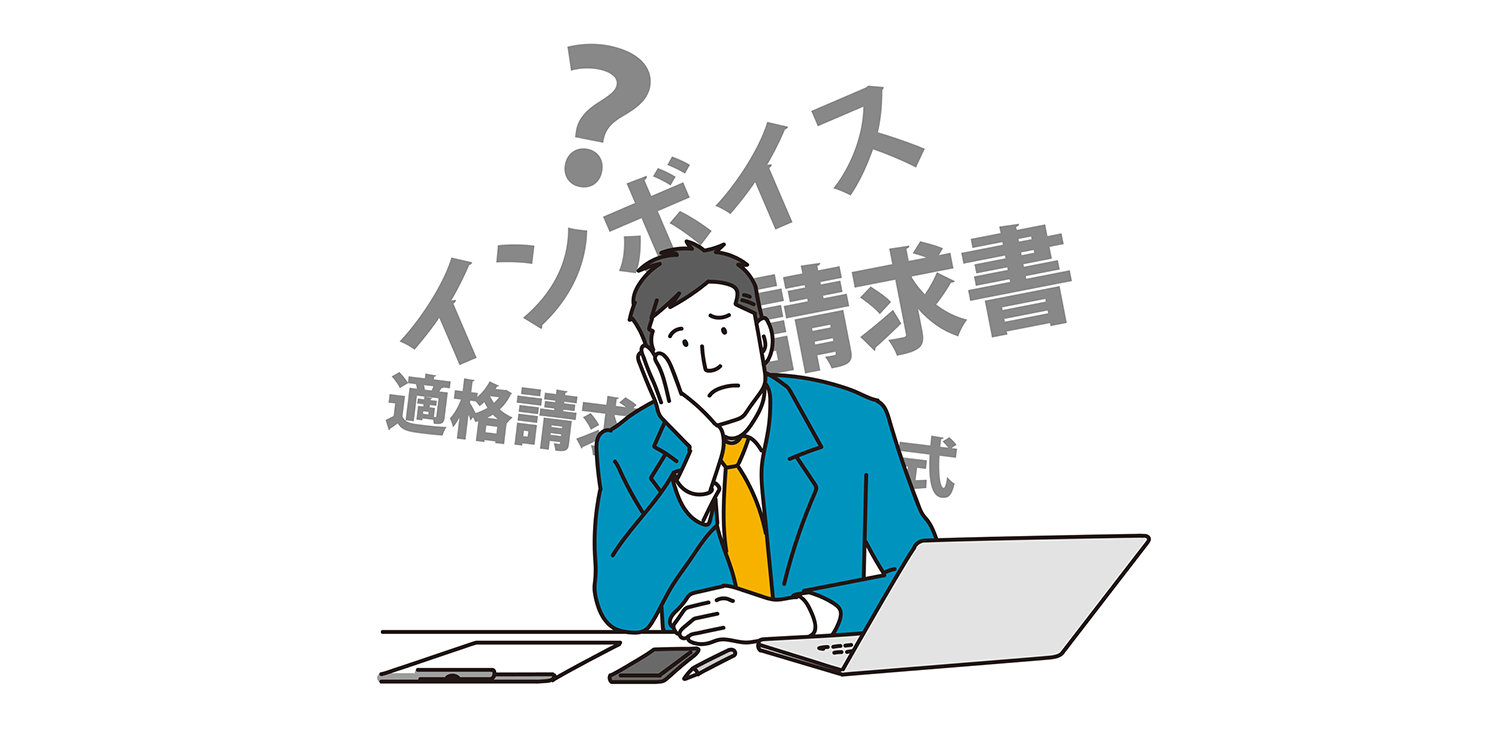
インボイス制度は、消費税の適正な把握と円滑な転嫁を目的として導入されました。現在、制度は本格運用の段階に入っており、厳格な対応が求められています。不動産賃貸業では物件の用途によって課税関係が異なることから、正確な理解と適切な実務対応が必要です。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の方式として2023年10月から導入された新しい制度です。この制度では、課税事業者が 一般課税により仕入税額控除を行うためには、取引先から「適格請求書(インボイス)」の交付を受け、保存することが必要となります。適格請求書には、従来の請求書の記載事項に加え、「登録番号」「適用税率」「消費税額」などの記載が必要です。
適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、免税事業者からの仕入 については、原則として仕入税額控除ができなくなります。
インボイス制度の影響を受ける取引
不動産賃貸業においても、「免税事業者」か「課税事業者」かの立場によって、インボイス制度への対応が大きく変わります。特に課税事業者の場合は、取引の内容によって適切な対応が必要となります。
不動産賃貸業において、住宅の賃貸借取引は消費税が非課税となるため、インボイス制度の影響を受けません。これは、賃貸借期間が1ヶ月以上の住宅用物件に適用され、付属する駐車場代も非課税となります。
一方、店舗や事務所などの事業用物件の賃貸は消費税の課税対象となるため、インボイス制度の対応が必要です。免税事業者である賃貸人は、課税事業者であるテナントとの取引に影響が出る可能性があります。これは、テナントが 課税事業者で一般課税である場合、仕入税額控除を受けられなくなり、その分のコストが増加するためです。その結果、賃料の引き下げ要請や契約の終了 、契約規模の縮小などが発生する可能性があります。
また、住宅と店舗が混在する物件の場合は、用途に応じて課税と非課税を区分して管理する必要があります。なお、2023年10月から2026年9月までは「2割特例制度」により、免税事業者から適格請求書発行事業者への転換時における消費税の納税の負担を軽減できます。
不動産業界向け『BtoBプラットフォーム』サービス概要資料
『BtoBプラットフォーム』は、企業間電子取引でトップシェアを誇るサービスです。
取引先は無料で利用でき、導入時には取引先へのサポートも含めた万全の体制でサポートします。
\ 3分でわかる! /
資料ダウンロード(無料)賃貸物件種別ごとのインボイス制度対応方法
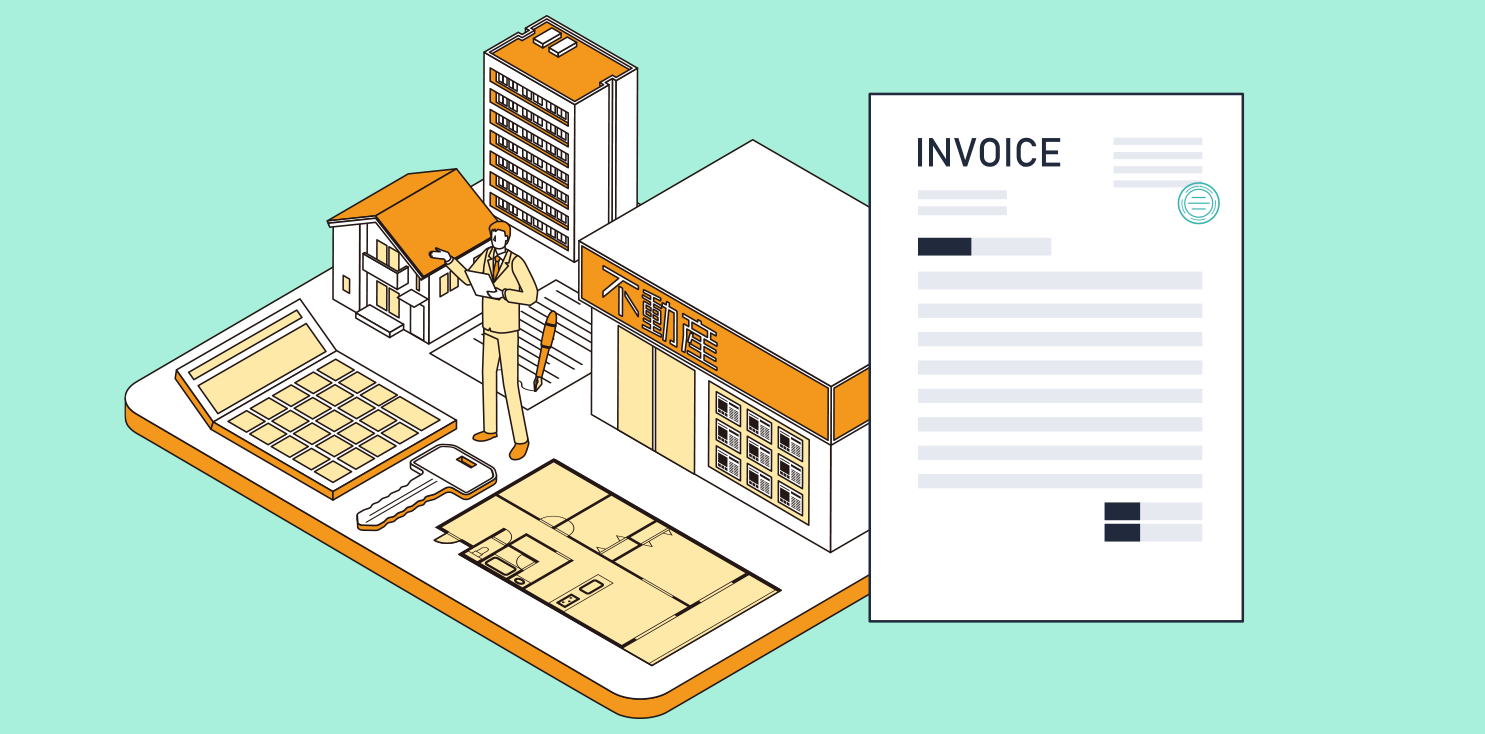
不動産賃貸業における実務対応は、物件の用途によって大きく異なります。住宅賃貸と事業用賃貸では必要な対応が全く異なるため、物件ごとに適切に対応する必要があります。
住宅賃貸の場合
住宅賃貸の場合、消費税は非課税のためインボイス制度への対応は原則不要です。ただし、共益費や管理費については、内容や契約形態によって課税対象となる場合があります。たとえば、共用部分の清掃費用や設備の保守点検費用を個別に請求する際は、課税取引として扱う必要があります。
管理費等が課税対象となる場合は、その部分についてインボイス制度に対応した請求書の発行が必要です。請求書上で家賃(非課税)と管理費(課税)を明確に区分して記載することが求められます。また、賃貸借契約書には、賃料と管理費等の区分を明確に記載し、それぞれの消費税の取扱いについても明示することが重要です。
事業用物件の場合
事業用物件の賃貸では、テナントの仕入税額控除のため、適格請求書の発行が必要です。適格請求書発行事業者への登録手続きを済ませ、必要事項を満たした請求書を発行できる体制を整えましょう。特に、登録番号や税率ごとの消費税額、適用税率の記載には注意が必要です。
既存のテナントとの契約も、インボイス制度に沿った形での見直しが求められることがあります。特に免税事業者である賃貸人は要注意です。テナントが仕入税額控除を受けられなくなるため賃料の見直しを求められる可能性があり、その場合は適格請求書発行事業者への登録を前向きに検討すべきでしょう。
複合用途物件の場合
住宅と事業用スペースが混在する複合用途物件では、課税取引と非課税取引を明確に区分して管理する必要があります。共用部分の管理費については、床面積比などの合理的な基準に基づいて按分計算を行います。この按分計算の基準は、事前に文書化し、継続的に適用することが重要です。
例えば、床面積による按分では、住宅部分600㎡・事業用部分400㎡の建物の場合、共用部分の管理費は住宅部分60%(非課税)、事業用部分40%(課税)として区分します。 区画数による按分であれば、住宅8戸・店舗2区画の建物では、共用部分の管理費を住宅部分80%(非課税)、事業用部分20%(課税)として計算します。
区分経理にあたっては、取引内容や按分計算の根拠を明確に記録し、保管する必要があります。特に共用部分の水道光熱費や清掃費用などの経費については、課税取引と非課税取引の区分を明確にし、適切に記録を残すことが求められます。また、テナント区画の用途変更や、共用部分の使用実態の変化にも注意を払い、必要に応じて按分基準の見直しを行うことも重要です。
不動産業界向け『BtoBプラットフォーム』サービス概要資料
『BtoBプラットフォーム』は、企業間電子取引でトップシェアを誇るサービスです。
取引先は無料で利用でき、導入時には取引先へのサポートも含めた万全の体制でサポートします。
\ 3分でわかる! /
資料ダウンロード(無料)実務対応における具体的な変更点
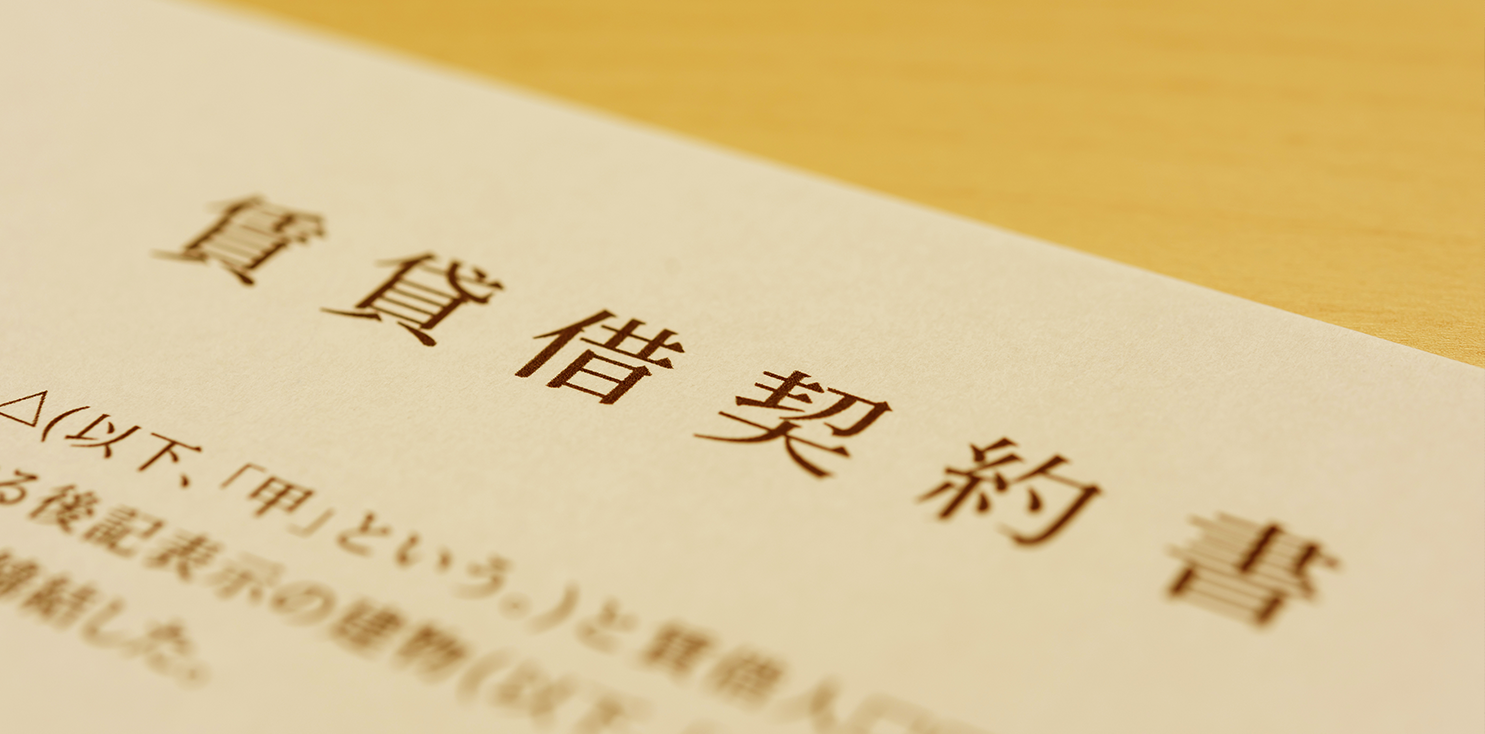
インボイス制度の導入に伴い、請求書や契約書の作成方法など、実務面での変更が必要となります。特に事業用物件の賃貸においては、制度が本格運用の段階に入り、厳格な対応が求められているため、適切な対応が重要です。
請求書・領収書の対応
適格請求書として認められるためには、従来の記載事項に加えて、新たな要件を満たす必要があります。具体的な必須記載事項は、適格請求書発行事業者の登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した合計額および適用税率、税率ごとに合計した消費税額等です。これらの記載がない場合、テナントは仕入税額控除を受けることができません。
経過措置期間中は段階的な対応が認められており、2029年9月までは一定の緩和措置があります。しかし、早期に完全対応を進めることで、スムーズな制度移行が可能となります。
システム対応では、まず請求書のフォーマットに登録番号欄を追加し、税率ごとの消費税額を自動計算できるよう設定を変更する必要があります。また、住宅用と事業用で課税・非課税取引を区別できるよう、物件ごとの区分設定も重要です。特に複合施設の場合、正確な区分管理のため、物件の用途に応じて自動的に税区分が振り分けられる仕組みを整えることで、業務の効率化と正確性を両立することができます。
賃貸借契約書の対応
既存の賃貸借契約書については、インボイス制度に対応するための追加的な対応が必要となる場合があります。特に重要なのは、消費税の転嫁に関する取り決めと、適格請求書の発行に関する規定です。これらの事項については、契約書本文の変更または覚書の追加により対応します。
新規の契約書については、インボイス制度に対応した記載内容を最初から盛り込む必要があります。課税取引と非課税取引の区分、消費税の取扱い、適格請求書の発行に関する事項などを明確に記載します。また、将来的な制度変更にも対応できるよう、柔軟な規定を設けることも検討に値します。特に、消費税率の変更や制度の変更に対応できる条項を入れておくことで、将来の契約変更の手間を省くことができます。
不動産業界向け『BtoBプラットフォーム』サービス概要資料
『BtoBプラットフォーム』は、企業間電子取引でトップシェアを誇るサービスです。
取引先は無料で利用でき、導入時には取引先へのサポートも含めた万全の体制でサポートします。
\ 3分でわかる! /
資料ダウンロード(無料)テナントとの関係における実務対応

インボイス制度の導入により、特に事業用物件のテナントとの関係において、新たな対応が必要となっています。テナントの事業形態や規模によって影響度が異なるため、個々の状況に応じた柔軟な対応が求められます。
インボイス制度とテナント契約条件の見直し
課税事業者であるテナントに対しては、仕入税額控除のために必要な適格請求書を確実に発行することが求められています。既存のテナントには、インボイス制度の導入に伴う変更点について丁寧な説明が必要となりました。特に、賃料や管理費の消費税の取り扱いについては明確な説明が欠かせないところです。
賃料の見直しが必要となる場合は、テナントとの十分な協議のもと、双方にとって納得できる条件設定を心がけましょう。また、免税事業者から課税事業者への移行時には、税負担の変化について分かりやすく説明することが大切です。その際、経過措置期間を活用した段階的な調整も効果的な選択肢となるはずです。
トラブル防止を未然に防ぐ対応
課税事業者であるテナント企業に対しては、仕入税額控除が可能な体制が整っていることを分かりやすく説明し、必要な情報提供を適切に行うことが重要です。これにより、制度変更による影響を最小限に抑え、テナント離れを防ぐことができます。
制度対応の遅れやミスによるトラブル防止には、社内体制の整備が重要な鍵となります。担当者への教育・研修の実施やチェック体制の構築により、実務上のミスも防げます。さらに、税理士等の専門家との連携を図ることで、より確実な制度対応が可能となるでしょう。
不動産業界向け『BtoBプラットフォーム』サービス概要資料
『BtoBプラットフォーム』は、企業間電子取引でトップシェアを誇るサービスです。
取引先は無料で利用でき、導入時には取引先へのサポートも含めた万全の体制でサポートします。
\ 3分でわかる! /
資料ダウンロード(無料)まとめ

インボイス制度は不動産賃貸業において、物件の用途によって対応が大きく異なることが特徴です。住宅賃貸については非課税取引として基本的に対応不要である一方、事業用物件については適切なインボイス対応が必要となります。2026年9月までは2割特例制度が適用されるため、この期間を有効活用して必要な体制整備を進めるといいでしょう。
具体的な準備として、賃貸契約書の見直しやインボイス発行に対応したシステムの導入が重要です。特に、請求書や領収書、契約書などの各種帳票をデジタル化することで、インボイス制度への対応と業務効率化を同時に実現できます。インフォマート社の「BtoBプラットフォーム」では、契約書の作成から請求書の発行、保管まで一連の業務をデジタルで完結できるため、インボイス制度対応と業務効率化を同時に実現できます。
このように、専門家との連携に加え、デジタル化による業務改善を進めることで、新制度にも対応した安定した賃貸経営を継続することができるでしょう。

宮川 真一
【保有資格】CFP®、税理士
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
不動産業界向け『BtoBプラットフォーム』サービス概要資料
『BtoBプラットフォーム』は、企業間電子取引でトップシェアを誇るサービスです。
取引先は無料で利用でき、導入時には取引先へのサポートも含めた万全の体制でサポートします。
\ 3分でわかる! /
資料ダウンロード(無料)



