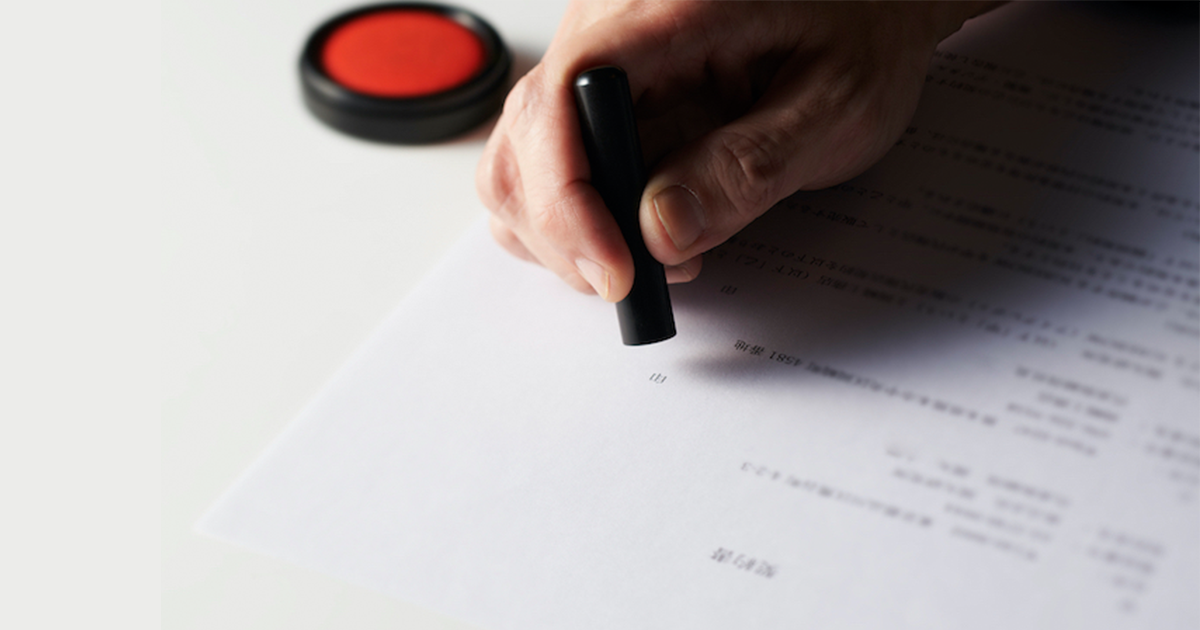政府がデジタル社会の実現を目指し、さまざまな取り組みを実施し、制度や法律の改正にも着手してきています。2021年には「改正会社法」によって株主総会関連資料の電子送付が義務化され、2022年の「電子帳簿保存法」では電子データによる保存を推進しています。こうした動きのなか、各企業では業務のデジタル化を進め、ペーパーレス化を実現しています。一方、自治体においては、デジタル化、ペーパーレス化が進んでいないといわれています。今回はその状況を踏まえ、自治体がペーパーレス化を実現することでなにがどう変わるのかを見ていきましょう。
■ 目次
自治体のペーパーレス化はなぜ必要なのか
企業においても同様ですが、自治体においてペーパーレス化が促されているのは、単に膨大な紙の資料を廃止するだけの理由ではありません。
紙でやり取りをして紙で保存をしてきた情報を電子データ化することで、より効果的にデータ活用ができるからです。事業の継続も容易になります。自治体は、地域住民の安全・安心を担保し、災害時においても、地域のライフラインの確保やいち早い復興を目指すことが期待されています。そうした際に、いつでもどこからでも対応できる電子データとして必要な情報を保存しておくことが有効なのです。ペーパーレス化が必要な理由はさまざま存在しますが、主なものを具体的にみておきましょう。
デジタル社会への動きに対応する
日本はデジタルの活用によって、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会をめざしています。2021年にはデジタル庁が発足しました。各地域のデジタル化は、各自治体がけん引することが期待されています。社会のデジタル化の波に乗り遅れ、地域住民、地域事業者が世界の動きに取り残されたり、行政サービスが滞ったりすることがあってはなりません。そうした事態を招かないためにも、自治体がデジタル化を進めることは重要です。そのひとつとしてペーパーレス化を実現される必要があるのです。
庁内業務の効率化を図る:多様な働き方へ対応する
自治体は、多くの他律的業務(業務遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務)を担っています。たとえば、議会対応や市民対応、取引先との対応など、対面で行うことも必要になり、そのプロセスにおいて申請書類や請求書、稟議書など紙媒体による情報のやり取りが発生しています。いいかえれば、職員の働き方改革や行財政改革が進まない状況にある、ともいえます。業務の効率化や多様な働き方が可能な体制への変革のためには、まずペーパーレスで情報共有ができるシステムへと改める必要があるのです。
庁内業務の効率化を図る:人材不足への対応
多様な働き方への対応が難しい状況が続くなか、多くの企業同様に自治体においても人材不足は大きな課題です。職員が働きやすい環境を整えること、たとえば、家族に介護が必要になった場合でも働き続けることができたり、子育て中の職員はテレワークが選択できたりする体制を整えることで、人材不足に対応できる可能性が高まります。こうした体制を構築するには、ペーパーレス化を実現させ、紙媒体でしか対応ができない業務を変革することが重要です。住民からの行政サービス申請等はスマートフォンからオンラインで手続きができるようにすることで職員の負担が軽減されます。また紙の書類でやり取りをし、保存をしていたのでは、管理するための時間やコスト、作業が発生し、効率化が図りにくい状況のままとなります。
人材不足をはじめとする業務効率化を図るには、まずペーパーレスで業務が行えるシステムへと変革することが重要なのです。
DX化を着実に推進する
ペーパーレス化の実現は、紙の使用量を削減する、業務の効率化を図るだけの対応ではありません。その先に自治体のDX実現があります。自治体が目指すべき姿は、住民や地域事業者への行政サービス提供をよりスムーズにより丁寧に、そして、住民や企業の方々の時間やお金や労力をできるだけ使うことなく、実施できる体制です。そのことによって、地域の魅力向上へとつながり、人が集まる自治体となるでしょう。
そのプロセスのひとつが、自治体内の業務効率化と働き方改革です。さらにまず取り組む変革として膨大な紙を使用する業務の見直し、つまりペーパーレス化への業務変革です。
ペーパーレス化の推進は、魅力的な自治体への第一歩ともいえるのです。
地域住民・地域事業者の利便性を向上させる
自治体における業務も徐々にデジタル化が進み、オンラインでの行政申請手続きが可能なものが増えてきました。さらに従来の紙媒体による申請・請求手続きを経なくても行政サービスが受けられる体制へと変われば、地域住民や地域事業者の利便性は向上します。
ペーパーレスによる地域住民や地域事業者の利便性の向上については次の記事が参考になります。
自治体におけるペーパーレス化の進捗
自治体DXの推進をするうえで、取り組みのひとつでもあるデジタル化。そのデジタル化を進めるためには紙書類を電子データ化する必要があります。いいかえれば、ペーパーレス化を進めなければ、自治体が保有する情報をデータとして有効的に活用することができないままだということになります。
2022年10月に公表している日本総研による調査があります。「データから見る都道府県別自治体DXの進展状況」というものです。その報告内容を見ると、各自治体においてDX推進のためのさまざまな取り組みがなされており、「推進体制」も着手しやすい取り組みから進めているといった状況です。「行政サービスの向上・高度化」においては、全国の自治体の7割以上が申請・届出等の手続きをオンライン化するためのシステムを導入したとしています。そのほか、ハードの導入は着実に進んでいるとする一方で、業務やサービスでの活用を促進するための計画や制度といったソフト面の対応が遅れているとの指摘もしています。また、「電子決裁」については、全国で2割程度の自治体しか対応できていないとしています。
電子決裁は従来の紙の文書や帳票類、印鑑を用いた決裁プロセスを電子化しなければ実現できません。つまり、ペーパーレス化が十分に進み、電子決裁が機能している自治体は全体の2割程度であるということです。
自治体DXの現状をみると、体制を整えたり、ハード面の構築をしてシステム導入までは取り組みを進めたりはしているものの、業務内容を見直し、フローを再検討し、業務プロセスを紙から電子データへと置き換えて変革を図れていないとしています。
ペーパーレス化が遅れている理由
DX推進をするうえでも、導入したシステムを十分に活用して業務効率化を図ったうえで、住民や地域事業者の利便性向上を実現するには、ペーパーレス化が必要であることはわかっていても、なぜ現実として進まないのでしょうか。いくつかの要因を考えてみましょう。
コストがかかる
ペーパーレスを実現するには、初期投資としてハードウェアやソフトウェアをそろえる必要があります。また、情報データを安全に保存するためのストレージも確保しなくてはなりません。こうした最初に必要となる費用に不安を感じると、取り組みは遅くなります。
ペーパーレス化を実現したのちに削減できるコストやムダを検討して、総合的にコスト面を判断することが重要です。
業務フロー変更に抵抗感がある(メリットの理解不足)
自治体では今まで多くの紙を使って情報のやり取りをし、保存をしてきました。そのための業務フローが長年の経験によって整備され、定着しています。ペーパーレス化を進め、システムを導入すると、今までの作業内容を変更して、新たな作業手順を覚える必要が生じます。また、端末の操作もこなさなくてはなりません。
ITリテラシーが十分でない職員にとってはストレスになる可能性もあります。
さらに、自治体では承認・決裁等においては、押印することで意思決定を伝えることが慣例とされてきました。このフローが電子決裁を導入し、ペーパーレスの書類を電子上で決裁することへの抵抗感があることも一因といえるでしょう。
「前例主義」「いままでどおり」という庁内文化がデジタル化、ペーパーレス化の足かせになっているとも考えられます。
こうした点は、ペーパーレス化が実現したときに、どのような効果が生まれ、それがどのような業務効率化をもたらすのかなどのメリットが正しく理解できていないこと、また、現在の業務の在り方、職員、住民、地域の企業等に、多くの、金銭的、時間的、精神的なコストを負担させていることを正しく認識できていないことが根本原因だと考えられます。まずはペーパーレス化を進める一歩として、職員や議員に理解を図ることが重要です。
セキュリティへの不安
ペーパーレス化を進め、情報を電子データに置き換えることには、確かに不安な点があります。たとえば改ざんしやすくなるのではないか、サイバー攻撃を受けると情報漏えいが起こるのではないかなど、セキュリティ面を不安視することは間違いではありません。そのためにセキュリティ体制を万全に整えることが重要なのです。
自治体におけるペーパーレス化の進め方

ではどのような手順でペーパーレス化を進めるのがよいのでしょうか。
具体的なペーパーレス化の手順を確認しておきましょう。
紙の使用状況を把握する
まず、すべての部署において、どれくらい紙を使用している業務があるのかを洗い出します。たとえば、報告書、稟議書、申請書、契約書、請求書、会議資料など紙で管理保存しているものなどもリストアップしましょう。
データ化が不可能な業務を明らかにする
紙を使用している業務が洗い出せたら、その業務において文書が必要かどうかを検討・確認しましょう。その文書が必要である場合は、業務的にも法的にも、紙でないといけないのかを判断しましょう。自治体の業務のほとんどは、基本的に、デジタル化する方が好ましいという原則を基本に考えましょう。また、法令等で紙での処理が義務付けられている業務については、法令改正などを政府に働きかけることも有効です。
また、業務自体をデジタル化し、情報のデータ化も、検討しましょう。
システムやツールを活用する:どの業務においてどういったツールが活用できるかを検討する
文書のなかでデータ化できるものが明らかになった段階で、どのツールやシステムを使ってデータ化するかを選択します。その際に重要なのは、やりたい作業に必要な機能が搭載されていることや、職員の使い勝手と操作性の良さです。また、提供先事業者の対応も確認します。たとえば、ツールやシステムのメンテナンスや導入にさいして、どのようなサポートが得られるのかも重要な選択要件です。
ITスキルのある専門家、支援サービスの活用を検討する
どのツールやシステムを活用できるかを検討し、候補を選択する段階で、職員自ら設定できるか、また、メンテナンスやトラブル時の対応にはITスキルの専門家が必要かを確認しましょう。そのうえで、専門的な技術と知識のある支援サービスを活用するのかも検討します。
ペーパーレス化実施後の効果を測り、さらに改善を繰り返す
ツールやシステムを導入して、各業務におけるペーパーレス化を実施した後は、定期的に効果を測ります。その効果をもとに、さらなる改善を図り、効果を高める工夫を繰り返していきます。
こうした取り組みは導入したら終わり、ではなく、実施、効果測定、改善、再実施を繰り返してくことが重要です。
また、一気にすべての業務におけるペーパーレス化を図るのではなく、実施しやすく効果が見えやすい業務からはじめ、徐々に拡大していくのが成功への近道です。
ペーパーレス化に成功した自治体
自治体のなかでペーパーレス化に成功した事例を確認しておきましょう。
長野県長野市:ペーパーレス会議を実現
長野県県庁では、電子市役所の構築を推進しており、各種業務のシステム化やデータベース化を実施してきました。しかし、内部事務においての紙使用量削減効果が期待したほどには表れませんでした。とくに、庁内の会議で配布される膨大な資料に大量の紙が使用されており、また会議が頻繁に開催されるため、紙の削減ができていないことが明らかになりました。この会議のやり方では、紙使用の削減ができないだけでなく、資料を用意する手間と費用が使われていることを意味しています。さまざまな取組を展開しながら、更なる効果を期待して、2015年からは、パソコンやタブレット端末、ICTの活用、ペーパーレス会議システムを導入し、省力化、省コスト化をめざしました。
知事、副知事、部局長等が出席する月1〜2回の「部局長会議」においてペーパーレスシステム会議を実施。そのほかの部内会議などを含め導入開始から10ヵ月で利用の拡大を進めました。その結果、紙資料に換算すると、約94,000枚の削減を実現しています。
大阪府吹田市:文書管理と決裁の電子化を実現
吹田市では、新型コロナウイルス感染症の拡大による働き方の見直しにより、テレワーク導入をきっかけに、文書管理と決裁の電子化に向けた検討を具体化してきました。そして、2023年(令和5年)1月にIPKNOWLEDGE文書管理・電子決裁システムを導入。各部署と運用に向けた調整・合意形成を円滑に行い、稼働当初より文書の電子化率は目標の70%を超えて推移し、電子決裁率も99%となりました。また、ペーパーレス化や業務の効率化などのメリットが職員に広く認識されたことで、さらなるDX推進への機運も高まりました。文書管理、電子決裁システムの導入は「ペーパーレスな市役所」の一施策として位置付けられているものですが、以前から課題として挙がっていた「書類が増え続けること、その管理と手間、保管場所の確保」を解消するための取り組みでもあります。具体的に動き始めたのはテレワーク導入にあたり、紙の運用・押印決裁の見直しが喫緊の課題となったからです。
IPKNOWLEDGE文書管理・電子決裁システムを導入後、テレワークでできる業務範囲が拡大しました。導入がスムーズにできたのは、各部署にヒアリングや説明会を実施して、懸念点や疑問を洗い出す事前の対応を充実させたことで、各部署が納得して電子化を進められたといえます。
まとめ:ペーパーレス化でデジタル技術を活用できる体制をつくり、自治体DXを加速させる
自治体において、デジタル活用によってペーパーレス化を実現することは、たんなる紙媒体を使わない体制にすることが目的ではありません。紙媒体によって情報の保存ややり取り、共有をしている状態では、機密情報の漏えいリスクは高いといえます。その観点からも、ペーパーレス化を実現することは有意義なのです。また、身近な課題であるペーパーレス化を実現するために、業務をデジタル化していくことで、他の効果も期待できます。たとえば、情報の有効活用がしやすくなり、共有もスムーズにできます。こうした体制が整備されれば、住民への行政サービスや地域事業者との取引もより短時間に確実に行えるようになると期待できるのです。まずは身近な課題解決としてペーパーレス化を実現する体制作りを進めましょう。
自治体DXの進め方や課題と対策については、次の記事が参考になります。
※本記事は更新日時点の情報に基づいています。
監修者プロフィール

一般社団法人 未来創造ネットワーク 代表理事
松藤 保孝 氏
自治省(現総務省)入省後、三重県知事公室企画室長、神奈川県国民健康保険課長、環境計画課長、市町村課長、経済産業省中小企業庁企画官、総務省大臣官房企画官、堺市財政局長、関西学院大学大学院 法学研究科・経営戦略研究科教授、内閣府地方創生推進室内閣参事官等を歴任し、さまざまな政策の企画立案、スリムで強靭な組織の構築、行政の業務方法や制度のイノベーションを推進。一昨年退官後、地域の個性や強みを生かすイノベーションを推進する活動を行う。