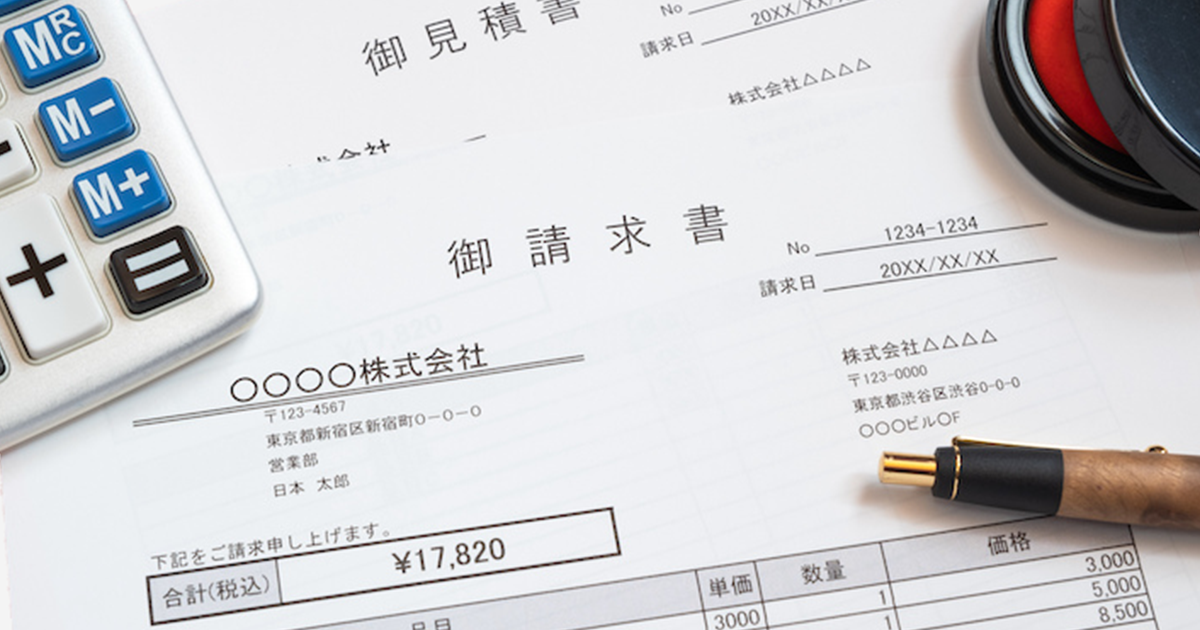政府は最新のデジタル技術を活用して、すべての国民がより豊かで安心して暮らせる社会、デジタル社会をめざして、さまざまな取り組みを打ち出しています。そのひとつにスマート自治体の実現があります。スマート自治体の実現によってめざす姿は「自治体が持続可能な形で行政サービスを提供し続け、住民福祉の水準を維持するもの」であり「職員を事務作業から解放し、より価値のある業務に注力できる環境が整えられ」ており、さらに、「ベテラン職員の経験をAI等に蓄積・代替し、団体の規模・能力や職員の経験年数に関わらず、ミスなく事務処理を行うことができる」自治体です。その自治体の職員の経験だけではなく、法令、判例、通達、全国各地の行政や企業の経験、社会の動向なども、AI等に蓄積し、AI等を使いこなし、自治体の政策立案力を飛躍的に高めることが期待されています。そのめざす姿に向けて、自治体における電子契約導入も推進されてきました。今回は電子契約導入がどのように推進されてきたのか、そしてどのようなメリットをもたらすものなのかなど、自治体における電子契約導入についてみていきましょう。
■ 目次
電子契約とは
電子契約とは、電磁的記録で作成・締結する契約のことを指します。電磁的記録は電子的方式、電磁的方式、そのほか人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を意味しています。
従来なら契約締結は紙の書類に押印や署名したものが利用されていました。電子契約では、押印の代わりに電子的な署名やタイムスタンプを使用します。
紙による契約締結の場合に必要であった書類の郵送や契約書の製本といった手続きを省略することができます。さらに契約書締結までに必要な時間的なコスト、また紙や製本費用といった制作コスト、印紙も不要になりますので、コスト面での節約にもつながります。
電子契約の仕組み
もう少し具体的に電子契約をみておきましょう。
まず、電子契約は「電子署名」「電子証明書」「タイムライン」の3つの構成要素によって成り立っています。それぞれについて確認しておきましょう。
電子署名
契約をする当事者による電子署名は、契約書が当事者の意思によって行われたものであることを担保するものです。
電子署名は紙の契約書における印鑑にあたるものだといえます。
電子証明書
電子契約書は電子データのやりとりによって契約を締結するため、データを送信したのが契約者本人であることを証明しておく必要があります。そのための仕組みが電子証明書です。第三者機関の電子認証局が電子証明書を発行します。
電子証明書は紙の契約書における印鑑証明書にあたる役割をもったものだといえます。
タイムスタンプ
タイムスタンプは電子的な仕組みで契約締結時の日時を記録し、その時点で契約書が存在したことと、改ざんされていないことを証明するものです。
電子契約システムを提供しているいくつかのサービスがありますが、それらサービスによって提供される契約書の種類やセキュリティの強度には違いがあります。
電子契約の種類
電子契約には大きく分けて2種類あります。「立会人型(電子サインタイプ)」と「当事者型(電子署名タイプ)」です。
立会人型(電子サインタイプ)
立会人型は電子サインタイプともよばれるものです。
ここでは、Aという人物が契約締結を行う場合を考えます。立会人型では、Aの契約意思を確認した事業者が、事業者の電子証明書・秘密鍵で電子署名します。あたかも「Aが契約の意思表示するのに立ち会ったこと」を証明しているように見えるので、立会人型とよばれるのです。
また、契約する本人の秘密鍵ではなく、サービス事業者の秘密鍵による署名を行うものなので、事業者署名型とよばれることもあります。
立会人型による本人確認は、電子契約サービスへのログインとメール証明を組み合わせて行われます。そのため契約を締結する二者間における電子契約の合意に必要となるのは、どちらか一方の電子契約サービスへの加入と双方のメールアドレスです。立会人型のメリットは簡単に契約締結を行えることと、取引先はシステム導入の必要がないことです。
当事者型(電子署名タイプ)
当事者型は電子署名タイプともよばれます。
当事者型の電子契約においては、第三者である電子認証局が契約の当事者を本人確認します。その本人確認に基づいて、電子証明書が発行されます。電子認証局が発行した電子証明書を利用して、契約の当事者が電子署名を行うのが当事者型の電子契約です。
当事者型の特徴は、第三者機関である認証局から発行される電子証明書を用いて検証するため、本人による電子署名であることを確実に証明できることです。その点、信頼性が高いものといえます。しかし、手間とコストがかかる点に注意が必要です。
自治体が電子契約を導入することのメリット
インフォマートが2023年12月に自治体向けに実施した調査結果によると、回答者の85%以上が契約書を「全て紙で受け取っている」「ほぼ紙で受け取っている」と回答しました。(自治体の会計業務に関する自治体職員向け実態調査)
自治体の業務効率化のためにも、また、自治体と契約する企業の業務効率化のためにも、電子契約の導入が期待されています。自治体が電子契約を導入することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
契約締結までの手続きの迅速化
紙の書類による契約であれば、契約内容を決め、それぞれに合意し、契約書にまとめるまでに、自治体と取引をする相手は何度も来庁し直接対面で交渉・相談・内容確認をする必要がありました。また承認フローも関係者に書類を回し、承認を示す押印等を完了することも必要でした。こうした契約締結までのフローは時間も労力も要するものです。働き方改革の障害にもなります。電子契約になれば、こうしたフローがスピーディに進むことになります。
契約業務の効率化
紙の書類による契約の場合は、「書類を製作し、印刷する」「製本して押印する」「契約書を相手に送る」「相手から押印した契約書を返送してもらう」「ファイリングして保管」「必要に応じて過去の契約書を探す」などの作業が必要です。もちろん相手側においても、受け取った契約書を返送するまでに、「内容を確認する」「関係者に承認をしてもらい押印」などの作業が必要です。
自治体側、契約相手側の双方にとってかなりの手間がかかる業務であったといえます。
電子契約では、システム上で手続きが完結できます。そのため、書面の郵送・受取、押印等の作業は不要になります。
地域企業の効率化
電子契約が自治体との取引で使えるようになれば、地域企業が従来のように庁舎に足を運んで契約関連の手続をしなければならない、という手間は省略できます。電子契約では、インターネット環境とメールアドレスの用意があれば、オンライン上で契約が完結するわけです。
コストの削減
紙の書類による契約には大まかに考えても用紙代・印刷費・印紙代・郵送費・保管費等のコストが必要です。
電子契約では、電子契約サービスを利用するコストが必要ですが、利用料金以外のコストは削減できると考えられます。
手続きの可視化
紙の書類による契約時には、契約書を郵送し、相手先が契約書を確認し、その後に返送するというフローが発生します。その間、自治体においては状況がつかめず、返送までの時間が予想以上に長引いたとしても頻繁に状況確認をするのも躊躇われ、不安になることも少なくありません。
電子契約では、上司等の関係者も含め契約の進捗が確認できるため、契約する双方が手続きが遅れている場合にはコミュニケーションをとり、遅延解消や遅延の理由を理解することも可能です。
コンプライアンス/ガバナンスの強化
電子契約では契約データの保管や電子契約サービス提供者側の適切なバックアップもあるため、コンプライアンス/ガバナンスの強化が図れます。とくに次の3点においてリスク低減が望めます。
1.改ざん・漏えい・紛失リスクの防止
電子署名とタイムスタンプによって契約内容の改ざんリスクを低減します。また各種文書をサーバーに保管するため紙の契約書に比べて紛失、劣化、棄損、データ改ざんのリスクが軽減されます。
2.権限設定
電子署名とタイムスタンプによって契約内容の改ざんリスクを低減します。また各種文書をサーバーに保管するため紙の契約書に比べて紛失、劣化、棄損、データ改ざんのリスクが軽減されます。
3.遅延・更新漏れの防止
契約期限アラート機能が付いているので、契約書の有効期限の前にアラートを出して遅延や更新漏れを防ぐことができます。
契約書類の管理が簡素化
契約の仕方として電子契約が主流になれば、契約書そのものはデータ保管ができるようになるため、膨大な量の紙や保存場所などさまざまなコストが削減できます。それ以外にも、契約内容を確認する際に、紙の契約書であれば、書庫に出向き、保管されている書類のなかから確認したい契約書類を探す必要があります。こうした手間も、データで管理することで、検索がたやすくなります。
自治体DXの進め方や課題と対策については、次の記事が参考になります。
自治体における電子契約の導入状況とその変化

自治体の電子契約については、地方自治法施行規則によって定められています。その規則が2021年1月に改正されました。
では、この改正を受けて、自治体において電子契約の導入はどのような状況なのでしょうか。その動きを確認しておきましょう。
2021年1月以前の背景と状況
改正前の地方自治法施行規則は「地方自治法234条5項の「契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合」に必要な総務省令で定める措置」として、12条の4の2第1項で一定の電子署名とする旨が定められており、また、第2項で第1項の電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証とする電子証明書を電子署名に併せて送信する必要がある旨を定められていました。
また電子証明書は「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)」の発行するもの(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則2条2項2号イ。職責証明書含む)か、主務大臣から認定を受けた事業者(認定認証事業者)が作成したもの(同号ロ)、あるいは登記官が作成したもの(同号ハ)であることが必要とされていました。つまり、上記で説明した電子サインタイプ(立会人型)は認められていなかったのです。
こうした条件は、契約をする当事者双方が満たす必要があるものです。そのため、自治体と契約をする民間企業にたいして、かなり難しい対応を求めているものであったといえます。
こうした背景から、自治体の電子契約導入は進んでいないとされていました。
2021年地方自治法施行規則の改正と状況変化
2021年の改正によって、電子署名の要件が緩和され、電子サインタイプ(立会人型・事業者署名型)の利用が可能になりました。
またこの法令改正によってクラウド型電子署名も利用可能になりました(本稿では、当事者署名型の「リモート署名」をクラウド上で行う仕組をクラウド型電子署名といいます)。ネットワークに接続できる環境であれば、いつでも、どこでも、電子署名が可能となります。
リモート署名というのは、署名者が、リモート署名事業者が提供するサーバー上に「署名鍵」を設置・保管しておき、この署名鍵を使って署名をするというものです。クラウド上で署名が完結できるうえ、当事者署名の手段として利用できます。
こうした法改正をうけて、自治体では電子契約への活用が期待され、関心が高まっていると考えられます。
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が、2022年5月〜6月に行った「全国自治体電子契約実態調査」(調査対象としたのは全国自治体1788機関。有効回答数は484自治体)によると、すでに導入をしている自治体も含め、約4割の自治体が電子契約の導入に備えているという結果がでました。
しかし、一方で、約半数の自治体では電子契約の導入を現時点では予定していないと回答をしています。
この調査でもうひとつ注目しておきたいのが、従来の紙の契約は効率的ではないと感じている自治体の多さです。85%の自治体が紙の書類による契約には1〜2週間ほどの時間がかかると回答し、過半数の自治体が電子契約に切り替えれば効率化できると考えていることが明らかになりました。
この様子から、自治体においての電子契約導入は着実に進んでいくのではないでしょうか。効率的でないもの、住民や企業の生産性に悪影響を与えるやり方は、速やかに変えていくことが期待されています。
自治体において電子契約を導入する際の注意点
自治体が電子契約を導入する際に注意しておくべき点を確認しておきましょう。
1.業務フローの変更が必要なこと
電子契約を導入すると、既存の業務フローが変更される可能性があります。変更された業務フローになれるまでは見落としや不備の発生するリスクが高まります。
業務フローの変更に際しては、短期的・一時的には、担当職員の負担となるケースもありますので、事前に十分な説明を行い、必要に応じてマニュアルの作成をしましょう。多くの民間企業や自治体で、既に導入されている業務フローです。先行している自治体等を参考にすれば、スムーズに電子契約に移行できると思います。
なかでも、押印が行われてきた、請求書といった書類の変更については、事前に取り組んでおく必要があります。電子契約書では、紙の契約書に用いていた押印は必要ありませんが、自治体の業務において、押印の運営や業務内容が明確になっていないと、スムーズに電子契約書への移行もできなくなります。
2.電子契約については取引先の合意が必要
契約はそもそも両者の合意をもって成立するものです。内容はもとより、紙文書を取り交わしての契約から電子契約に変更することへの合意も必要です。電子契約は、双方にとって、極めて効率的、合理的な方法です。印紙代も不要となり経済的にも合理的です。最初は不安もあるかもしれませんが、一度経験すれば、心配はいりません。多くの方々が既に実践している仕組みです。簡単で効率的だからこそ普及するのです。
電子契約に対応していない契約はごく一部
なお、建設工事の請負契約書、下請事業者に対して交付する「給付の内容」等記載書面、定期建物賃貸借契約の際の説明書面、労働条件通知書や派遣社員に対する条件明示書面など、電子契約の利用に承諾・希望・請求が必要なものがあること、事業用定期借地契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約及び任意後見契約書は、公正証書によって契約を締結すべきことが法律で定められているために、電子契約にできないことにご留意ください。電子契約にできないものはどんどん縮小し、科学技術の進歩を生かす方向に社会は向かっています。(2025年1月現在の情報に基づいた内容です)
3.地域企業への説明会・問い合わせ対応
電子契約に変更する際は、地域企業へ通達をするだけではなく、事前に説明会を開催したり、相談窓口を設けたりするなどが必要です。インフォマートでは、これまでの民間企業をはじめとする実績、特に、飲食店をはじめとする小規模な事業所や企業での多くの取引実績もあり、現場に寄り添った丁寧な対応が可能です。
まとめ:業務効率化が推進され、地域企業や住民にとって魅力的な地域を実現するスマート自治体をめざす
自治体での業務の多くは書類の取り交わしや紙文書による保存、確認などを行います。こうした業務に膨大な量の紙が使われています。それらをデータ化し、業務をデジタル化することで、紙の使用を減らすだけでなく、業務に潜むムダ、ムリ、ムラが省ける可能性が高まります。電子契約もこうした効果が狙えるシステムだといえます。たとえば、電子契約に変更することで、契約書の郵送に時間がかかるという課題が解消できます。また押印漏れや確認などの手間も省略できます。印紙代や印刷、輸送費など、経費面でもムダが削減できます。このように、アナログで行ってきた業務フローにデジタル技術を活用することで、効率化できる可能性が高まるのです。その結果、職員の負担軽減が実現できれば、より高度な業務に時間と労力を割くことができ、住民や地域企業の利便性を向上させることへつなげることができるのです。社会に後れを取ることなく地域の住民や企業の皆様のDXを推進するためにも、自治体が率先してDXを進めることが大切です。
インフォマートが提供するBtoBプラットフォーム 契約書は発行側も受領側もWebだけで契約が完了する高度な電子契約システムです。電子契約の導入を検討されるさいは参考にしてください。
BtoBプラットフォーム 契約書の詳細は次のサイトでご確認いただけます。
※本記事は更新日時点の情報に基づいています。
監修者プロフィール

一般社団法人 未来創造ネットワーク 代表理事
松藤 保孝 氏
自治省(現総務省)入省後、三重県知事公室企画室長、神奈川県国民健康保険課長、環境計画課長、市町村課長、経済産業省中小企業庁企画官、総務省大臣官房企画官、堺市財政局長、関西学院大学大学院 法学研究科・経営戦略研究科教授、内閣府地方創生推進室内閣参事官等を歴任し、さまざまな政策の企画立案、スリムで強靭な組織の構築、行政の業務方法や制度のイノベーションを推進。一昨年退官後、地域の個性や強みを生かすイノベーションを推進する活動を行う。