電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、電子取引のデータ保存は2024年1月1日より完全に義務化されました。また、2023年10月からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されています。こうした改正や新たな規定を背景にして、民間事業者では電子請求書の導入が進んでいます。インフォマートが運営するBtoBプラットフォームは、全国100万社以上の企業で利用されています。一方、自治体でも、業務効率化や地域のデジタル化推進の観点から、電子請求書の導入が注目されています。本記事では、先進自治体の事例をもとに、電子請求書の導入のポイントと効果について解説します。
■ 目次
電子請求書の基本と効果
電子請求書とは
電子請求書とは、紙の請求書ではなく、インターネットを経由して電子データでやり取りができる請求書のことを指します。現在、大きく分けてPDF型とデジタルデータ型の2つの方式があります。
PDF型は、事業者が紙の請求書をPDF化して、メールにPDFファイルを添付して送付したり、自治体側で紙の請求書をスキャンしてPDF化したりする方式です。導入は比較的容易ですが、PDFは画像データのため、その後、数字の入力作業や計算を手動で行う必要があります。
一方、デジタルデータ型は、クラウドシステムで数字や文字を入力して請求書を作成・発行し、データとして送受信する方式です。財務会計システムとの連携により、入力作業をさらに自動化でき、インボイス制度への対応も容易になります。本記事では、このデジタルデータ型の請求書で実現できる効果と導入のポイントについて、先進自治体の事例をもとに解説します。
なお、PDF型とデジタルデータ型のより詳しい比較については、「請求書DXの比較:PDF型とデジタルデータ型」をご参照ください。
また、事業者にとってのデジタルデータ型請求書の有効性については「事業者にとって、デジタルデータ型の請求書が有効である理由」も参考になります。
電子請求書導入の主な効果

請求書作成・訂正の手間・コストの削減
- 一定のフォーマットによる作成時間の削減、数字や単語だけの入力
- 入力ミスは訂正印不要で該当箇所の修正のみで完了、一から作り直す手間を省略可能
- 印刷した請求書と請求データの確認や、そのダブルチェック作業の削減
- 封入の際の宛名確認とそのダブルチェック作業の削減
- テレワーク環境での業務遂行
郵送関連の削減効果
- データ送信による郵送手間の削減
- 郵送コストの削減
- 発送~到着・確認までの時間削減(紙で発送する場合、先方の到着リミットに合わせて発送側の担当者が休日出勤して発送準備を行う必要があったが、その負担を解消)
管理業務の効率化
- データによる効率的な保管
- 期間、取引先別、発注品別など、必要に応じた分類が可能
- 検索機能による探しやすさ
- 紛失リスクの軽減
- 自然災害時等の業務遅延リスクの軽減
システム連携による効果
- 財務関係システム、電子決裁システムとの連携により、さらに業務効率化
- 受領確認の自動化
- 伝票への情報自動転記
- 証拠書類確認作業の軽減
自治体における請求書処理の現状と課題
自治体側の課題
自治体では日々大量の請求書処理が発生しており、インフォマートのBtoBプラットフォームを導入いただいた自治体の例でも以下のような課題に直面していました。
東京都東久留米市では、支出伝票は年間約35,000件、1日約150件の処理が必要となっており:
- 繁忙期は数字の確認や突合に数日かかり、支払遅延のリスクが大きい
- 請求書の記載事項等の不備による差し戻しにより支払い処理が遅れる
- 請求書の毀損や紛失、添付書類の紛失の可能性や添付漏れがある
- 会計事故再発防止対策として、内容確認のための添付資料の増加など、会計課と原課の負担が多い
- (参考:東久留米市の取り組み:デジ田交付金で、一気通貫の会計事務DXへ! 活用事例)
兵庫県多可町では、財政課の決裁業務に1日1時間程度を要しており:
- 支出伝票の決裁は1日80件ほどで、全庁の支出伝票は年間2万件に及ぶ
- 本庁舎と異なる施設(小中学校、観光施設など)は、片道20分~30分かけて紙の調書を持参する必要がある
- 紛失するケースも発生している
- (参考:兵庫県多可町 財務会計システムと電子請求書の連携で進むDX。)
鹿児島県鹿屋市では、登録事業者約1,200社と取引があり:
- 年間約5万通、1日平均200通の請求書処理が必要
- 支所や出張所から会計部署のある本庁へ都度、時間と手間をかけて、紙の請求書を持参する必要がある
- 2022年より段階的に電子決裁システムを導入したが、依然として紙のやり取りが一部場面で残っている
- (参考:鹿児島県鹿屋市 年間約5万通におよぶ受取請求書のデジタル化に着手。)
帳票を「ほぼ紙」でやり取り!書類の不備で地域企業への支払い遅延が発生!自治体にこそ「デジタルインボイス」が求められる理由
詳しくはこちらの資料『自治体の会計業務に関する自治体職員向け実態調査』をご覧ください。
地域事業者の課題
事業者側では以下のような課題に直面しています:
- 納品書や請求書は押印の上、市役所に郵送または持参が必要
- 事業者に郵送費用や移動等の負担がある
- 請求書を郵送した場合、担当課が受け取るまで2~3日かかり、その後数字の確認など請求書の内容確認の会計事務が行われるため、入金まで時間を要する
- 請求書・領収書などの帳票に消費税法で定められた項目を記載し、発行したインボイスを7年間、控えをファイルに綴じて保管するか、電子データとして保管し、また、電子データで保管する場合は、電子帳簿保存法で定められた方法で保管しなければなりません。例えば、紙の請求書をお客様へ送る前に、スキャナで読み取りPDFデータとして保存することが必要になります。このように、インボイス制度や電子帳簿保存法に対応したシステムを用意する必要があります。
自治体と取り引きする地域企業からの悲鳴が続出!地域企業と自治体との取り引きの非効率さを解消する方法とは?
詳しくはこちらの資料『自治体の会計業務に関する地域企業向け実態調査』をご覧ください。
先進自治体に見る電子請求書導入の取り組みと効果
多可町の取り組み
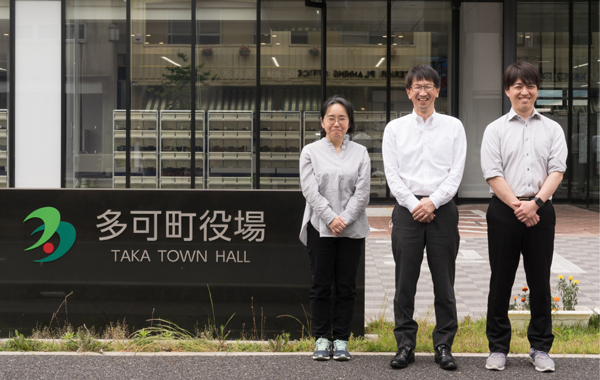
導入プロセス
多可町では、電子請求書導入にあたって段階的なアプローチを採用しています。まず電子決裁システムを導入して素地を作り、2023年1月頃に財務会計システムを次世代型のクラウドタイプに入れ替えました。その後、電子請求書システムの導入へと進みました。
導入時の工夫
電子請求システムの導入時には事業者への配慮を重視しています。事前説明会を開催し、取引の多い事業者から段階的に導入を進める一方で、パソコンになじみがない事業者やインターネット環境がない事業者向けには、紙での請求書提出も継続して受け付けるなど、柔軟な対応を行いました。
実現した効果
この取り組みにより、具体的な効果が現れています。請求書の処理状況が可視化され、システム上でステータス確認ができるようになったことで、支払通知書の郵送が不要になりました。また、電子データでの受け取りにより保管事務の負担が減少し、郵送コストも削減できています。事業者からの反応も良好で、業務デジタル化への関心は想定以上に高く、「実際に使ってみたら簡単だった」という声が寄せられています。
多可町の導入事例のインタビュー記事について詳しくは「財務会計システムと電子請求書の連携で進むDX。事業者様と歩調を合わせ、地域全体のデジタル化へ。」をご参照ください。
鹿屋市の取り組み

導入プロセス
鹿屋市では業務負荷を軽減するとともに、2022年より段階的に導入していた電子決裁システムによる効果を高める目的で電子請求の導入を開始しました。導入にあたっては、前年度の取引実績を分析し、取引件数の多い事業者500社を優先して運用開始の案内を行いました。その後、2023年10月からは全部署での本格運用を開始しています。
導入時の工夫
説明会は、より多くの事業者が参加できるよう、オンライン形式と対面形式の両方を用意しました。多様な参加形式を設けることで、事業者が参加しやすい環境を整えました。
実現した効果
導入後は業務プロセスが大きく改善されています。電子請求書を受信すると各部署の代表メールに通知が届き、受信状況はプラットフォーム画面で確認できるようになりました。また、これまで必要だった紙の支出命令書への請求書の糊付けや押印待ち時間が不要となり、紙の請求書のスキャンやPDF化、会計部署への持参も必要なくなりました。説明会実施後は約半数の事業者がBtoBプラットフォームIDを取得するなど、着実な成果が現れています。
鹿屋市の導入事例のインタビュー記事について詳しくは「年間約5万通におよぶ受取請求書のデジタル化に着手。電子化による業務負担の軽減を実感しています。」をご参照ください。
東久留米市の取り組み

導入プロセス
東久留米市では、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用し、BtoBプラットフォーム「TRADE+契約書+請求書」の導入を進めています。2024年3月からの導入しており、見積依頼から契約、発注、納品書、請求書に至るまで、全ての書類の発行・授受・内容確認・保管を電子データで実施しています。
導入時の工夫
この取り組みにより、帳票確認や差し戻し、郵送等に伴う業務時間とコストの削減を進めています。また、テレワーク環境の整備も計画しています。なお、2023年10月から始まったインボイス制度や電子帳簿保存法への対応は既に実施しており、業務のデジタル化も着実に進めています。
実現した効果
特に紙の書類での取引件数の多い事業者を対象とし、月間で約100通の請求書や70通の契約書を削減。庁内では電子決裁により支出命令起票・審査も完全ペーパーレス化がされました。また、財務会計システムと連携し、システム入力のミスや手間のリスクを軽減しました。
事業者側では類推で郵送費約7.5万円、契約書の印紙57万円の削減、さらに来庁などの移動時間も削減されています。
東久留米市の導入後の活用状況について詳しくは、「地域DXが市の業務を変える。取引事業者と実現した契約・会計事務DX東久留米市の取り組み」をご参照ください。90秒で概要がわかる動画も無料公開で掲載しておりますので、ぜひご視聴ください。
事例から見える円滑な導入のポイント
これら3つの自治体の取り組みから、電子請求書導入を成功に導くためのポイントが見えてきます。
1.システム導入の柔軟なアプローチ
- 電子請求システムは単独でも導入でき、大きな効果が期待できます
- 事業者側:郵送コストと手間の削減、支払状況の可視化
- 自治体側:請求書処理の効率化、保管業務の軽減、紛失リスクの低減
さらに、以下のシステムとの連携により、効果を段階的に高めることができます。
(1)財務会計システムとの連携
- 支払データの自動連携による入力作業の削減
- 会計処理の正確性向上
- 予算執行状況の即時把握
(2)電子決裁システムとの連携
- 決裁過程の迅速化
- 承認状況の可視化
- 完全なペーパーレス化の実現
2.段階的な導入アプローチ
効果的な導入には、以下のような段階的なアプローチが有効です。
- 取引量の多い事業者を優先した段階的な展開
- 事業者の状況に応じた柔軟な対応(紙での提出も継続して受付)
- 丁寧な説明会の実施(オンライン・対面の併用)
説明会の開催方法にも工夫が見られます。多可町、鹿屋市とも事前説明会を重視し、特に鹿屋市ではオンラインと対面の両方の形式を用意することで、より多くの事業者の参加を促しました。さらに多可町では、紙での請求書提出も継続して受け付けることで、事業者の状況に応じた柔軟な対応を実現しています。
まとめ:電子請求書システム導入で自治体のデジタル化を加速
電子請求書の導入は、自治体の業務効率化と地域全体のデジタル化推進の重要な起点となります。多可町、東久留米市の事例が示すように、計画的な準備と段階的な展開により、大きな効果を得ることが可能です。特に重要なのは、職員と地域事業者双方への丁寧な説明と、柔軟な運用方針の確立です。
事業者(市民)にメリットがある取り組みは多々ありますが、職員負担が増えているケースも見られます。しかし、電子請求の導入により、自治体と、その取引先の職員の事務負担が軽減され、政策立案や地域のための付加価値創造の業務に取り組む時間を新たに創出でき、地域のDXの取組みとなります。
まず、現状を見直すことからはじめましょう。ベンダーとの協力・サポート体制の構築も重要な要素となります。
そのなかで、インフォマートが提供しているBtoBプラットフォーム 請求書もひとつの選択肢です。BtoBプラットフォーム 請求書は、請求書の発行だけでなく、受け取り、支払金額の通知など、請求業務全体をデータ化する電子請求書(WEB請求書)システムです。また、デジタルデータ型の為、PDF型のように紙の請求書のスキャンやメールへのPDF添付、数字の入力作業や計算を手動で行う必要がありません。時間・コスト・手間のかかる経理業務を大幅に改善するほか、電子帳簿保存法に対応しているためペーパーレス化、テレワークを実現します。
なお、デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用して、電子請求システムを導入した東久留米市の事例は、以下の記事も参考になります。
※本記事は更新日時点の情報に基づいています。
監修者プロフィール

一般社団法人 未来創造ネットワーク 代表理事
松藤 保孝 氏
自治省(現総務省)入省後、三重県知事公室企画室長、神奈川県国民健康保険課長、環境計画課長、市町村課長、経済産業省中小企業庁企画官、総務省大臣官房企画官、堺市財政局長、関西学院大学大学院 法学研究科・経営戦略研究科教授、内閣府地方創生推進室内閣参事官等を歴任し、さまざまな政策の企画立案、スリムで強靭な組織の構築、行政の業務方法や制度のイノベーションを推進。一昨年退官後、地域の個性や強みを生かすイノベーションを推進する活動を行う。




