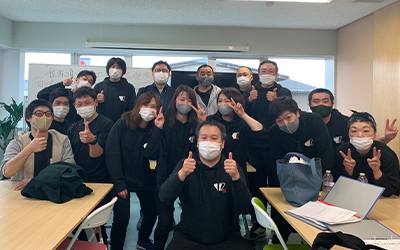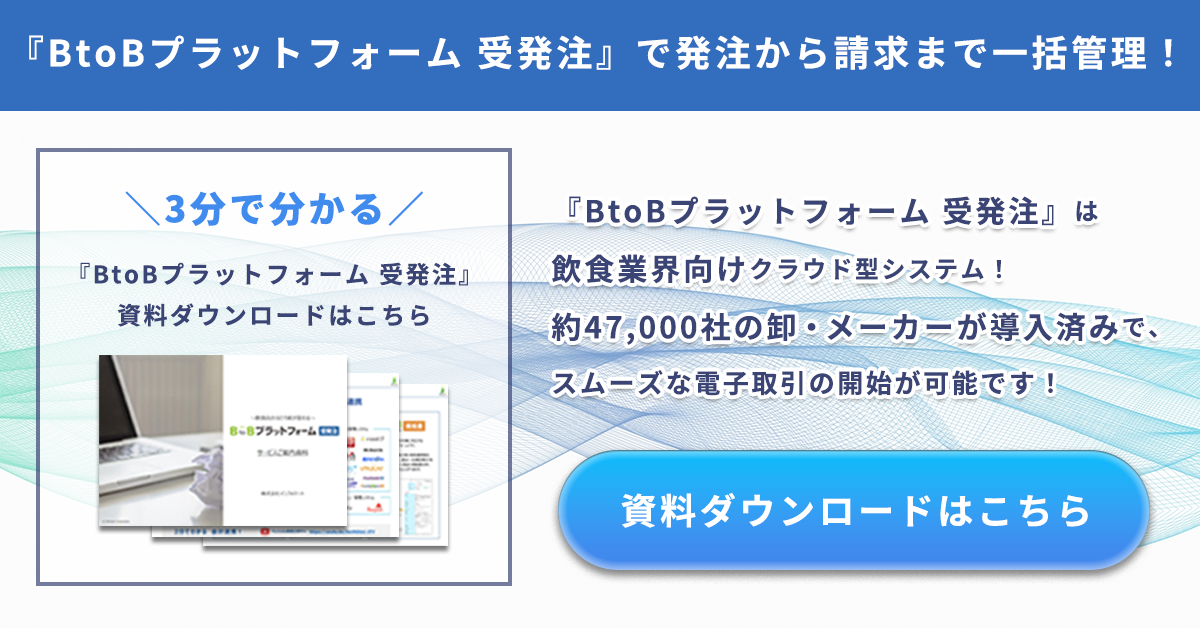広告畑の経験を生かした、強烈なファーストインパクト
【Q】なぜラーメン業態を始められたのでしょうか。
代表取締役 齋藤 晴紀 氏(以下同):もともと東京の小さなアパレルの設立に携わり、主に広告代理業を手がけていました。大手広告会社のアパレル部門ができない地道なPR活動をしながら、それなりのブランドを展開していました。
そんな中、27歳のときに祖父が亡くなって地元に戻ることになりました。そのときに改めて何のビジネスをしようか考えたんです。最初は競争相手の少ないアパレルも考えました。ただ、地方都市だけに顧客対象が絶対的に少ないから厳しいだろうと。
競争が激しくても潰れずに続けていける業種、つまりレッドオーシャンに絞ろうと決めました。リサーチの結果、山形ではラーメン業界の競争が激しいことが分かり、私自身もラーメンを年400食くらい食べ歩きするほど好きでしたので、これだ、と。そこから3年掛けてアパレルの運営をしながらラーメンの修行に打ち込みました。

株式会社もっけだのフードサービス
代表取締役 齋藤 晴紀 氏
オープン初日から行列でした。レッドオーシャンに挑むため、どんな手を打ったのでしょうか。

アパレルで培ったPRの手法を駆使しました。まずは味とビジュアルです。それを、「聞いたことがない」と思わるような形でPRしていきました。もともと山形県酒田のご当地ラーメンといえば、縮れ系の自家製麺と透き通った醤油味のスープが特徴で、いわゆる「二郎インスパイア系」はまったく存在していませんでした。だから二郎系ラーメンを選んだのです。
そこに「ラーメン二郎とは」というストーリーをテレビや広告で大きく打ち出しました。地元では初めての味だけに「よく分からない食べ物」「ふつうのラーメンとは違うのか」と、オープン前から話題になるよう仕掛けた結果、オープン初日から行列を生むヒットへとつながりました。
【Q】PRで突破口は開けましたが、その後の店舗展開をするためにどんな施策を講じましたか。
他店との徹底的な差別化を図りました。もともと地元民の間でラーメンといえば、ファミリーで出かけるお店、という印象が根強いんです。店の面積も大きくて駐車場も広くて、食堂のようなお店が当たり前でした。ラーメン以外のメニューも幅広く揃えています。
その市場にあとから参入するとなったら、他と同じコンセプトでは到底太刀打ちできません。そこでまず、ファミリーは狙わないことを決め、女性や60代以上もターゲットから外しました。大型店が多いなか、最初に出店した『風林火山鶴岡本店』は、わずかカウンター7席のみ。回転率を重視した店という7点に絞ったのです。

【Q】いつも混んでいる店、という印象につながりますね。
そういう効果はあったと思います。ありがたいことに、二郎系のこってりだけではなく一般的なラーメンも食べてみたいという声をいただいて、翌年2店舗目の酒田店は、35席の二郎系がメインではありながら中華そばもある、といった店舗を展開しました。
さらに3店舗目、4店舗目は、二郎系とは対極にある、あっさり系の『中華そば雲ノ糸』を出しました。これは地元で主流のあっさり系への需要が根強かったためです。何より開店当初に排除してきたファミリーや高齢者、女性にも食べていただきたかったので、毎日食べても飽きが来ない食事を提供したいと思っていました。いまはそれぞれのお客様が互いに行き来してくれるようになり、相乗効果が生まれています。