取締役会は企業の取締役が集まり、経営に関する意思決定を行う会議体です。取締役会議事録は会社法で定めのあるとおり、取締役会が行われるたびに作成しなければなりません。とはいうものの、議事録には押印が必要で、電子化をする際に必要な電子署名の要件も細かく決められていました。
しかし法務省が2020年に新しい見解を表明したことから、これまでよりも柔軟に取締役会議事録の電子化が可能になり、注目を集めています。本記事では、取締役会のオンライン開催や取締役会議事録の電子化について、わかりやすく解説します。
- ■ 目次
1.取締役会議事録とは
2.取締役会議事録の押印が不要、電子署名でも対応可能に
3.取締役会議事録電子化が注目を集める背景
4.取締役会議事録を電子化するメリット
5.取締役会議事録を電子化する際の要件や注意点
6.取締役会をオンラインで開催する方法や注意点
7.取締役会議事録を電子化する方法
8.まとめ
1.取締役会議事録とは
取締役会議事録は、企業における重要な決定を記録する役割から、その取り扱いが会社法によって詳細に取り決められています。会社法における公開会社には、取締役会議事録作成の義務が課せられており、書面または電磁的記録で作成しなければなりません。公開会社とは、株式に譲渡制限のない株式会社を意味します。
通常の会議後に作成される内部的な議事録とは異なり、企業における正式な文書として扱われます。金融機関や出資者、株主などのステークホルダーに開示する場合もあるため、重要な書類の一つです。
コロナ禍においてワークスタイルが大きく変化したことにともなって、取締役会をオンラインでするケースも増えています。その一方で、議事録の作成や押印は紙で行っているケースも少なくありません。
関連リンク:取締役会議事録とは
2.取締役会議事録の押印が不要、電子署名でも対応可能に
法務省は2020年5月に取締役会議事録に関する新しい見解を示し、「署名又は記名押印に代わる措置」としてクラウド電子契約サービス事業者が提供する電子署名も有効とすると発表しました。
従来の見解においては、リモート署名などは認められていませんでしたが、法務省の新見解により、議事録を電子化する際の利便性が飛躍的に高まることとなりました。
有効な電子署名の定義は会社法施行規則225条により定められていますが、法務省によりクラウド電子契約サービス事業者が提供する電子署名も含まれるとされたからです。
参考・出典:取締役会議事録に施す電子署名についての法務省見解│新経済連盟
e-Gov法令検索会社法第二百二十五条│デジタル庁
3.取締役会議事録電子化が注目を集める背景

取締役会議事録の電子化が注目を集める背景にはどのようなものがあるのでしょうか。
①コロナ禍で加速したオンライン取締役会
コロナ禍では、リモートワーク/ハイブリッドワークが急速に浸透し、新たな就労環境に適応するために各社がリモート対応を急ぎました。この流れに乗り、取締役会においてもオンライン開催を導入済みという企業は96%を超えるという調査結果もあるほどです。
その反面、実際の会議とは異なり意見が述べにくいといった問題点も浮き彫りになりつつあるようです。また、機密性の高い内容についてはオンラインでは議論しにくくなっている現状も指摘されています。
このようにセキュリティ面における課題などはあるものの、オンラインで開催する取締役会は、その利便性などから今後も継続されると見られています。
②社内文書も電子署名による電子化が加速
独立系ITコンサルティング・調査会社株式会社アイティアールの調査によると、新型感染症を契機とした社外取引文書(契約書など)の電子化対象拡大を行うと答えた企業は、36%にも上りました。
社外取引文書に続き取締役会議事録に代表される社内文書も、電子契約サービスで電子署名が行えることから、今後も電子化が拡大されると予想できます。
4.取締役会議事録を電子化するメリット
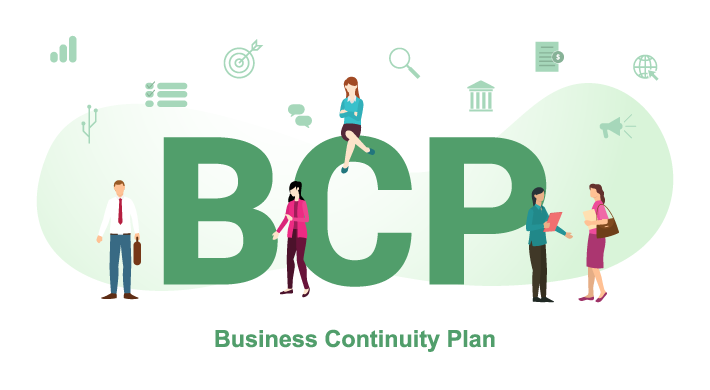
取締役会議事録を電子化するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。コストや会議開催に関する業務負荷削減だけではありません。
①テレワークや働き方改革への対応(社内監査)
取締役会議事録を作成する場合、取締役会の出席者(代表・取締役・監査役など)に対して、記名や押印を求める必要があります。取締役会議事録を電子化すれば、郵送で書類のやり取りを行う手間や時間が省けるため、テレワークへの対応と効率化が実現できます。
リモート監査も増えています。電子化することで必要な時に議事録の検索もしやすいため、社内監査にも簡単に対応できるといえるでしょう。
②セキュリティやガバナンスの強化
電子署名を活用することで、紙の場合より高度なセキュリティを担保できます。アクセス権限を設定することで、第三者や部外者に当該企業における重要な決定事項などを見られるリスクがなくなる効果が期待できます。
企業に対するコンプライアンス強化や透明性のあるガバナンスを求める機運は高まる一方です。 意思決定において重要な取締役会議事録の真正性担保や、会議体のプロセスを記録することは非常に重要です。
社会的な要請を背景に、電子署名技術が広く浸透した結果、社内文書の電子化を推進しやすくなっています。企業における情報の透明性を確保することでガバナンス強化にもつながるでしょう。
③BCPとしても有効
BCPはBusiness Continuity Planningの略で、企業などの事業継続計画を指します。自然災害のみでなく、テロや事件・事故・システムにおける障害や、事業に大きな影響を及ぼす不祥事が起きた時でも混乱せず、事業を継続するための計画を定めることは重要なリスク管理です。
従来の紙を使用した取締役会議事録の保管は、地震や火事などの自然災害における維持が難しく、記録が失われてしまうリスクも。
日本はとくに自然災害リスクが高い国であるため、事業継続計画の策定が重要です。
内閣府も、日本は地理/地形的または気象的条件から、地震・津波・台風・豪雨などの災害を受けやすい国土であるとして注意を促しています。
電子署名付与などにより、取締役会議事録を電子化しておけば、過去の重要な意思決定の内容やプロセスが保管されやすくなり、BCPとしても有効な手段となります。
参考・出典:日本の災害対策│内閣府
5.取締役会議事録を電子化する際の要件や注意点

取締役会議事録を電子化する際の要件や注意点を詳しく解説します。
①立会人型、当事者型いずれも利用可能
電子署名の付与方法には、立会人型と当事者型の2つがあり、それぞれ以下のような特徴を持っています。
・立会人型
立会人型は、電子署名を行う本人ではない者が、署名の意志を持つ当事者の指示のもと電子署名を付与する方式。 メール認証などで当事者の本人確認を行い、手続きを進めます。法的にも署名を行うのは依頼を受けている第三者ですが、当事者の意思によって行われたものであれば、本人による電子署名だとみなされます。
・当事者型
当事者型は、署名する本人の電子署名を電子契約サービスなどで付与すること。 当事者型を利用するには、認証サービスを行う企業に本人証明を行って、本人の電子証明書を発行します。
取締役会議事録の電子化には、上記いずれも使用可能となっています。
②定款・印章規程・文書規程の改訂が必要
取締役会議事録を電子化する際、定款をはじめとして、印章規程や文書規程の改訂が必要となっています。定款に押印規定を設けている企業は、まずこれを削除しなければなりません。とくにグループ企業で取締役会議事録電子化を計画している場合は、すべてのグループ企業の定款を確認する必要があることに注意が必要です。
企業における取締役会議事録に関する詳細な取り扱いは、主に取締役会規程で定められています。現在の取締役会規程を確認し、「記名押印しなければならない」などという記述になっている場合は電子署名も認める旨変更するとよいでしょう。
同様に、自社に印章管理規程がある場合にはこちらの内容も確認しておきましょう。
取締役会議事録の電子化のみであれば変更の必要がない場合もありますが、電子契約サービスも並行して使う場合には印章管理規程を変更しておいた方がよいといえます。
③オンライン登記申請する場合には会社の商業登記電子証明書の取得が必要
電子証明書は、行政手続きを行う際、申請者の本人確認のために使用する証明書です。 電子証明書を用いることによって、手続きの正確性や真正性が担保されます。
本店所在地の変更等などのオンライン登記申請において、取締役会議事録を添付資料として申請するためには、会社の商業登記電子証明書そのものの取得が必要です。商業登記電子証明書は、法務局が企業の代表者に対して発行する証明書であり、オンライン申請時に添付する必要があります。
つまり、オンライン登記において取締役議事録を添付書類として申請する際には、「商業登記電子証明書」と「取締役全員の電子署名」が必要ということです。
参考・出典:ご利用の手引き│法務省
④保存期間と保存場所
取締役会議事録は会社法により、その保存場所と期間が定められています。
会社法371条によると、取締役会議事録は
- 10年間のあいだ
- 企業の本店において
保存されなければなりません。
各種監査においても確認されるポイントなので、上記を守って対応しましょう。
6.取締役会をオンラインで開催する方法や注意点
取締役会をオンラインで開催する方法や、その場合の注意点を詳しく解説します。
①取締役会はテレビやWEB会議でも開催可能
取締役会においては、参加者が必ずしも「同じ場所にいなければならない」など、出席の方法については厳密に決められていません。これは会社法施行規則101条3項1号において「当該場所に存しない取締役が取締役会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。」としていることに根拠が求められます。
そのため、物理的に開催場所にいなくとも、テレビ会議・Web会議システムによる取締役会出席が可能です。取締役会のオンライン開催や開催方法は、開催通知を行う招集権がある人が決定できます。
開催の1週間以上前に招集通知を送る必要があり、取締役会規定に特別の定めがない限り、法的に通知方法に関する定めはありません。
②双方向性のあるインタラクティブな手段が理想的
取締役会をオンラインで行う場合には、双方向性のある手段でなくてはなりません。会社法においても、会議室などで集まることと同様に柔軟かつ円滑な意思疎通をできることが必要だとされています。
映像や音声のないチャットや双方向性に欠ける方法は、活発な議論にも繋がらないため望ましくありません。顔を合わせない会議の場合は、普段よりもファシリテーションの重要性も増すため、活発な議論に繋げられるよう工夫も必要です。
ツールの選定時には、操作性や利便性、セキュリティなどを総合的に判断しましょう。
参考・出典:e-Gov法令検索会社法第百一条│デジタル庁
③開催場所として、会議システムの情報を記載
オンラインで取締役会を行う場合には、開催場所として会議システムの情報を記載しておきましょう。
- システム/ツール名
- 開催URL
などを記載することが妥当です。
7.取締役会議事録を電子化する方法

具体的に、取締役会議事録の電子化はどのように行えばよいのでしょうか。電子契約サービスを使用することで登記申請する際の流れは、以下のようになっています。
取締役会議事録を作成する
必要な項目を網羅しているか確認のうえ、取締役会議事録を作成していきます。
取締役会議事録には、日時・場所・出席者・議長・書記・議論の内容と結果などを明確に示す必要があります。
出席者の電子署名を記録する
取締役会議事録に出席者全員の電子署名を記録します。
また、議事録を登記申請に使用する場合は加えて下記の手順が必要となります。
会社の電子証明書(商業登記電子証明書)を取得する
企業がオンライン登記するためには、商業登記電子証明書の取得が必要です。このとき、商業登記電子証明書の発行対象となるのは、登記されている「会社・法人の代表者」に限られることに注意しなければなりません。
登記申請を行う
商業登記電子証明書と取締役の電子署名がなされた取締役外議事録を添付し登記申請します。司法書士などの第三者に登記申請を依頼する場合は、委任状が必要です。依頼時に詳細を確認してみましょう。
8.まとめ
法務省が2020年に新見解を示したことにより、クラウド電子契約サービス事業者が提供している電子署名も取締役化議事録の作成に有効だとされました。取締役会の電子化はコスト削減や業務効率化につながります。さらにワークスタイルへの柔軟な対応やガバナンス強化・BPO対策など、電子化するメリットは複数あげられます。
ぜひ取締役のオンライン開催と議事録の電子化に取り組んでみてください。
関連リンク:電子契約に関する各種セミナーはこちら




