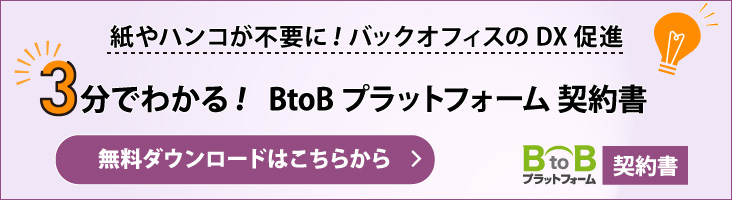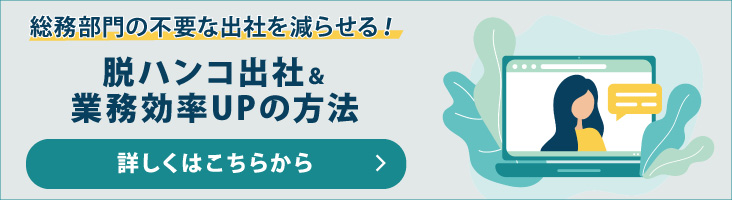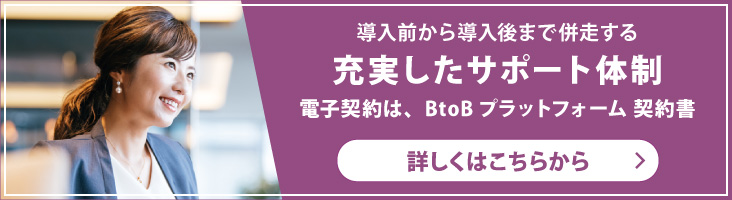電子化が進む現代社会において、「脱ハンコ」は企業経営の効率化の方法として注目を集めています。長年日本の商習慣に根付いてきた押印文化から脱却することで、業務プロセスの迅速化や働き方改革の推進が期待されています。
本記事では、脱ハンコの意義、企業が脱ハンコに取り組むメリット・デメリット、そして実現に必要なツールやポイントを幅広く解説します。
- ■ 目次
1.脱ハンコとは
2.脱ハンコのメリット
3.脱ハンコのデメリット
4.脱ハンコを実現するためのツール・システム
5.脱ハンコを実現するためのポイント
6.脱ハンコ実現にはポイントを押さえて計画的な推進が不可欠
1.脱ハンコとは

「脱ハンコ」とは、従来の押印や印鑑による承認・確認プロセスを、電子署名やデジタル認証などの方法に置き換える取り組みを指します。具体的には、契約書や申請書類への押印を不要とし、電子的な手段で本人確認や意思表示を行うことを意味します。
日本では古くから、ハンコ(印章)が契約や公文書の正当性を示す重要な手段として広く使用されてきました。しかし、電子化が急速に進む現代社会において、この伝統的な慣行が業務効率化の大きな障壁となっていました。
転機となったのは、2020年に政府が行政手続きの簡素化の一環として「脱ハンコ」を宣言したことです。これを契機に、ビジネスや行政のさまざまな場面で脱ハンコの動きが大きく加速しました。
この「脱ハンコ」の流れは、企業にとっては大きな変化をもたらすものです。特に、ビジネスプロセスの効率化やコスト削減を追求する企業にとって、脱ハンコは非常に魅力的な選択肢となっています。
参考:河野内閣府特命担当大臣記者会見要旨 令和2年11月13日 - 内閣府
脱ハンコが注目される背景
政府が脱ハンコを主導したことに加え、昨今、脱ハンコが注目を集める要因には以下のような背景があります。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速 グローバル競争の激化や人手不足を背景に、企業のDXが加速しています。業務プロセス全体のデジタル化が進展し、従来の紙とハンコを中心とした業務フローが、デジタルワークフローへと移行しつつあります。
ハイブリッドワークへの対応 コロナ禍でのリモートワーク導入をきっかけに、多くの企業が電子契約の利便性を実感しました。現在は出社を再開した企業も多いものの、一度導入された電子契約システムは業務効率化の要として定着しています。また、ハイブリッドワークの浸透に伴い、場所を問わない契約手続きの需要は依然として高く維持されています。
コンプライアンスと内部統制の強化 電子契約や電子承認システムなどの電子的な手段の導入により、承認プロセスの透明性が向上し、監査対応も容易になります。企業のコンプライアンス体制と内部統制の強化につながるため、経営層からも高い関心を集めています。
2.脱ハンコのメリット

企業が脱ハンコに取り組むことには、以下のようなメリットがあります。
デジタル化の推進
脱ハンコは、企業のデジタル化を大きく推進する重要な取り組みです。まず、押印プロセスの電子化は、紙ベースの業務フローをデジタルに移行する契機となります。これにより、企業全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)が加速します。
電子署名や電子契約の導入は、単に押印をなくすだけでなく、関連する業務プロセス全体のデジタル化につながります。例えば、文書の作成から承認、保管、検索までの一連の流れがデジタル上で完結するようになり、業務の自動化やデータの活用が容易になります。
さらに、クラウドベースのシステムを採用することで、場所や時間の制約なく業務を遂行できるようになります。これは、リモートワークやフレキシブルな働き方を支援し、デジタルを活用した新しい働き方の実現に貢献します。
業務効率の向上と生産性の向上
脱ハンコは、押印のための出社や管理部門との調整、印刷・製本・郵送など、紙の書類に関連する煩雑な作業を解消します。特に書類の保管管理における改善効果は顕著です。従来は書類を連番で一覧化してファイリングし、保管場所を管理する手間が発生していました。さらに、書類を探す際は管理表と実際の保管場所を照合し、外部倉庫からの取り寄せと返却が必要なケースも多く、保管場所の誤りがあれば書類の紛失にもつながりかねませんでした。
また、契約業務における営業活動の効率化も大きなメリットです。これまでの契約手続きでは、社内での押印から始まり、郵送、取引先での押印、返送まで、契約完了までに多くの時間を要していました。さらに、急を要する案件では契約書を直接持参せざるを得ず、営業担当者は本来の営業活動の時間を割かれていたのが実情です。
これらの課題は押印の電子化により解決されます。総務部門は煩雑な書類管理から解放され、営業担当者も顧客折衝や案件獲得といったコア業務に専念できるようになります。文書はオンラインでキーワード検索が可能となり、瞬時に必要な書類を見つけ出せる上、契約手続きもオンラインで完結するため、ビジネススピードが格段に向上します。
これらの効果により、企業全体の業務効率が向上し、結果として生産性が大幅に改善されます。脱ハンコは、単なる押印の廃止ではなく、業務プロセス全体を最適化し、企業の競争力を高める重要な取り組みといえるでしょう。
コスト削減
紙の消費量や印刷費、郵送費、保管スペースなどのコストが削減できます。具体的には、書類の印刷にかかるインクやトナー代、大量の書類を保管するためのキャビネットや倉庫のレンタル料、書類の郵送や宅配にかかる費用などが大幅に削減されます。これらの直接的なコスト削減に加え、書類の作成や管理に費やす人件費も抑えることができます。
また、紙の使用量減少は、環境負荷の軽減にもつながります。森林資源の保護や、紙の製造・廃棄過程で発生するCO2排出量の削減は、SDGsが掲げる環境保全の取り組みの一つです。このような取り組みにより、企業のESG評価が向上し、環境に配慮した経営を実践する企業としてステークホルダーからの信頼を高めることができます。
さらに、電子契約の導入で印紙税の節約が可能です。印紙税法では、契約の類型にもよりますが、一定の金額以上の契約書に印紙を貼付する必要があります。しかし、電子化された契約書では印紙税が不要となります。これにより、高額な契約を頻繁に行う企業にとっては、大きなコスト削減効果が期待できます。
電子契約なら収入印紙は不要?印紙コスト削減シミュレーション
セキュリティの強化とコンプライアンスの向上
電子署名の導入は、セキュリティとコンプライアンスを大幅に強化します。 改ざん困難な電子署名と監査証跡により、従来の押印以上の信頼性を確保できます。また、文書の電子化と一元管理により、紛失リスクを軽減し、アクセスと操作の厳密な制御が可能になります。この結果、内部統制が強化され、監査対応や法令遵守がより容易になります。
このように、脱ハンコは単なる業務効率化にとどまらず、企業のリスク管理とコンプライアンス体制を強化する重要な取り組みです。これにより、企業の信頼性向上と持続可能な成長を支える強固な基盤が構築されるでしょう。
紙から電子契約・署名への切り替えで防げる改ざんリスク
3.脱ハンコのデメリット

一方で、脱ハンコには以下のようなデメリットも存在します。
初期投資コストがかかる
電子署名システムの導入には、一定の初期投資が必要です。主な費用には、ソフトウェアライセンス代やクラウドサービスの利用料が含まれます。また、既存システムとの連携やカスタマイズ、従業員教育のコストも考慮する必要があります。
これらの費用は企業の規模や導入範囲によって変動しますが、長期的には業務効率化やコスト削減のメリットがこの投資を上回ることが期待されます。導入を検討する際は、短期的なコストだけでなく、長期的な投資対効果も考慮することが重要です。
社内外の調整
長年の習慣を変えることで、新しいシステムへの不安を感じる従業員もいるでしょう。また、すべての取引先が電子契約に対応しているとは限りません。業務フローの見直しが必要な場合もあるため、新しい方法に慣れるためには一定の負担をかけることになります。まずは、社内外に脱ハンコの目的やメリットを丁寧に説明し理解を求めることが必要でしょう。
電子化が制限されるケースがある
一部の公的書類や特定の契約形態では、依然として実印や紙の書面が必要とされます。例えば、事業用定期借地契約などが該当します。
しかし、法改正により徐々に電子化の範囲は拡大しており、不動産関連書類や販売契約書でも電子化が可能になってきています。
企業は自社の業務内容に応じて、電子化可能な範囲を見極め、段階的に導入を進めることが重要です。完全な脱ハンコや電子化には課題が残されていることを理解しつつ、対応を検討する必要があります。
どんな契約書が電子化できるの?
4.脱ハンコを実現するためのツール・システム

脱ハンコを実現するための代表的なツールやシステムを紹介します。
電子署名システムデジタル文書に電子的な署名を付与するシステムです。法的効力を持つ署名を電子的に行い、契約書などの文書を安全かつ効率的に処理します。
電子印鑑システム従来の印鑑を電子化し、電子文書に押印できるようにしたシステムです。日本の印鑑文化に馴染んだユーザーにとって直感的で、視覚的にも従来の印鑑に近い形となっています。
ワークフローシステム文書の作成、承認、署名などの業務プロセスを電子化し、管理するシステムです。承認フローを自動化し、文書の流れを可視化することができます。
ワークフローシステムで社内稟議を電子化
電子契約システム署名や印鑑の電子化に加え、契約手続きに必要な機能を統合したシステムです。企業内の申請・承認・決裁のフローを電子化し、一元管理することができます。多くのサービスは高度なセキュリティ対策が施されており、安心して導入できます。
近年は、電子契約、ワークフロー、文書管理など、複数の機能を一つのプラットフォームで提供するシステムが主流となっています。企業は自社の業務内容や規模に応じて、必要な機能を備えた最適なシステムを選択し、導入することが重要です。特に脱ハンコを効果的に進めるには、電子契約からワークフロー管理をカバーできるツールを選定することをお勧めします。これにより、スムーズな業務の電子化と安全な運用が可能となります。
電子契約とは?仕組みやメリット、法律、導入事例から比較ポイントまで解説
5.脱ハンコを実現するためのポイント

脱ハンコを成功させるには、計画的かつ段階的なアプローチが重要です。以下に、効果的な導入のための主要なポイントを紹介します。
- 1.現状分析と問題点の洗い出し
- 日常的に発生する押印業務を確認し、現在の作業にどのような手間やコストがかかっているかを把握します。特に時間を要する作業や、改善効果が期待できるポイントを整理しましょう。
- 2.脱ハンコ可能な書類の特定
- 電子化可能な書類と電子化できない書類をリストアップします。初めは全ての書類を一度に変更するのではなく、リスクを最小限に抑えつつ効果が得られる書類から始めるスモールスタート方式がおすすめです。
- 3.具体的な目標設定
- 分析結果に基づき、「承認プロセスの30%短縮」や「年間コストの20%削減」など、具体的な数値目標を設定します。明確な目標があることで、取り組みの進捗や成果を客観的に評価できます。
- 4.適切なツール・システムの選定
- 目標達成に必要な電子署名システムやワークフローシステムを慎重に選定します。セキュリティ、操作性、コスト、他システムとの連携性を総合的に評価し、複数のベンダーのデモを比較検討して、自社の状況に適したツール・システムを選びましょう。
- 5.試験運用の実施
- 選定したシステムの導入後、小規模な試験運用を行い、問題なく機能することを確認します。実際に使用してみることで、操作方法の把握や潜在的な問題点の発見ができます。
- 6.段階的な導入
- 社内の稟議書や申請書など、内部文書から脱ハンコを開始し、徐々に取引先との契約書にも拡大していきます。この段階的なアプローチにより、問題点を早期に発見し、修正することができます。
- 7.ワークフローの作成と社内周知
- 新しいシステムを誰でも使えるよう、わかりやすいワークフローを作成し、社内に運用方法を周知します。社内研修やデモンストレーションの機会を設けることで、スムーズな移行を促進できます。
- この段階的なアプローチにより、社内外の関係者に徐々に慣れてもらう時間的余裕も生まれ、効果的な脱ハンコの実現が可能となります。
6.脱ハンコ実現にはポイントを押さえて計画的な推進が不可欠

脱ハンコは、単なる押印の廃止ではなく、企業の業務プロセス全体を見直し効率化を図る重要な取り組みです。その実現により、業務スピードの向上、コスト削減、セキュリティ強化、そして従業員の働き方改革など、多岐にわたるメリットが得られます。これらは企業の生産性向上と競争力強化に直結します。
自社の状況を十分に分析し、計画的かつ段階的な導入をすすめることで、これらのメリットを最大限に活かすことができます。ただし、導入を成功に導くためには、以下のような点に注意を払う必要があります。
- 社内外への説明と理解促進
- 運用ルールの整備
- 取引先への説明と移行準備
- 導入後の継続的なサポート体制
特に重要なのが、導入前から導入後まで一貫してサポートを受けられる体制が整っているかどうかです。導入をご検討の際は、単なるシステムの機能だけでなく、貴社の経営課題解決に寄り添えるパートナーとしてのサポート力も重視するとよいでしょう。
「BtoBプラットフォーム 契約書」では、25年以上の企業間取引の経験を活かし、導入前の社内説明会の開催から、運用ルールの整備、取引先への説明サポート、さらには導入後の継続的なフォローまで、包括的なサポート体制を整えています。ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。豊富な導入実績を持つ専門スタッフが、貴社に最適な導入プランをご提案させていただきます。
電帳法改正対応の電子契約システムで契約書を電子化

宮内 宏 弁護士
宮内・水町 IT法律事務所
1985年に東京大学工学系大学院電子工学専門課程(修士課程)卒業。同年、日本電気株式会社に入社し、中央研究所にて、情報セキュリティ、AI等の研究に従事。その後、東京大学法科大学院を経て、2008年に弁護士登録。
現在は電子契約を始めとする電子取引や電子署名に関する法律業務に従事。政府や地方公共団体の委員を多く務めており、上場会社の社外役員、大学の非常勤講師にも就任。