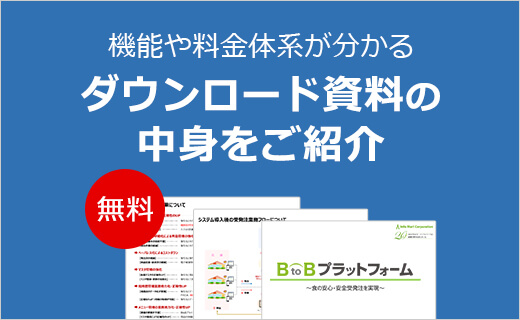飲食店経営において、感覚や経験に頼った判断は、環境変化の激しい今の時代ではリスクにもなり得ます。特に店舗ごとの変動費「FLコスト」のコントロールが曖昧なままでは、利益を圧迫する要因を見逃しがちです。このFLコストこそが、赤字転落のサインや、収益最大化のヒントを教えてくれる経営の羅針盤となります。
そこで今回は、FLコストの管理を仕組み化し、多店舗にわたる収益構造を安定させるための実践ステップを解説します。
FLコストとは?飲食店経営を安定させる指標と適正値・改善策を徹底解説
2025/11/04
FLコストとは?
FLコストとは、「Food(食材費)」と「Labor(人件費)」を合算した飲食店経営の主要なコスト項目です。これらが売上に対してどの程度の割合を占めるかを示す「FL比率」は、収益性や運営効率を数値で把握するための重要な指標となります。
FLコストの計算方法
FLコストとFL比率の基本的な計算式は以下のとおりです。
・FLコスト:食材費 + 人件費
・FL比率(%):(食材費 + 人件費)÷ 売上高 × 100
一般的にFL比率は60%以下が望ましく、これを上回ると利益が圧迫される恐れがあります。近年では、家賃(Rent)を含めた「FLR比率」も重要視され、経営の実態をより正確に捉える手段として注目されています。
なぜ今、FLコストの管理が必要なのか?
飲食業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、FLコストの管理は、店舗ごとの無駄を発見し、収益構造を安定させるうえで欠かせません。
FLコストを把握しなければ、利益構造の悪化に気づけない
FLコストは、売上の約6割を占めるといわれます。この比率を意識せずに経営を続けると、仕入れや人件費が膨らんでも、売上だけを見て赤字リスクに気づけないことがあります。
たとえば、同じFLコストでも売上規模によって利益の状況は大きく異なります。
たとえば、同じFLコストでも売上規模によって利益の状況は大きく異なります。
| 売上高 | 食材費 | 人件費 | FL比率 | 経営状態 |
|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 60万円 | 40万円 | 66.7% | 赤字リスク大 |
| 200万円 | 60万円 | 40万円 | 50.0% | 黒字可能 |
| 300万円 | 60万円 | 40万円 | 33.3% | 優良経営 |
このように、FLコストの「金額」ではなく「売上に対する比率(FL比率)」を把握することが重要です。
融資や新規出店判断でもFL比率は信用材料になる
飲食店を複数店舗で展開・管理する責任者にとって、FL比率は、融資や新規出店の判断においても重要な信用指標といえます。
金融機関や投資家は、コスト管理の精度と利益計画の実現性に注目するため、FL比率が60%以下に収まっていれば、経営体制の信頼度が高まります。
さらに、家賃を加味したFLR比率【=(食材費+人件費+家賃)/売上】を70%以下に設計できていれば、収益構造の健全性を数値で裏付ける材料になります。
金融機関や投資家は、コスト管理の精度と利益計画の実現性に注目するため、FL比率が60%以下に収まっていれば、経営体制の信頼度が高まります。
さらに、家賃を加味したFLR比率【=(食材費+人件費+家賃)/売上】を70%以下に設計できていれば、収益構造の健全性を数値で裏付ける材料になります。
多店舗展開の成功には、FL比率の標準化とPDCAの仕組み化が不可欠
単独店舗であれば、経験や勘に頼った運営でもある程度対応できますが、店舗数が増えると属人的な判断では安定した再現が困難になります。
下表は店舗規模ごとのコスト構造の目安です。実際には業態や立地、客単価、提供スタイルなどの要因によって数値は変動します。実績に合わせて、適切に調整することが重要です。
下表は店舗規模ごとのコスト構造の目安です。実際には業態や立地、客単価、提供スタイルなどの要因によって数値は変動します。実績に合わせて、適切に調整することが重要です。
| 店舗規模 | 食材費(原価)率の目安 | 人件費率の目安 | 家賃比率の目安 | 利益率目安 |
|---|---|---|---|---|
| 小型店 | 約28〜32% | 約25〜30% | 約8〜10% | 約10%以上 |
| 中型店 | 約30〜33% | 約22〜28% | 約10〜12% | 約7〜8% |
| 大型店 | 約32〜35% | 約20〜25% | 約12〜15% | 約5%前後 |
また、多店舗展開を成功させるには、各店舗のFLコストを数値で可視化し、統一されたFL比率のもとで管理することが欠かせません。この統一基準をもとにPDCAサイクルを回すことで、初めて経営の標準化が実現します。
PDCAの各段階では、次のようなFLコストの活用が求められます。
PDCAの各段階では、次のようなFLコストの活用が求められます。
Plan:FL比率を60%以内に設定(例:食材費30%・人件費30%)
Do:食材費・人件費をPOS等で日々記録し、実績を蓄積
Check:売上とのバランスを週単位で把握し、目標値との差分を分析
Action:分析結果に基づき、メニューやシフトの改善策を講じる
このように、FLコスト管理を仕組み化することで、全店共通の判断基準と改善サイクルを確立できます。
FLコストが高止まりしてしまう原因
「FLコストの適正化を目指していても、思うように数値が改善しない」という悩みには主に以下の原因が考えられます。
食材ロス(廃棄・オーバーポーション)が多く、原価率が悪化している
FLコストが高止まりする背景には、食材廃棄や在庫ロスの増加が大きく影響しています。
・食材廃棄の増加: 賞味期限切れや売れ行きの悪いメニューの見直し不足が、仕入費用の無駄を招きます。
・オーバーポーション: 定められた食材量を超えて過剰に盛り付けると、わずかな違いでも原価が上がり、多店舗間で原価率のバラつきが発生します。
特に多店舗展開では、調理基準のバラつきは全体収益の安定を妨げる可能性があります。
廃棄食材のコストも売上原価に含まれるため、粗利益を圧迫しFL比率を押し上げます。
廃棄食材のコストも売上原価に含まれるため、粗利益を圧迫しFL比率を押し上げます。
来客数に応じた適正シフトが組めておらず、人件費が過剰になっている
来客数の波に応じた柔軟なシフト調整ができていないと、人件費が過剰になりがちです。
「念のため」といった感覚で厚めに人員を配置していると、売上の少ない日でも人件費が膨らみ、人件費率が高止まりする要因になります。たとえば、金曜夜は混雑しても、月曜や雨天の日には来客数が半減することがありますが、にもかかわらず同じ人数で運営していれば、費用対効果が著しく悪化します。
店舗ごとの売上推移や時間帯別の来客数を分析したうえで、人員配置を見直すことが必要です。
「念のため」といった感覚で厚めに人員を配置していると、売上の少ない日でも人件費が膨らみ、人件費率が高止まりする要因になります。たとえば、金曜夜は混雑しても、月曜や雨天の日には来客数が半減することがありますが、にもかかわらず同じ人数で運営していれば、費用対効果が著しく悪化します。
店舗ごとの売上推移や時間帯別の来客数を分析したうえで、人員配置を見直すことが必要です。
高コストなメニュー構成や非効率な調理工程が利益を圧迫している
メニュー構成や業務の進め方自体が、FLコストを押し上げているケースもあります。
・高コストなメニュー構成: 高原価でも注文の少ないメニューや、使用食材が多く在庫管理を複雑化させるメニューは、ロスを引き起こす原因にもなります。
・調理工程の非効率: 調理に手間がかかる複雑な工程は、スタッフの作業負担を増やし、結果的に人件費率を押し上げます。
さらに、現場の判断が属人化し、FL比率の確認や対策が後手に回ると、改善PDCAが形骸化し、経営悪化のリスクが高まります。
店舗経営を数字で動かす|FLコスト改善の実践ステップ
FLコストの重要性は理解していても、「何から着手すべきかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、FLコストを継続的に改善するための実践的な手法について紹介します。
毎月のFL比率を数値で算出し、適正値と差分を把握する
まず現状のFLコストを数値として明確に把握することが出発点となります。毎月の数値をもとに分析すれば、根拠ある改善策の立案につながります。
食材ロスの原因を数値で特定し、廃棄率を継続的に改善する
食材ロスの削減は、FLコスト改善において最も効果が表れやすい取り組みの1つです。
ロスを記録するだけではなく、下表のように「誰が・いつ・なぜ廃棄したのか」を明確にしたうえで、廃棄率(月間廃棄原価 ÷ 売上高)を継続的に計測し、改善状況を定点で確認する体制を構築することが重要です。
ロスを記録するだけではなく、下表のように「誰が・いつ・なぜ廃棄したのか」を明確にしたうえで、廃棄率(月間廃棄原価 ÷ 売上高)を継続的に計測し、改善状況を定点で確認する体制を構築することが重要です。
| 廃棄理由 | 月間廃棄量(kg) | 金額換算(円) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 仕入れ過剰 | 20 | 12,000 | 40% |
| 賞味期限切れ | 15 | 9,000 | 30% |
| 調理ミス | 10 | 6,000 | 20% |
| 提供遅延など | 5 | 3,000 | 10% |
| 合計 | 50 | 30,000 | 100% |
人時売上高を基準に、シフト配置と労働時間を最適化する
人件費を適切に管理するには、「人時売上高(売上÷労働時間)」を基準とした数値に基づく判断が求められます。たとえば1日の売上が20万円で、スタッフの総労働時間が40時間なら人時売上高は5,000円となり、飲食店における目安として妥当といえます。
これを下回る場合、人員配置の過多や業務の非効率化が疑われ、時間帯や曜日による売上変動に応じて、無駄のないシフト設計を行う必要があります。さらに、AIを活用した自動シフト作成やセルフオーダーの導入により、労働時間の最適化と業務負担の軽減が図れます。
これを下回る場合、人員配置の過多や業務の非効率化が疑われ、時間帯や曜日による売上変動に応じて、無駄のないシフト設計を行う必要があります。さらに、AIを活用した自動シフト作成やセルフオーダーの導入により、労働時間の最適化と業務負担の軽減が図れます。
POSや分析ツールを活用し、FLコスト管理を仕組み化する
FLコストの管理を属人的な判断に委ねるのではなく、POSレジや仕入れ管理システムを活用して仕組み化することが、持続可能な利益体質を築くポイントとなります。
・POSレジ:売上・食材費・人件費をリアルタイムで可視化し、日次・週次でのFL比率変動を確認。
・仕入れ管理システム(「BtoBプラットフォーム 受発注」):店舗ごとの仕入れ単価や発注データを一元管理し、「理論原価」と「実際原価」の差を正確に把握。
・メニュー管理ツール(「メニューPlus」):仕入れ状況とレシピ情報を連動させ、メニューごとの原価差異を分析し、改善の優先順位を明確化。
こうしたツールを活用すれば、現場の感覚に頼らず、数値に基づく判断と改善が定着し、店舗全体でPDCAを回せる体制が構築されます。
経験と勘に頼らず、数字で未来を読み解く飲食経営へ
FLコストは、飲食店経営における利益を左右する重要な指標です。これまで経験や勘に頼ってきた経営判断も、FL比率を軸とした数値管理によって、再現性と説得力を持った意思決定へと変わります。
数字をもとにした経営は、銀行融資や新規出店時の信用力向上にもつながります。今後は、POSや分析ツールを活用しながら、全店共通の判断基準と改善サイクルを確立することが重要です。数字で未来を見通せる飲食経営を目指して、仕組み化を進めていきましょう。
数字をもとにした経営は、銀行融資や新規出店時の信用力向上にもつながります。今後は、POSや分析ツールを活用しながら、全店共通の判断基準と改善サイクルを確立することが重要です。数字で未来を見通せる飲食経営を目指して、仕組み化を進めていきましょう。
日々の発注を賢く、FL管理をラクに!