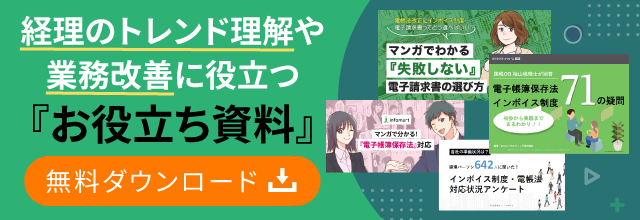最終更新日:2025年07月02日
IFRSは、国際的に通用する会計基準として注目されており、日本でも導入が進んでいます。一方で、「日本基準とどう違うのか」「導入にはどのような効果があるのか」といった疑問を持つ方も少なくありません。そこで本記事では、IFRSと日本の会計基準との違いのほか、導入によって期待される効果や懸念される課題、導入ステップ、注意点などについて解説します。
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化
目次
- IFRSとは、グローバルで通用する会計基準のこと
- IFRS導入が広がる背景
- IFRSと日本の会計基準は何が違う?
- 会計基準の考え方
- 利益計算のアプローチ
- 財務諸表の構成・利益区分
- 連結財務諸表の考え方
- 収益認識のタイミング
- 無形資産・のれん・研究開発費の取り扱い
- リース取引・固定資産の取り扱い
- IFRS導入で期待される効果
- 海外からの資金調達がスムーズになる
- グループ全体の財務情報を統一できる
- グループ全体の財務情報を統一できる
- 実態に即した財務状況を把握できる
- 企業価値が高まる
- IFRS導入により懸念される課題
- コストがかかる
- 実務の負担が増える場合がある
- 運用への負担が大きい
- IFRS導入の3つのステップ
- 1. 分析・評価
- 2. 導入
- 3. 運用・改善
- IFRS導入の注意点
- 導入のタイミングを綿密に練る必要がある
- 初度適用の規則に従う必要がある
- 資産の時価評価が求められる
- 会計システムや人材の整備の必要がある
- IFRSの導入には、適切なシステムを活用しよう
- よくあるご質問
IFRSとは、グローバルで通用する会計基準のこと
IFRS(International Financial Reporting Standards:国際財務報告基準)は、国際会計基準審議会(IASB)が策定する、国際的に統一された会計基準です。日本語では「アイエフアールエス」や「イファース」あるいは「アイファース」と呼ばれ、「国際会計基準」と表記されることもあります。
IFRSの最大の特徴は、世界の資本市場における財務情報の「透明性」と「比較可能性」を高めることを目的としている点です。このため、グローバルに展開する企業や海外投資家にとって、IFRSに準拠した財務諸表は非常に信頼性の高い情報源となります。
現在、IFRSは140ヵ国以上で導入されており、EU、韓国、ブラジル、オーストラリアなどでは上場企業に対して適用が義務化されています。こうした背景から、IFRSは世界標準の会計基準としての地位を確立しているといえるでしょう。
一方、日本ではIFRSの強制適用はされていませんが、上場企業を中心に任意適用が進んでおり、今後さらに広がると見込まれています。国際競争力を高める上でも、IFRSの適用は重要な選択肢となっているのです。
IFRS導入が広がる背景
かつては国ごとに独自の会計基準が用いられており、企業の財務情報を国際的に比較することは困難でした。しかし、経済のグローバル化が急速に進んだことで、異なる国にまたがる企業活動が一般的となり、共通の会計基準が必要とされています。
このような背景のもと、国境を越えて企業の財務情報を正確に把握・比較できるIFRSの重要性が高まり、導入が進んでいるのです。
IFRS導入により、企業の財務情報の透明性が向上し、投資家や金融機関にとって理解しやすくなることで、海外からの資金調達や市場での信頼性が高まります。
特に、海外展開を進める企業では、現地子会社との会計基準の統一が必要となるケースも多く、グローバル化の進展とともにIFRSを採用する企業が増加しているのが現状です。
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化
IFRSと日本の会計基準は何が違う?
IFRSと日本の会計基準(日本基準)は、さまざまな点で異なります。ここでは、IFRSと日本基準の具体的な違いについて項目ごとに解説します。■IFRSと日本基準の違い
| IFRS | 日本基準 | |
| 会計基準の考え方 | 原則主義 | 細則主義 |
| 利益計算のアプローチ | 資産・負債のアプローチ | 収益・費用のアプローチ |
| 財務諸表の構成・利益区分 | 包括利益計算書など、区分表示義務 | 損益計算書など、区分表示の義務なし |
| 連結財務諸表の考え方 | 経済的単一体説 | 親会社説 |
| 収益認識のタイミング | 履行義務の充足時 | 実現主義から履行義務の充足時へ |
| 無形資産・のれん・研究開発費の取り扱い | 時価評価、非償却、条件付きで資産計上可能 | 時価評価なし、償却、原則費用処理 |
| リース取引・固定資産の取り扱い | 実態重視、範囲広い | 法人税法基準、範囲狭い |
会計基準の考え方
IFRSと日本基準の違いとして一番に挙げられるのが、会計基準の考え方の違いです。
IFRSは「原則主義」を採用し、会計処理の基本原則のみを示して詳細なルールは企業の判断に委ねます。これにより柔軟な対応が可能ですが、財務諸表には判断根拠を示す注記が求められ、専門的な知識や適切な判断力が必要となるでしょう。
一方、日本基準は「細則主義」で、詳細なルールや数値基準が定められており、処理の統一性は高いものの、柔軟性には欠けます。
利益計算のアプローチ
IFRSと日本基準では、利益をどのように算出するかというアプローチにも明確な違いがあります。IFRSでは「資産・負債アプローチ」を採用しており、貸借対照表(バランスシート)を重視して利益を計算します。特に、公正価値(フェアバリュー)評価が取り入れられている点も、IFRSならではの特徴です。
一方、日本基準では「収益・費用アプローチ」が中心で、損益計算書(P/L)をベースに実現主義で利益を算出します。
財務諸表の構成・利益区分
IFRSと日本基準は、財務諸表の名称に違いがありますが、下記のように主な書類は共通しています。<IFRSと日本基準に共通する主な財務諸表>
・貸借対照表(IFRSでは財政状態計算書)
・損益計算書(IFRSでは包括利益計算書)
・キャッシュフロー計算書
・株主資本等変動計算書
IFRSでは、日本基準でいう「損益計算書」と「その他の包括利益計算書」を統合した、「包括利益計算書」の作成が求められます。
ただし、IFRSと日本基準では、利益区分について大きな違いがあるので注意しましょう。
IFRSは、「継続事業からの当期利益」と「非継続事業からの当期利益」を、明確に区分して表示することが義務付けられています。
一方、日本基準は事業の継続性に関する区分表示の義務付けはありません。
>
連結財務諸表の考え方
IFRSと日本基準では、連結財務諸表の作成に対する基本的な考え方にも違いがあります。IFRSでは「経済的単一体説」を採用し、企業グループ全体を1つの経済単位として連結財務諸表を作成します。
一方、日本基準では「親会社説」にもとづき、親会社の株主に有用な情報提供を重視するのが一般的です。これにより、少数株主持分の扱いなどに違いが生じます。
収益認識のタイミング
収益をどのタイミングで計上するかという点も、IFRSと日本基準では異なります。IFRSでは「履行義務」にもとづき、契約上の義務を果たした時点で収益を認識します。つまり、商品やサービスが顧客に引き渡され、契約にもとづく義務が果たされた段階で、初めて収益が計上されるという考え方です。
日本基準は従来、「実現主義」にもとづき、商品が出荷された時点や代金が確定した時点など、より具体的な事実をベースに収益を認識していましたが、近年ではIFRSに近い基準を導入し、収益認識のタイミングの差は縮まりつつあります。
無形資産・のれん・研究開発費の取り扱い
無形資産やのれん、研究開発費の会計処理についても、IFRSと日本基準では違いがあります。これらの項目は、企業の将来価値を左右する重要な資産であるため、その会計処理の違いは投資家に与える印象にも影響します。それぞれの項目ごとの基準の違いは、下記のとおりです。
■無形資産・のれん・研究開発費の取り扱いの違い
| IFRS | 日本基準 | |
| 無形資産 | ライセンスや顧客リストなど、将来の利益が見込まれるものは時価で認識可能。 | 法律上の権利に限定。時価評価は行わない。 |
| のれん | 償却は行わず、毎期減損テストを実施。 | 取得後、20年以内で定額償却。 |
| 研究開発費 | 開発段階の費用で将来利益が見込まれるものは資産計上可能。 | 原則、すべて費用処理。資産計上は認められない。 |
リース取引・固定資産の取り扱い
リース取引や固定資産の会計処理も、IFRSと日本基準で明確な差があります。IFRSではリース取引のほとんどを貸借対照表に計上するため、資産計上の範囲が日本基準よりも広いのが特徴です。一方、日本基準では、ファイナンス・リースのみ資産計上し、オペレーティング・リースは原則として費用処理(オフバランス)となるため、資産計上の範囲が狭いといえます。
しかし、2027年4月以降開始の事業年度から適用予定の「新リース会計基準」では、日本基準もIFRS第16号に準拠し、ほとんどすべてのリースを貸借対照表に計上する方式へと移行します。これにより、従来オフバランスだったオペレーティング・リースも資産・負債として認識されるため、企業の財務諸表や財務指標に大きな影響を与えることになるでしょう。
また、固定資産の耐用年数についても、IFRSは実態に即して柔軟に設定可能です。日本基準は法定耐用年数や付随費用の範囲が限定的なため、実態との乖離が生じることがあります。
今後は新リース会計基準の導入により、日本基準とIFRSのリース取引に関する会計処理の差が縮小し、国際的な財務諸表の比較もしやすくなることが期待されています。
IFRS導入で期待される効果

IFRSを導入することによって、どのような効果が期待されるのでしょうか。ここでは、IFRSを導入することで期待される具体的な効果について解説します。
海外からの資金調達がスムーズになる
IFRSは国際的に広く採用されている会計基準であり、IFRSに準拠した財務諸表は、海外投資家や金融機関にとって信頼性が高く、理解しやすい情報源となります。これにより、企業はグローバルな資本市場での資金調達を、より円滑に行えるようになるでしょう。
また、IFRSは財務諸表の比較可能性を高める仕組みでもあるため、同業他社との比較も容易になり、投資家にとって魅力的な企業として映る効果も期待できます。
グループ全体の財務情報を統一できる
IFRS導入により、国内外の子会社や関連会社を含めた企業グループ全体で統一した会計基準を用いることができます。これにより、各社が同一のルールにもとづいて財務情報を作成できるため、連結処理がスムーズになり、決算のスピードと精度が向上します。さらに、経営陣がグループ全体の経営状況をタイムリーに把握できるため、意思決定の迅速化や経営の透明性の向上にもつながるでしょう。
海外企業と同一の基準で比較できる
IFRSは国際的な企業の多くが採用している会計基準であるため、IFRSを導入することにより、海外企業との財務情報の比較が容易になります。これにより、企業の実力や競争力を正確に評価できるようになり、企業側もグローバルな競争環境での自社の位置付けを把握しやすくなります。
また、投資家にとってもIFRSに準拠した財務諸表は読み慣れている形式であるため、企業価値の評価がしやすくなり、企業にとっては資本市場での信頼性向上も期待できるでしょう。
実態に即した財務状況を把握できる
IFRSは、公正価値評価や包括的な情報開示を重視しており、企業の経済的実態をより正確に財務諸表へ反映できます。資産や負債を時価で評価することで、将来のリスクやキャッシュフローも反映され、経営者や投資家は企業の真の財務状況を把握しやすくなるでしょう。なお、2027年1月以降に開始する事業年度から、新しい基準であるIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」が適用される予定です。
IFRS第18号は、これまで財務諸表の表示方法を定めていたIAS第1号に代わるもので、IFRS第18号の適用開始と同時にIAS第1号は廃止され、今後はIFRS第18号が新たな表示・開示のルールとなります。
これにより、損益計算書の「営業」「投資」「財務」の3区分や、営業利益の表示が義務化され、企業の財務状況の比較可能性や透明性がさらに高まることが期待されています。
企業価値が高まる
IFRSを導入することで、財務情報の透明性と信頼性が向上し、投資家や顧客からの信頼を得やすくなります。国際的に認められたIFRS基準に準拠した財務諸表は情報の信頼性が高く、グローバルな投資家や顧客にとって安心材料となるでしょう。また、財務情報の精度と一貫性が増すことで、企業の経営戦略や財務体質が明確に伝わりやすくなり、長期的に見て企業価値の向上に寄与します。
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化
IFRS導入により懸念される課題
IFRSには多くのメリットがありますが、その導入には一定の負担やリスクも伴います。ここでは、IFRSの導入により懸念される、主な課題について解説します。
コストがかかる
IFRSを導入するには、多くの場合、初期投資が必要となります。既存の会計システムの改修やシステムの新規導入のほか、会計方針や業務マニュアルの整備、従業員研修、外部コンサルタントの活用など、大企業であっても数千万円単位、中小企業ではそれ以上のコストがかかることもあるでしょう。
加えて、導入後もIFRSに準拠した財務諸表の作成や、頻繁に改訂される基準への対応といった形で、継続的な運用コストが発生します。
実務の負担が増える場合がある
IFRSは原則主義のため、会計担当者の判断が求められる場面が増えます。これにより、手間や業務負荷が増加することが懸念されるでしょう。具体的には、取引ごとの会計処理についての判断基準や背景説明を注記として記載する必要があり、そのための判断根拠や記録作成に時間と労力がかかります。
さらに、社内での判断基準の統一やトレーニングも不可欠で、これらが不十分だと判断のばらつきやミスが生じるリスクも高まります。
運用への負担が大きい
IFRSを導入した後も、その運用には継続的な労力とリソースが必要となります。特に、IFRS特有の会計処理や頻繁な改訂への対応、専門的知識の維持・更新が求められるため、運用面での負担が大きい点は否めません。まず、IFRSは国際基準であるため、英語での原文確認が必要になる場面も多く、一定の語学力と専門知識を併せ持つ人材が欠かせません。また、IFRSの用語や概念は日本基準とは異なる部分が多く、制度の理解と定着には時間とコストがかかります。
さらに、IFRSは世界の経済状況やビジネス環境に対応するために、頻繁に改訂されます。そのたびに新しいルールを学び、会計システムや業務フローを見直す必要があるため、実務担当者にとっては大きな負担となるでしょう。
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化
IFRS導入の3つのステップ
IFRSの導入は一朝一夕にできるものではなく、企業の規模や事業内容に応じて段階的に進める必要があります。ここでは、IFRSの導入プロセスを、3つのステップに分けて紹介します。

1. 分析・評価
IFRS導入の第一歩は、現状の会計・業務体制を正確に把握し、IFRS導入が自社にもたらす影響を分析・評価することです。まずは導入の目的を明確にし、経営層の合意を得た上で、専門部署やプロジェクトチームを立ち上げましょう。
次に、自社の現行の会計処理とIFRSとのあいだにどのような差異があるかを洗い出し、財務諸表や業務プロセス、経営管理制度への影響を評価します。また、グループ会社が複数ある場合は、それぞれの会計処理の状況を把握し、連結上の課題も考慮しなければなりません。
これらの情報をもとに、導入までのロードマップや必要なリソースを明確にし、経営層や関係部署との合意形成を図ります。最終的には、全社的なプロジェクト計画を策定し、導入に向けた準備体制を整えることが、IFRS導入の成功へとつながります。
2. 導入
分析・評価で得られた情報と計画をもとに、導入フェーズでは実際にどのような会計方針を採用するかを決定し、具体的な運用に落とし込むための差異の明確化・検証を行います。この段階では、財務諸表の試作や、財務会計ソフト・ERPシステムの対応など、実務に即した形で日本基準との差異がどのように現れるかを再度確認します。
また、IFRS導入は親会社だけでなく、国内外の子会社・関連会社にも影響を及ぼすため、グループ全体での統一した対応が不可欠です。
さらに、実務担当者や経営層へのトレーニングを行い、IFRSの基本概念や具体的な会計処理を理解させ、日常業務に活かせるよう教育体制を整えます。こうした多面的な準備と調整が、円滑な導入につながるのです。
3. 運用・改善
IFRS導入後は、実際の会計処理や財務報告をIFRS基準で行う、運用・改善に移行します。この段階では、IFRSに準拠した会計方針や業務手順にもとづき、四半期・年度ごとの財務諸表を作成し、継続的な実務運用を行います。運用開始後には、分析段階で想定できなかった課題や改善点が明らかになることも多いため、定期的なフィードバックを通じて、業務フローや会計システムの設定の見直し、内部統制の見直しを行い、運用体制の最適化を図りましょう。
また、IFRSは頻繁に改訂されるため、新たな基準やルールが公表されるたびに、社内の対応方針を見直し、必要な教育やシステムの改修を継続的に実施することが求められます。
IFRSの導入は、単なる基準適用にとどまらず、企業文化としてIFRSを根付かせ、持続的な改善と発展を目指す姿勢が重要です。
IFRS導入の注意点

IFRSの導入を成功させるためには、単に会計処理を切り替えるだけでなく、導入に伴うさまざまなリスクや制度上の要件に注意を払う必要があります。続いては、IFRS導入時に、特に注意すべき点を解説します。
導入のタイミングを綿密に練る必要がある
IFRS導入には多くの準備期間とリソースが必要であり、拙速な導入は混乱やミスの原因となります。1、2年程度の準備期間を設け、会計方針の整備や既存のシステムの改修、社員教育、業務プロセスの見直しなどを段階的に進めるのが一般的です。
グループ会社・海外子会社の対応も含めて、決算時期や経営戦略との整合性を考慮し、最適な導入時期を慎重に検討しましょう。
初度適用の規則に従う必要がある
IFRSの初度適用時には、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」に従う必要があります。この規則では、移行時の特例措置や開示義務が詳細に定められており、誤った対応をすると財務諸表の信頼性や法令遵守に支障をきたす可能性があります。特に重要なのが、「2期間分のIFRS財務諸表」の開示義務です。初めてIFRSを適用する期(当期)だけでなく、その前年度(比較対象期間)についてもIFRSにもとづいた財務諸表を作成しなければなりません。これにより、過年度との比較可能性が確保され、ステークホルダーに対して適切な情報開示が可能になります。
また、初度適用時には、日本基準からIFRSへの会計方針の変更や調整項目について、詳細な注記や移行調整表の作成も求められます。これらの開示は、財務諸表の透明性を確保する上で不可欠なプロセスです。
資産の時価評価が求められる
IFRSでは、資産や負債の公正価値評価が重視されます。これにより、財務諸表はより実態に即したものとなりますが、日本基準の取得原価主義とは異なり、評価額の変動幅が大きくなる場合があります。このため、評価の対象となる資産の洗い出しや、適切な評価方法の選定、時価の根拠となるデータの収集と管理が必要となり、企業の会計・財務部門には高い実務能力が求められます。
特に、非上場株式や不動産など、市場価格の把握が難しい資産の時価評価には、専門的な知識と慎重な判断が欠かせません。
会計システムや人材の整備の必要がある
IFRS導入・運用には、専用の会計システムの導入とIFRS対応人材の確保・育成が不可欠です。日本基準とは異なる処理や開示が求められるため、従来の仕組みやスキルでは対応が困難なケースも多く、早期からの準備が重要です。まず、会計システムについては、IFRS特有の会計処理(のれんの非償却、公正価値評価、履行義務基準にもとづく収益認識など)に対応できる機能が必要です。既存の会計ソフトでは対応しきれない場合もあり、システムの見直しや再構築が求められることもあります。
また、連結決算やセグメント情報の開示など、グループ全体の財務情報を統合管理できる仕組みも必要です。
加えて、実務担当者には国際会計の知識だけでなく、英語による基準文書の読解力も求められるため、社内での人材育成だけでなく、外部の専門家やコンサルタントと連携する体制も整えておくといいでしょう。
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化
IFRSの導入には、適切なシステムを活用しよう
IFRS導入には、単なる会計基準の切り替えだけでなく、実務の複雑化や情報開示の高度化に対応するためのシステム整備が不可欠です。資産・負債の時価評価や収益認識、セグメント情報の開示など、多岐にわたるIFRS特有の処理を正確かつ効率的に行うには、IFRS対応の会計システムが大きな力を発揮します。「BtoBプラットフォーム 請求書」は、多様な会計ソフトと連携し、請求書処理を電子化・自動化できるクラウドサービスです。会計ソフトと連携して使用することで、IFRS対応に伴う業務負荷やミスの削減、業務効率化を実現します。
IFRS導入を成功させるためにも、ぜひ「BtoBプラットフォーム 請求書」の導入をご検討ください。
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化
よくあるご質問
Q. IFRSとは何ですか?
IFRSは国際会計基準のことで、企業の経営状況を国際的に比較しやすくするための会計基準です。2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)が新しい会計基準を公表し、2027年4月1日以降に開始する会計年度から上場企業・大企業に対して強制適用されることが決まっています。Q. IFRSと日本の会計基準との違いは何ですか?
日本の会計基準とIFRSには異なる部分が多く、2007年に一度国際基準に近づける改正が行われましたが、2016年にIFRS16が発表されたことで再び違いが顕著になりました。具体例として、リース会計では、IFRSではすべてのリース取引を貸借対照表に計上(オンバランス)することが求められますが、日本の現行基準ではそうした要件はありません。Q. IFRSの読み方は?
International Financial Reporting Standardsの略で、「アイエフアールエス」、「イファース」、「アイファース」などと読みます。監修者プロフィール

宮川 真一
岐阜県大垣市出身。1996年一橋大学商学部卒業、1997年から税理士業務に従事し、税理士としてのキャリアは20年以上たちました。現在は、税理士法人みらいサクセスパートナーズの代表として、M&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。あわせて、CFP®(ファイナンシャルプランナー)の資格を生かした個人様向けのコンサルティングも行っています。また、事業会社の財務経理を担当し、会計・税務を軸にいくつかの会社の取締役・監査役にも従事しております。
【保有資格】CFP®、税理士
請求書を電子化して、経理業務のコスト削減!
BtoBプラットフォーム請求書の詳細はこちら
『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書の発行も受取もデジタル化!
『BtoBプラットフォーム 請求書』は、国内シェアNo.1* の電子請求書システムです!
- 特徴
- ご利用企業115万社以上
- 請求書の発行も受け取りもデジタル化