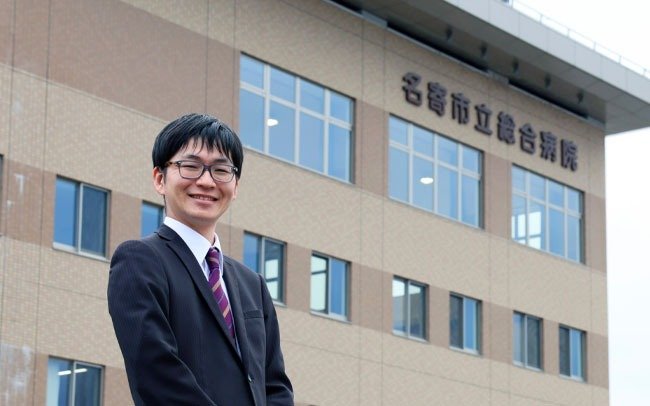北海道北部の基幹病院として、救急医療のような重症患者に対する高度な医療提供を担う、名寄市立総合病院様。市内外の関係医療機関や調剤薬局等と、医療介護情報をネットワークで連携するなど、ICT活用にも取り組んできました。コロナ禍を機に、テレワーク対応が可能な体制を構築すべく、請求書の受取をデジタル化。BCP対策だけでなく、紙や作業時間の削減など大きな効果が得られています。
ココがPOINT!
-
1
財務会計システムとの連携で支出伝票を一括起票
-
2
ペーパーレスで請求書の紛失リスク減、検索性アップ
-
3
作業時間を減らし、より経営改善に直結する業務へ注力
年間2万枚にのぼる伝票の処理に追われる
名寄市立総合病院の概要を教えてください。

経理係 係長
事務部 総務課 経理係 係長(以下、同):
名寄市は、旭川空港から北へ車で2時間の場所に位置する、北海道北部の中心的な都市のひとつです。人口は2万5,000人弱、基幹産業は農業で、特にもち米は日本一の作付面積、アスパラガスは北海道有数の作付面積・収穫量を誇ります。冬は平均気温-9℃、1~2月には-15℃を下回る日も多く、国内トップクラスの積雪量と雪質をアピールして、ウインタースポーツの大会や合宿の誘致にも取り組んでいます。
名寄市立総合病院は、22の診療科と359床の病床があり、名寄市内のみならず、上川北部地域という、東京都の総面積の倍ほどのエリアの救急医療を担う道北地方の基幹病院です。また、国より研修医や特定看護師(医師の診療補助を行う専門性の高い看護師)などの教育機関にも指定され、人材育成のための体制整備を行っています。
2020年には、地域の病院や自治体などが協力して質の高い医療を効率的に提供するための地域医療連携推進法人制度により「一般社団法人上川北部医療連携推進機構」を設立しました。全国でもまだ40事例ほどの制度ですが、近隣の士別市とも連携を深め、人材交流や薬品・診療材料などの共同購入など、地域の病院を超えた連携を推進しています。
所属されている事務部総務課経理係について教えてください。
事務部は院内の事務全般を担っており、保険請求などの医療事務に関わる医事課と、それ以外の事務処理を行う総務課に分かれています。総務課の中でも経理係は会計業務の他に、財務や契約、中長期計画の策定など多岐にわたる業務を担っています。また、医療機器やカテーテルなどの医療物資から事務用品まで、さまざまな物品の購入や在庫管理、価格交渉などを行う、用度という業務も担当しています。人員は3名で、他に、用度の院内物流担当の5名がいる体制です。
少人数で、多くの業務をこなしておられますね。
限られた人員でさまざまな業務を行うには、バランスを考慮しなければなりません。たとえば受け取った請求書の処理など会計業務に求められるのは、正確さと、期日を守るスピードです。請求書の紛失や伝票の誤入力といったケアレスミスで事業者にご迷惑をおかけするわけにはいきません。しかし、繁忙期にリソースを割いて対応しても病院の業績向上には直接つながりません。むしろ、在庫管理や価格交渉を行う用度などに注力したほうが収支は改善する可能性はあります。システム導入で省力できる業務はデジタル化するなど、経営改善に向けた取り組みを強化したいと思っていました。
請求書業務のどういったところが課題でしたか?
公立の病院経営においては、物品購入時等の支払いにあたって、法令に規定された所定の手続きを必ず行わなければなりません。その手続きで作成する支払伝票は年間4,000枚から5,000枚程度発生し、請求書や明細もあわせると年間で2万枚あまりにのぼります。どれぐらいの紙なのだろうと、保管用の分厚いファイルに綴じた状態で重さを量ってみると、なんと約85キログラムもありました。
月締めで請求書が届くと1事業者の明細だけでも最大で数十枚にのぼります。明細のすべてを少数のスタッフの手作業でシステム入力するのは不可能なので、伝票には合計金額と債権者である事業者や口座情報等の最低限の情報のみ入力し、詳細は糊付けされた紙の請求書の明細をめくって確認せざるをえませんでした。過去の取引の詳細を確認したい場合があってもデータのみでは内容がわからず、必要に応じて書庫で紙のファイルをひっくり返して探さないといけない状態です。また、手入力である以上、誤記載などのヒューマンエラーが排除しきれないと感じていました。
地方公営企業法の財務は、すべての伝票が整った後に審査して支出しなければなりません。審査を担う市長部局は、車での移動が必要な別の建物にあり、月末になるたびに全ての帳票類を衣装ケース2箱に詰めて運んでいました。これは伝票だけでなく医療機器の購入や保守点検といった支払いの根拠となる書類なども含まれるので、相当な重量になります。一人で運搬するのはかなり大変ですし、無理に運べば腰を痛めるリスクもあります。
また、公立の病院ならではの事情として、数年おきに人事異動があります。地方公共団体の会計制度は、単式簿記が一般的ですが、病院は複式簿記を採用しており、異動してすぐ業務を把握するのは困難です。システム導入で仕訳の精度を高めるなど、効率のよい運営は考えていかなければならないだろうと感じながら業務にあたっていました。
コロナ禍をきっかけに、請求書の受取業務をデジタル化
電子請求書の導入を検討しはじめたのはいつからですか?
名寄市では、2013年に道北北部医療連携ネットワーク(通称:ポラリスネットワーク)という、地域医療に関わるICT連携をスタートさせています。名寄市立総合病院が中心となって、道北北部の医療連携からはじまり、今では名寄市内の調剤薬局、歯科医院、介護サービス施設・事業所および地域包括支援センターや名寄消防署救急隊も加わりました。患者様の情報を相互に共有し、処方データや検査データを共有して持続的で一貫性のある医療を提供する目的です。
そうした背景もあって、請求書業務にデジタルを受け入れる環境はある程度整っていましたが、導入検討が具体化したのは2020年の6月ごろです。新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大し、いつ院内クラスターが発生して執務室で業務ができない状況が起こるかわかりませんでした。
コロナ禍でよく耳にしたエッセンシャルワーカーというと医師や看護師を想像しますが、医療を継続的に提供するうえで、病院にとってバックオフィス業務は止めてはならない業務のひとつです。地域での感染者が増加するにつれ在宅勤務や遠隔地であっても請求書を受け取って支払いに向けた処理を進められる体制や、取引先の事業者にとっても、請求書を作成し押印、郵送するための出社が不要な体制を早急に構築したいと考えました。
請求書の受取業務に『BtoBプラットフォーム 請求書』を選んだ理由を教えてください。
請求書のデジタル化にあたって、請求書業務だけでなく、従来は紙でまわしていた稟議・承認フローもペーパーレス化できないと本当の効率化にはつながらないと考えていました。財務会計システムなど、他システムとの連携を前提に、CSVなどでデータが出力できて費用対効果が高いものを条件に選定にあたりました。
従来、請求書は発行側の記載が間違っていれば、電話で確認の上、郵送しなおしてもらっていました。そのような差戻しも画面上で完結できて、時間的に余裕が生まれるところもポイントでした。また、『BtoBプラットフォーム 請求書』は機械学習機能があり、一度入力すれば以降の勘定科目が自動選択されるので、懸案だった仕訳の精度も高められます。
導入にあたって、院内や取引先の反応はいかがでしたか?
例えば市役所と比較して、事務全般を所掌する部署が集約されている病院では、複数部署との合意形成をはかる必要がなく、導入自体はスムーズでした。従来の繁忙期、時間外労働しながら何とかこなしていた会計処理の作業時間をぐんと減らした上で、費用対効果も充分にあると説明できたので、院内のコンセンサスは容易に得られました。
取引事業者からも、おおむね好意的に受け止めていただきました。取引先は市内の事業者や、市内に支店を構える全国区の販売業者、また旭川市や札幌市などエリアも多岐にわたりますので、導入説明会は現地とオンラインの同時進行で実施し、大きな混乱はありませんでした。コロナ禍でデジタル・DXが急速に広がった時期でもあり、事業者側もデジタル化に取り組みやすい環境だったかと思います。
バックオフィスのスマート化で地域医療を支え続ける
現在の活用状況はいかがですか?
定期的に取引のある事業者の6割が『BtoBプラットフォーム 請求書』で請求書を発行しています。残りの4割は、既に別のシステムを利用していたり、パソコンになじみがなかったりで導入が難しい事業者です。とはいえ、4割の紙媒体の請求書も、別途電子保存とすることで、前述の課題を全て解決し、毎月の衣装ケース運びの重作業からも解放されてしまいました。紙の量自体も減って、年間の重量は85キログラムから37キログラムと、48キログロムほど減りました。重量が半分以下なので紙に換算すると、8,000枚ぐらいまで減った試算です。
現在は、『BtoBプラットフォーム 請求書』で受け取った請求データをCSVでダウンロードし、財務会計システムへ連携しています。明細までデータ化されて検索性は大いに向上しました。『BtoBプラットフォーム 請求書』と並行して文書管理システムやオンラインのファームバンキングの導入も進め、院内ツールで決裁から支払処理まで画面上で完結できるようになりました。
これまで月末になると2人がかりで一週間ほど毎日21時まで残業し、なんとか会計処理を間に合わせていました。今は基本的に残業はありません。時間外業務は劇的に減りました。時間に余裕が生まれたぶん、用度関係の価格交渉などが可能になりました。導入時の試算より業務量が減り、システム利用料などの支出を差し引いても、さらに大きな経済効果を得られています。
今後の展望をお聞かせください。
他の自治体でも同様かもしれませんが、人口減にともなうサービスの縮小は行政が抱える課題です。そんな中でも医療は提供できる体制を構築し続けないといけません。できるうちにバックオフィス業務をスマート化させ、少人数でも負担なく対応可能な体制を築きたいです。
ツールを導入しデジタル化しただけでは業務は効率化しません。業務を抜本的に見直し、バラバラのやり方を統合してこそ利益が享受できるので、なるべく処理を一元化に近づけ、ひとつのフローで全ての業務が終わる形にしたいと考えています。そのためにも、『BtoBプラットフォーム 請求書』の利用率は高めていきたいです。無理にお願いすることはありませんが、条件が揃えば導入可能な取引先もあるのではと思っています。
組織運営に必要な事務は、それぞれ別に動いているようでもどこかでつながっています。請求書業務以外のデジタル化、スマート化も前提とした業務の構成も考えていきたいですし、『BtoBプラットフォーム 請求書』はその実現に向けた、効果的なツールだと期待しています。
※掲載内容は取材当時のものです。